| 上白沢慧音さんの歴史講座「伝承文化と民間信仰」 | 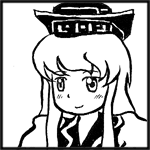 |
| ・節分儀礼と追儺 |
●蛇足の解説(節分と追儺)の巻
| 上白沢慧音さんの歴史講座「伝承文化と民間信仰」 | 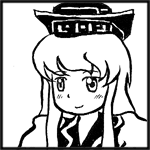 |
| ・節分儀礼と追儺 |
| さて、今回は節分儀礼をその元となった追儺について述べようと思う。 *** 少々錯雑だがその辺りは御容赦願いたい。 で、この解説方法なのだが、管理人が語り口に迷っていてな、今回は私が解説するという体裁にしたらしい。合わない人は申し訳ないが、少しばかり我慢して呉れ給え。 余談だが、本来種族が鬼の伊吹萃香殿が語る形式が相応しいと思われるのだが、管理人のPC はパワー不足で萃夢想が動かないらしい。で伊吹殿が居ないので、私が解説の代役を務めることに なったという訳なのだ。 *** それでは本題に入ろう。 追儺(ついな)とは宮中で行われていた年中行事の一つだ。元々は大陸で行われていた大儺の礼が、本邦にも取り入れられた訳だ。この儀式の形式は、おそらく、『唐書』「礼楽志」にあるような唐代の儀式が伝えられたものだろう。 本来「儺(だ)」とは疫病を駆逐するという意味を持つ。大陸では、この儀礼は季節の変わり目に行われていたらしい。その大儺の礼とは、方相氏が窮奇や騰根等の十二頭の野獣に扮したもの達と百二十人の子供を引き連れて妖魔を祓うというものだ。 我が国では儺遣(なや)らう、儺遣(なや)らい、鬼遣らいともいう。重要な宮中行事で、後世には変質しながら民間にも広がって行った。 追儺は既に7世紀頃には本邦に伝わっていたらしいが、『続日本記』の慶雲三年(西暦706年)に大儺が行われた記事があり、これが文献に表れた最初であるとされている。 *** ここで行事のあらましを見ておこう。 追儺は大晦日に行われる。これが行われている時には、禁中の所々に燈火を灯す。天皇は紫宸殿に出御、所司が承明門を開き公卿が参入する。そして黄金四つ目の仮面を被り玄衣朱裳をまとい、右手に桙(ほこ)、左手に楯を持った方相氏が※子(わらわべ)二十人(後には八人)を率いて南庭に参入。王卿は侍従、大舎人を率いおのおの桃の弓、蘆の矢を持って方相氏の後ろに列す。 (※は“にんべん”に“辰”と書く漢字である) 陰陽師は齋郎(さいのお)を率いて月華門より入り祭文を読む。 陰陽師の祭文が終わると、方相氏は「オニヤロー」と大声を発して桙で楯を三度打ち、群臣これに呼応して東西南北に別れて、桃の弓を射、疫鬼を駆逐する。そして群臣が方相氏の後に続いて振り鼓(でんでん太鼓みたいなものだな)をバラバラと鳴らしながら宮中を巡るのだ。 祭文についてだが、『延喜式』陰陽寮に祝詞の「儺の祭の詞」がある。 「今年今月今日今時 大宮内に神祇官宮主の祝ひまつり敬ひまつる 天地の諸御神たち平けくおたひにいまさふへしと申す 事別けて 詔りたまはく 穢く悪しき疫鬼の 所所村村に蔵り隠らふるをば 千里の外 四方の堺 東方陸奥 西方遠価嘉 南方土佐 北方佐渡より おちの所を なむたち 疫鬼の住みかと定め賜ひ 行け賜ひて 五色の宝物 海山の種種味物を給ひて罷賜ひ 移し賜ふ 所所方方に 急に罷往ねと追給うと詔るに 奸心を挟んで 留りかくらば 大儺公 小儺公 五兵を持ちて追い走り 刑殺物ぞと 聞き食ふと詔りたまふ」 *** 追儺で駆逐される「鬼」は、本来具体的な形を持たなかったのだが、方相氏の姿が恐ろしいことから、後世にはむしろ方相氏が鬼と見なされるようになってしまったのだよ。平安時代末期には後ろに付き従った群臣も、むしろ方相氏を追い回すように理解されたのだ。 つまり、追う者が何時の間にか追われる者となってしまったわけだ。これは、平安期に鬼の概念を用いて隆盛を極めた陰陽師達の、民間へと散っていった後の歴史を考え合わせると感慨深いものがあるな。 ……歴史とは皮肉なものだ。 *** さて、追儺は元々は年の瀬、大晦日の行事であったのだが、後世になると節分と追儺と豆撒きとが混淆するようになっていった。 節分とは季節の変わり目のことで、本来年四回あるものだ。しかし、特に重要とされた立春前、冬と春との節分を主に差すようになったのだ。これは旧暦で新年に当たる訳で、二十四節句が一巡して新しくなる時でもある。現在の太陽暦上では二月の三日か四日に当たる。 節分、つまり季節の変わり目の宮中行事には、例えば土牛童子(とぎゅうどうじ)というものもある。これは土で拵えた牛と桃の枝を持つ童子の像を宮城の東西南北の十二門に据えるというものだ。これも陰陽五行に基づく儀礼で、陰気を祓い陽気を迎え入れ春を呼ぶためのものだ。 *** これらのいくつかの節分の儀式が習合して豆打ちをする今日の節分儀式となったのだよ。 *** ところで、豆撒きは普通は、古代漢民族の持っていた大豆を用いた呪術を受け継いだものと言われている。穀物には生命力と魔除けの呪力が備わっているという信仰だな。室町時代、十五世紀頃には大豆を撒いて邪気を払う事が行われたことが文献からわかっている。 また、『臥雲日件録』文安四年(西暦1447年)の記事に「散熬豆因唱鬼外福内」とあり、既に「鬼は外、福は内」と唱えていたことがうかがえるのだ。 *** 結局、宮中では中世に廃れてしまったわけだが、逆に民間へは伝播して行く。例えば諸国の寺社では追儺祭が行われるようになった。神戸の長田神社などではその古式を現在でも伝えている。また、近代になって復興したものもある。現在京都の吉田神社や平安神宮で行われているものがそれだな。 因みに吉田神社では方相氏の仮面を象った土鈴が売られているぞ。 *** そうそう、方相氏は鳥山石燕の『今昔百鬼拾遺』にも描かれている。 ここで方相氏についても述べておこうか。石燕は四ツ目の鬼のような仮面を被った人物を描き、次のような詞書きを寄せている。 「論語曰 郷人儺朝服而立於*階 註儺所以逐疫周礼方相氏掌之」 (論語に曰く、郷人の儺(おにやらい)に朝服をして*階(そかい)に立てり 註に儺は疫を逐う所以(ゆえん)也 周礼に方相氏之を掌る) (*は“こざとへん”に“乍”と書く漢字である) これは『論語』にある言葉を引いたものだ。『論語』郷党篇にある言葉だな。読み下しは「郷人の儺(だ)には朝服して*階(そかい)に立つ」となる。孔子の隣人とのつきあいについて記した部分だ。村の人が鬼遣らいの行事をするときには、朝廷の礼服を着て階段の東側に立つ、という意味だ。当時堂宇の階段では、客は西の段から上がり、主人は東側から上がったという。 また、なぜ礼服を着て東側に立ったかというと、古注では先祖の霊が驚くことを恐れてと言い、朱子は誠を尽くして隣組の行事に参加したという意味だという。 *** 石燕によってもう一つ言及された『周礼』によると、方相氏は熊の皮を被り、黄金四つ目の仮面を付け、黒い衣を赤い裳を身につけ、矛と盾を持ち眷属を引き連れ悪鬼を追い、疫鬼を駆逐するものという。 本邦の追儺の方相氏がこの流れを汲むことは一目瞭然だな。 方相氏の由来については、伝説の聖帝である黄帝の后の一人が最初の方相氏という。彼女は醜かったが徳を持っていたという。これらのことは、例えば『軒轅本記』などに記されている。この書は白澤の由来も記されていることで有名(?)だな。ん、そうでもないのか。 大陸では後に方相氏は険道神、開道神と呼ばれる死者の棺を守護し、出棺の先導をする神となる。『酉陽雑俎』には、方相氏は棺に先立って墓に入り矛で四隅を撃って魍魎を駆逐するとある。 *** ただ、一筋縄ではいかないところが民間伝承の奥深いところだ。 追儺の鬼も単なる邪悪なるものとばかりは決めつけられぬのだ。そもそも追う者たる方相氏自身が鬼と習合してしまっているのだからな。各地の芸能にも鬼の如き仮面を被ったものが悪霊を追い払うというパターンが数多く見られるのだ。 さて、字義から語り起こすべき鬼についての話は尽きないが、きりがないし、今回の趣旨からはずれるので、この辺にしておこう。 |
*** 最後に此処で言うべきことかどうか迷ったが、少し私見を。 色んな伝承等を書き散らしている私が言えたものではないが、様々な伝承や地方の文化について最近気になることがあるのだ。 この数年、全国の小売り店舗で盛んに宣伝している恵方巻に端的に示されているのだが、本来ある一定に地域にのみあった習俗が、全国一律に、恰もまるでずっと過去から存在したかのように広められてしまう……。特にそれが商業主義と結びついて居る場合に、非常に危うさを孕んでいるよう感じられるのだ。 管理人の私見では、関東にはその習俗は薄く、神戸や大阪の商家の風習(特に大阪の芸者衆の間の風俗)ではないかということだ。なんでも周りの親戚から聞いたとかいう適当な話だがな。 とにかく習俗には、各地の固有の特徴があり、多様性がその特色の一つだと言って良いだろう。 ところが、いみじくも天文学者カール・セーガンが指摘したように、現在のように人も情報も、極めて急速に流動する社会では、その多様性が失われ文化が均質化、画一化してしまう危険性が否定できない。 グローバルな社会は長所もあるし、時の流れは止められない。文化の変化は仕方のない点も多いだろう。 けれど、私は伝統文化や伝承については出来るだけそうしたことに注意が払われるべきだと思うのだ。 卑近な例でも、「水子」の概念や「河童」の姿や名称など、長い伝統があるように思われて流布しているものが、実はごく最近になって変質したものに過ぎない場合が少なくない。 つまり、関東近辺の一名称に過ぎなかった「河童」と様々なメディアによって流布されたキャラクター化された画一的河童像が、現在では全国にあった多様な水怪像を駆逐してしまっているのだ。 こうした例は少なくはない。 多様性や地域性にもっと敬意を払うべきなのだ、と私は思う。 これを読んでくれた諸氏にこの点は是非伝えておきたい。 長々と悪かったな。 最後まで読んでくれてありがとう。 |
おまけの絵は「方相氏」。鳥山石燕が描いた衣装のバージョンで。
尻尾がないけど勘弁してね。
あれ?なんか閻魔様の服に似てる気が……。
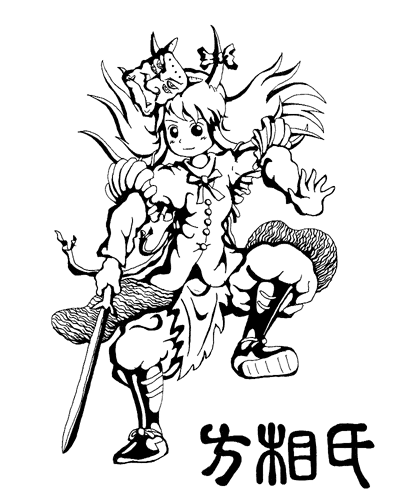
参考文献
・小松和彦ほか『日本民俗文化大系4 神と仏』小学館1983
・柳田國男「石神問答」、「巫女考」『柳田國男全集』筑摩書房1997
・国史大辞典編集委員会編『國史大辭典』吉川弘文館1979
・『論語』(『新釈漢文大系』明治書院』)
・笹間良彦『日本未確認生物事典』柏美術出版1994
・高田衛監修『鳥山石燕 画図百鬼夜行』国書刊行会
・多田克己『百鬼解読』講談社1999
ほか、民俗学、歴史学の諸文献、『広辞苑』等の辞書
柳田國男、小松和彦、京極夏彦、夢枕貘の諸氏の著書