![]()
○平成23年5月
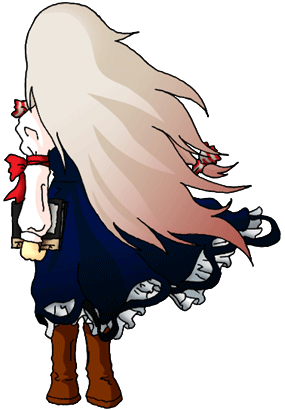 |
 |
命二ツの中に生たる桜哉
松尾芭蕉『野ざらし紀行』(※1)
 |
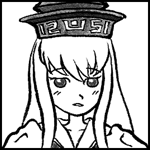 |
| 藤原妹紅 | 上白沢慧音 |
| ??? | :……〜い! ……先生!! :ああ、やっと見つけました。 |
| ??? | :お、おい。 :身体が弱いのだろう? 無理をするな。 |
| 髪飾りの少女 | :大丈夫ですよ、私だってそんなにやわじゃあありません。 :それにしても、こんなところで何してたんですか? |
| 長い髪の少女 | :いや、ちょっと古い友人を思い出していて、な。 |
| 髪飾りの少女 | :古い御友人ですか? |
| 長い髪の少女 | :桜の老木が好きだったんだ。たった一人で、よく眺めていたもんだ。 :独りで居る方が良いなんて言ってな。 :(……人一倍寂しがりやだったくせに。) :そう、あいつも……、この木のように静かに里を見守っていたんだ。 |
※ |
|
| 上白沢慧音 | :「命二つの…中に生きたる……桜かな」 |
| ??? | :松尾芭蕉かい? 相変わらず、博識だねぇ。 |
| 上白沢慧音 | :ああ、妹紅……。 |
| 藤原妹紅 | :何もこんな寂しいところで花見しなくても良いんじゃないか? |
| 上白沢慧音 | :ふふ。私はこの樹とこの場所が好きなんだ。……人間の里が良く見える。 |
| 藤原妹紅 | :―――、まあいいさ。 :芭蕉の句も良いもんだね。桜は和歌ばかりかと、何となく思ってたけど。 |
| 上白沢慧音 | :そんなことは無い。芭蕉に限ったって、有名な桜の句が幾つもあるぞ。 |
| 藤原妹紅 | :そっか。 |
| 上白沢慧音 | :この句は貞享二年(西暦1685)、芭蕉四十二歳の時の作で季語は春の「桜」、二十年ぶりに知人に出会った感慨を句にしたものと言われている。「水口にて二十年を経て故人に逢ふ」とあるからな(※2)。 :ああ、この場合の故人は死んだ人のことではなく、旧知の人という意味だがな。 |
| 藤原妹紅 | :あはは、そりゃそうだろ。幽霊譚じゃあるまいし。 |
| 上白沢慧音 | :この“故人”は芭蕉の門人である服部土芳のことだ。彼は芭蕉が東下した寛文六年(西暦1666年)にはまだ十歳の少年だったんだ。 :時経て桜の下で再会したとき、土芳は既に二十九。芭蕉は時の流れ速さと共に運命的なものを感じたのだろうな。 |
| 藤原妹紅 | :ああ、ニ十年というのは決して短い時間ではない。 :……気づけばあっという間だけど。 |
| 上白沢慧音 | :僅かな間で人は去り、景色さえも変わってしまう。人が同じ時間を共有していることは奇跡のようなものだ。かつて桜を共に見た者と年月を経て再び桜の樹の下で巡り合う。 :……「命二つ」とは、そんな運命さえも共に戴くという親愛と連帯感の込められた言葉なのだろう。 |
| 藤原妹紅 | :桜に託された遠い日の思い出と、今この時を生きているという実感か……。 |
| 上白沢慧音 | :そう、“生きたる”は二つの命と咲き乱れる桜の双方に効いているわけだ。 :桜の記憶というのは、しばしば幼い頃の思い出と深く結びついている。共に育った友人、学校の仲間たち、親兄弟、恩師……。それはいつの時代でも変わらないようだな。 |
| 藤原妹紅 | :うん。私たちの意識の中では、桜と命も分かちがたく結びついているね。 |
| 上白沢慧音 | :止まることの無い時の流れの中の命か……「年たけてまた越ゆべしと思ひきやいのちなりけり小夜の中山」 |
| 藤原妹紅 | :西行法師…か? |
| 上白沢慧音 | :ああ、芭蕉の句はこの歌をふまえたものと言われているな。 :もっとも、この句はそんな背景の知識などなくても心に響くものを持っている。 :出会いと別れ、生と死、移り行く儚さと繰り返される永遠。希望、感傷、そして諦観……私たちが桜の花に向かうときに抱く気持ちというのは、そうしたあらゆるをひっくるめたものなのだろうな。 |
| 藤原妹紅 | :命二つ、か。……まるで今の私たちみたいだな。 |
| 上白沢慧音 | :ん? |
| 藤原妹紅 | :勿論、年月を経て再会したわけじゃないけど、二つの命がこうして花咲く桜の樹の下で相対している。出会って、共に生きたこの時間。それはきっと運命的なものだし、正に奇跡そのものだよね。 |
| 上白沢慧音 | :……すまない妹紅。“通り過ぎる者”に過ぎない私には、そなたに生命や永遠について語る資格など無いのにな。 |
| 藤原妹紅 | :それは言いっこなし。 :別れを怖れてずっと忘れていた人との繋がりを、慧音は私に思い出させてくれたんだから。辛くても、苦しくても、それが人間なんだと、生きているということなんだと。 |
| 上白沢慧音 | :―――――。 |
| 藤原妹紅 | :ところで、里のお花見には行かないのか? |
| 上白沢慧音 | :え、ああ。堅苦しい私が居ない方が良いこともあるさ。 :私にはこの山の桜の老木が似合っている。 |
| 藤原妹紅 | :独り、誰にも知られずに里を見守るって訳か? ははは、慧音らしいな。 |
| 上白沢慧音 | :――花に礼いうわかれ哉。 :……妹紅。もし…、もしそなたが望むなら。私との思い出を無かったことにしよう。そう、あの時の出会いから……総てを。私には過去そのものを改変する力は無いが、思い出すことが無いようにすることなら出来る。 :私はそなたが命短き存在に対して深く関わることを避けてきたことを知っていた。それなのに、私にはそんなそなたへの配慮が欠けていた。私などのために気を使うことは無い。そしてこれ以上苦しむこともな。 :どんな人でも所詮生きるも独り、死ぬも一人。ならば……。 |
| 藤原妹紅 | :なあ、そんな悲しい事を言わないでくれよ。私が慧音と一緒に居るのは私自身が楽しいから、幸せを感じられるからなんだ。 :それに買い被りだって、私はそんなに他人ことを考えてやしないよ。 |
| 上白沢慧音 | :そう、なのか? 私はそなたを束縛したくないし、これ以上悲しい思いをして貰いたくないんだ。人は死んでも思い出の中で永遠に生きると言う。だがそれは言い換えれば死者が永遠に残された生者を束縛してしまうということだ。残される者にそんな事を強いるのは忍びない、私はそう思うんだ。 :“常に残される者”の気持ちが理解できるなんて言わない。だが私でさえ……、いや、そなたと比べたら無に等しい時間かもしれないがな。それでも、ずっと少ないとはいえ、多くの別れを、時間を共に出来ない苦しみ哀しみを経験してきたんだから。 |
| 藤原妹紅 | :ありがとう、慧音。心遣いはありがたく受け取っておくよ。でも、この思い出は二人のものだ。私のものでも、慧音のものでもない。私にとって、それはかけがえの無いものなんだ。だから決して失くさない、忘れない。たとえ慧音の願いでも。 :確かにね、誰もが皆先に行ってしまうのは悲しいことだ。何人も私と同じ時間を生きられない。それでも。それでも誰かと一緒に生きて、笑って、怒って泣いて……。それが生きることなんだ。 :この幻想郷で、私は取り戻したんだ。見失っていた生きることの意味を。そしてそれを教えてくれたのは、他ならない慧音じゃないか。 |
| 上白沢慧音 | :妹紅……。 |
| 藤原妹紅 | :だから、大切な思い出を無かったことになんて寂しいことを言わないで。人と人との絆を否定するようなことを言わないで。自分でも分かってるはずだよ。私が人として生きることを決めた――その後押しをしてくれたのは慧音なんだから。 :ほら、桜が私たちを見ている。そう、この木もいつか枯れるだろう。でもきっと新たな木がこの地に花を咲かせるに違いない。そうやって命は受け継がれていくんだ。永遠なんて、そんなものだよ。 :だから今この一瞬、二つの命がここにある。それでいいじゃないか。 |
| 上白沢慧音 | :いいのか。私はずっと一緒にはいられない。その日は必ず来るんだ。 |
| 藤原妹紅 | :ああ。いつか来る別れさえも、生きることの一部なのだから。 |
| 上白沢慧音 | :そうか、そうだな。……すまん。別れを怖がっていたのは、本当は私の方だったのだな。 |
| 藤原妹紅 | :善いんだよ。共に生きる喜びも、別れの悲しみも。総てあるがままに。 :だから今は笑っていよう。共に生きている、この輝かしき時を。 :(そして私は決して忘れないよ。たとえこの世界が貴女の存在を忘れてしまってもね。) :(そう、決して……) |
※ |
|
| 髪飾りの少女 | :さあ、早く行きましょう。みんな待ってます。 |
| 長い髪の少女 | :(……ああ、この桜はもう何代目だったか) |
| 髪飾りの少女 | :先生が居ないと始まらないんですよぉ。話を聞きたがってる奴が一杯来てるんですから。 |
| 長い髪の少女 | :む、あいつらか…、最近里にまで入り浸ってからに。 |
| 髪飾りの少女 | :良いじゃないですか、もう別に危険も無いんですし。 :それに私も聞きたいんですよ。いろんな話。先生が居ればみんなちゃんと話してくれるんです。私が取材しても嘘ばっかり吐くような連中なのに。 |
| 長い髪の少女 | :はは、そうか。 :(…じゃあ、行くよ。) :(安心してくれ。私は大丈夫。人間として生きてゆく意味を、悲しみも喜びも、…その全てを受け入れる勇気を、貴女が呉れたから) :もう私は独りじゃない。そして貴女も。 :……不本意かもしれないけど、貴女はいつでも私と、里の皆と一緒だよ。 |
| 脚注 | |
| ※1 | :『菊の香』には「命二つ中に活(いき)たる桜かな」とある |
| ※2 | :水口(現滋賀県水口町)は東海道の宿場町。句が作られた経緯については、『土芳筆全伝』に「是ハ水口ニテ土芳ニ玉ハル句也。土芳、此年ハ播磨ニ有リテ、帰ル頃ハハヤ此里ヲ出ラレ侍ル。ナヲ跡ヲシタヒ、水口越ニ京ヘ登ルニ、横田川ニテ思ハズ行逢ヒ、水口ノ駅ニ一夜昔ヲ語(かたり)シ夜ノ事也」とある。 |
参考文献
・大谷篤蔵・中村俊定校注『芭蕉句集』(『日本古典文学大系45』岩波書店1962)
・井本農一・堀信夫・村松友次(校注・訳)『松尾芭蕉集』(『日本古典文学全集41』小学館1972)