![]()
| さて、今回の建築探偵では、妖々夢、永夜抄の冒頭読み込み画面に登場する、屋根の装飾について見てみたいと思います。 対象とする画面は、両作品を起動したときに標示される画面です。文字の背景として、睡蓮の池(妖々夢)や月(永夜抄)と共にシルエットとして登場します。これは建物の軒先部分と考えられるのですが、その上に小さな像が載っています。今回のテーマは、この像は何なのかというものです。 ※[]内は一つの漢字を表します。 |
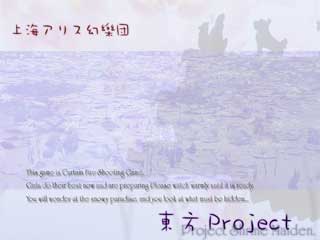 図1 「東方妖々夢」読み込み画面  図2 「東方永夜抄」読み込み画面 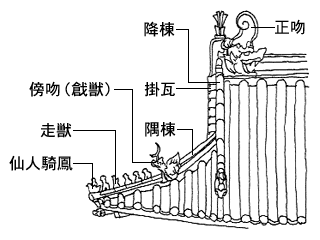 図3 入母屋屋根の装飾(中国建築) 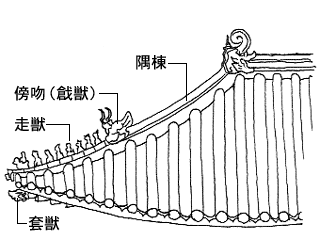 図4 寄棟屋根の装飾(中国建築) 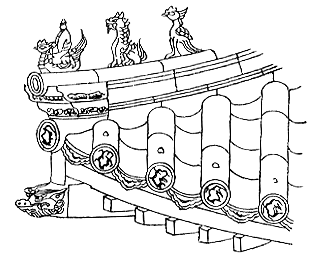 図5 脊獣/走獣(太和門軒先) (伊東忠太『東洋建築の研究』 図版64より)  図6 紫禁城内楼閣屋根 |
さて、図1が妖々夢、図2が永夜抄の起動画面です。向きが反対ですが、どうやら同じもののシルエットのようです。 先端には何かに乗った人物の像、その後ろには複数の動物の像が並んでいます。これは中国の建築に見られる屋根装飾と思われます。 ***** 中国の明・清時代の建物(宮殿、寺院)の屋根には、数種類の動物の形をした装飾が付けられました。通常陶製で、脊獣・走獣などと呼ばれています。大棟と四つの隅棟を五脊とし、そこを装飾する小像(神獣)を指して六獣と言い、併せて五脊六獣と総称します。 原型となった装飾はかなり昔から存在したようです。漢時代の埴輪には既にそれらしきものが見られ、宋時代の絵画からは小像が棟に並ぶ様子がうかがえます。また、元時代には武将の像が用いられたと言います。明・清時代を通し、次第に現在の形に完成されたと思われます。 大棟の両端部(日本では鯱の置かれる位置)には、正吻(せいふん)と呼ばれる大きな口の龍が置かれます。降棟の先端にもこれに似た龍の上半身が置かれ、これは旁吻(ぼうふん)あるいは[倉戈]獣(そうじゅう)と呼ばれます。正吻よりもやや小さく、枝状に分岐した角を持ちます。これは龍の九子の一ともされています(第二子)。これらは、日本の鯱と同じように、水を呼び火災を防ぐことを期待されたものと考えられています。 そして隅棟の先端には、脊獣が並びます。これがこの画面のシルエットとなっている像です。日本ではこれを鬼龍子と称する場合もありますが、あまり適当とは言えないようです。走獣、垂獣の呼称も、同じ装飾を指すようです。先頭には霊鳥に乗る仙人の像があり、その後ろに様々な霊獣が並びます。霊獣の順番や形態には様々なバリエーションがあるようです。これらの像はそれぞれ意味をもっていたとされていますが、現在ではその名称や像容、意味などについては、不明となってしまった点も多いようです。 なお、読み込み画面のシルエットでは分かり難いのですが、通常軒の下部にも龍頭のような装飾が設置されます。これは、套獣と呼ばれ、隅木に被せることでその先端を保護する役割を担っています。 屋根各部と装飾の名称や位置について、入母屋の場合を図3に、寄棟の場合を図4に、簡単な立面図として示しました。また、軒先部分の立面詳細図を図5に示しました。 ***** それでは脊獣について、さらに細かく見てゆくことにしましょう。 脊獣は隅棟に並んでいますが、建物毎に1,3,5,7体とあり、最大で10体となります。この数は建物のヒエラルキーを表しており、数が多いほど貴い建物ということになります。北京の紫禁城太和殿が10体であり、これが最大かつ唯一の例です。紫禁城(現故宮博物院)の様々な建物の屋根に注目すると、色々な数の脊獣が並んでいるのを見ることができます。(残念ながら、かつての旅行の時に撮った写真には、屋根が大きく写ったものは見つかりませんでしたので、図6に紫禁城内の別の建物の屋根の写真を挙げておきます) 十体の神獣については、名前と名称が伝わっていますが、先に述べたように、確実なものではないようです。例えば、『中国伝統図案系列』を引いた『図説社寺建築の彫刻』によれば、仙人騎鳳に続いて、麒麟、鳳凰、獅子、海馬、天馬、押魚、サン猊([獣偏に夋]さんげい)、カイ豸([獣偏に解]、かいち)、斗牛(とぎゅう)、行什と続くのだそうです。工匠に伝わったとされる文言は、「一龍二鳳三獅子,四天馬五海馬,六サン[獣偏に夋]七魚,八カイ[獣偏に解]九吼十猴」であるとされ、それぞれ神獣の名前を並べたものとなっています。 これらの個別の神獣についても記しておきましょう。 鳳凰に乗る仙人については、怪異を除いた太公望、あるいは治水で知られる帝王禹、周の敏王、周の敬王など、様々に伝えられているようです。像容は梅福仙人に似ているとも言われます。この仙人は日光東照宮の陽明門の彫刻に見ることができます。 龍や麒麟、鳳凰は良く知られた吉祥の神獣であり、仁政と王者の徳を表します。獅子は王権と聖山の支配を、天馬や海馬は皇帝の徳が天に通じ大海にまで至ることを象徴します。斗牛、押魚は雨をもたらし、火を鎮め災害を防ぎます。サン猊は獅子の別名(ライオンを意味するサンスクリット語のシンハSimhaの音訳)と言われ、虎や豹すら凌ぐ猛獣で、あらゆる動物の支配を象徴します。また、龍の九子の一(第八子)とされることもあり、その場合は煙を呑み霧を吐くという性質を持ち、香炉の魔除け文様として使われたと言います。カイ豸は、裁判が正しく行われている時に現れるとされ、皇帝の治世が公明正大なことを象徴します。行什は猿に似て(或いは有翼の人物)、行列の十番目に置かれることから行什の名を持つと言います。この猿に似た像と先頭の人物は、三蔵法師とお供の孫行者だとして語られることもあるようです。 下に、『図説社寺建築の彫刻』などによる、脊獣の姿を示します。いくつかの例を見た所では、これらの聖獣たちの姿は多種多様であり、ここに示すのはあくまで一例に過ぎません。角の数や脚の形状などが他の文献図像と一致しないものもあり、製作当初の名称と異なる可能性も指摘されています。 なお、これらの小像には、装飾や魔除け、火除けの他に、雨漏りを防止するという実際的な役割もあるそうです。 ***** |
|||||
 |
 |
 |
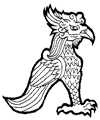 |
 |
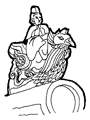 |
|
| No.5 天馬 | No.4 海馬 | No.3 獅子 | No.2 鳳凰 | No.1 麒麟 | No.0 仙人騎鳳 | |
 |
 |
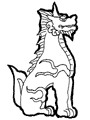 |
 |
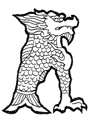 |
||
| No.10 行什 | No.9 斗牛 | No.8 |
No.7 |
No.6 押魚 | ||
 図7 藤井有鄰館(京都市)の屋根  図8 水原華城(韓国、水原市)の屋根 |
残念ながら、両作品での像容に当てはまるものは同定することはできませんでした。永夜抄で台湾関連の建物が幾つか取り上げられていることから、台湾にある建物のものかも知れません。三体目のシルエットが鼻の長い象のように見えるのが特徴と言えましょう。 日本でも、大陸風の意匠を持つ建物の屋根には、しばしばこれらの神獣が置かれています。中華街で探してみては如何でしょうか。変わったものには、伊東忠太設計の湯島聖堂があります。そこには、大棟に鬼犹頭(きぎんとう)と呼ばれる一種の正吻、降棟に鬼龍子と呼ばれる翼のある虎(旱獣(かんじゅう)、[馬芻]虞(すうぐ)とも)が鎮座しています。 ここには京都の藤井有鄰館の屋根の脊獣を示しておきます(図7,不鮮明な写真で申し訳無いです)。 日本で公的な建造物に用いられたことは無かったようですが、より大陸的な王朝を擁した朝鮮半島の宮殿建築には、これらの装飾用神獣が鎮座しています。例えば、ソウルに残る各種の李王朝の宮殿の屋根にそれらの例を見ることができます。左の図8に示したのはソウル近郊水原(スウォン)市の水原華城の建物の軒先です。 ***** 東方projectのタイトルに登場する、具体的な建物について、何か情報をお持ちの方は、是非ともご一報頂きたく、どうぞよろしくお願い致します。 |
参考文献
高藤晴俊『図説社寺建築の彫刻』東京美術1999
竹島卓一『中国の建築』中央公論美術出版1970
伊東忠太『東洋建築の研究』(上)龍吟社1936
三橋四郎『大建築学』(下)1908
劉敦楨『中国古代建築史』中国建築工業出版社1984
『建築大辞典』彰国社1993
御指摘や御意見等が御座いましたら、掲示板かメールなどにて遠慮無くお寄せ下さい。