次頁へ
| 目次 |
|
| 前ノ段 | |
| 第一ノ舞 | 伎樂 開眼供養 |
| 幕間狂言 | 地獄變 |
| 第二ノ舞 | 古樂 山の神の唄 |
| 第三ノ舞 | 聲名 萬燈萬華 |
| 幕間狂言 | 修羅 |
| 第四ノ舞 | 今様 紺青鬼 |
![]()
| 藝能とは、諸人の心を和らげて、上下の感をなさむ事、壽福増長の基、 遐齢延年の方なるべし 世阿彌「奥義云」『風姿花傳』 |
||
※ |
||
|
|
||
| 前ノ段 | ||
※ |
||
| 今は昔、旅を続ける楽人の一座がおりました。神々に奉納する舞を得意とした彼女たちは、村から村へと移動しながら暮らしておりました。いつの頃からか、その見事な舞は、鬼神も心を動かすとの評判を受けるようになっておりました。 それはある山の麓の村での出来事でした。鎮守の社で舞を奉納した後、どこからともなく現れた身形の良い若者が、主人の下で舞を披露してもらいたいとの依頼を楽人たちに告げたのです。 その屋敷が山中にあるということを聞き、村人は不審がって引き留めましたが、楽人たちは若者の熱心な様子に心動かされ、山の中へ向かったのでありました。 日も暮れ、墨を流したような闇の中で楽人たちが案内されたのは、とても小さな部屋でした。その薄暗い片隅に、主らしき人物と数名の人が待っているのが感じられました。彼女たちは不安な気持ちを抱きながらも、心を込めて舞を始めたのでした。 ところが、ふと気がつくと、そこは山中とは思えぬ立派な御屋敷の中だったのです。縁の向こう側には何十もの蔵が建ち並ぶ様が見て取れました。楽人たちは多くの灯りが点された、絢爛豪華な設えの古風な御殿の広い座敷で、主人一家を前に舞っていたのです。その後ろに居並ぶ大勢の下人たち、美しい装束の家族、それはまるで夢の中の景色のようで、御伽噺の龍宮や桃源郷とは斯くやと思わせる、それは見事なものだったのです。 館の主は楽しそうに彼女たちに語りかけました。 「評判をお聞きして、ついつい無理なお願いをいたしました。このような見事な舞は本当に久方ぶりでございます」 そして舞が終わると山海の珍味が振る舞われ、彼女たちは夜更けるまで豪華なもてなしを受けたのです。御殿の中には様々な宝が満ち、子供たちの笑い声が聞こえていました。そこでは人々は最高の幸福に包まれているように見えたのです。ただ、後に楽人の一人は思い出したそうです。上機嫌な主の後ろで、家宰らしき老人と妻らしき女性が物悲しげな様子をしていたということを。 次の朝、朝露にぬれて目覚めた楽人たちは、そこが荒れ果てた山中の原野の一角であることに気がつきました。辺りにあるのは古い井戸の跡と、散らばった冷たい瓦けばかりでありました。そして麓の村人の話を聞いて、彼女たちはようやく悟ったのです。 そこは遙か昔に没落し、荒野と化した長者屋敷の跡だったのでした。彼女たちが見たのは長者一族のかつての姿、華やかなる古の幻想であったのです。 そう、清らかなる舞は遙かなる過去をも招き返したのでありました。 |
||
※ |
||
| 藤原妹紅は独り、月明かりの中、夜道を人間の里の方向へと歩いていた。 慧音は私に何を見せるというのか。 ―――見せたいものがある、慧音は珍しく強い調子でそう言ったのだ。 私は誰の助けも借りずに生きてきたし、これからもそうするつもりだ。誰の助けもいらない。私は一人で生きていくんだ。 妹紅は思う。最近慧音はちょっと五月蠅い。人間の里へ来いとか、巫女と話してみろとか……。そして妹紅は博麗の巫女を思い出し、少し鼻白んだ。あいつは私に手加減無しで弾幕を打ち込むようなやつじゃないか。それにあの時はああ言ってはいたが、生き肝だって喰いかねない。 人間の里、人々の暮らし……。妹紅は再び考えを元の方向へと戻す。……里に暮らす人間達と積極的な関わりを絶ってからどのくらいになるのだろう。改めて考えてみたのだが、どうにも記憶に靄がかかったようではっきりしない。此処に辿り着くまで、私はどうしていたのだろう。 だが、妹紅はすぐ疑問を振り払い、過去のことを考えるのを止めた。今更人間と関わっても良いことなど有るはずがない、互いに苦悩が深まるだけなのだ。いや、互いにではない、残されるのはいつも私なのだから……。これまでもそうだったし、きっとこれからもそうだろう。 私は人間だけど、やっぱり人間じゃない。そんなことは自分でも良く解っているのだ。人として生きるなど笑わせる。そんな思いはもう遙か昔に燃え尽きた。 妹紅は思う。今の私の心には曇りも影も無い。たとえ欠けた部分があるとしても、それは永久に埋められることはないのだから。いや、むしろ欠けた心こそ我が姿そのもの。そしていつもの考えへと戻ってくる。そう。私は一人で生きてきたし、これからもずっと一人で生きていくのだ。いや死なずに存在し続けるだけだ。 人間の里へと通じる峠道の途中、小さな空き地がある。慧音はそこで待っているというのだが。 妹紅は暗く茂った雑木林を抜け、空き地へと踏み出した。そこには……。 |
||
| ▲ | ||
|
|
||
| 第一ノ舞 伎樂 開眼供養 | ||
※ |
||
| 宜しく天下の諸國をして、各敬んで七重塔一區を造り、并に金光明最勝王經、妙法蓮華經、各一部を冩さしむべし。 ……冀ふところは聖法の盛んなること、天地と共に永く流へ、擁護の恩、幽明に被らしめて恒に満たむことを。 其れ造塔の寺は、兼て國の華たり。必ず好處を擇びて、實に長久なるべし。 ……尼寺には一十尼ありて、其の寺の名を法華滅罪之寺と為す。 『続日本紀』 |
||
※ |
||
| 木々が影が切れたその空き地には、月の光があふれていた。月光は、淡く輝く冷たい水のようにそこを満たしていた。中央には古式ゆかしい装束を身に着けた上白沢慧音が独り佇んでいた。その周囲には、月の光と夜の冷気が硬く艶やかな結晶のように集まり、近寄り難い雰囲気を醸し出していた。 藤原妹紅は息を呑んでその様子を見つめていた。突然結晶が砕け、辺りは煌めく小さな光で一杯になった。どこからか音楽が聞こえてくる。舞が始まったのだ。 ああ、こんな華やかで美しいものがあったのだ。天から降ってくるが如き音楽に合わせ、月の光を浴びて舞う慧音を眺めながら妹紅は思った。……音楽は使い魔達が奏でているのだろうか。今ではもう廃れてしまった古い楽器の古い音だ。……流石博識な慧音は使い魔の使い方も違う。有職故実に則った、……そう、私も知っているはずだ。 蘇る朧なる記憶を辿りながら妹紅は考える。これは伎楽だ。……なんだか懐かしい。遙かな過去、まだ世界が小さかった頃に聞いた音楽だ。 そう、あれは確か……。 |
||
※ |
||
| 巨きな堂宇の前に設けられた舞台上での華やかな舞、響き渡る楽器の音。舞い落ちる五色の蓮弁と風に翻る五色の幕、美しい錦の幡をたなびかせる竿の上部には、燦々と輝く金色の鳳凰が地上を見下ろしている。 貴賤、老若男女を問わず、大勢の人が詰めかけていた。正面の舞台上では伽藍落成を記念する様々な儀式が厳粛に進められて行く。 その人混みの中、貴族達から遠く外れた小さな席の端に幼い藤原妹紅は居た。傍らには母が居る。その面影はもはや記憶の彼方に霞み、朦朧としてはっきりとは見えなかった。それでも母は美しかった。 後ろに控える守役のじいの声が聞こえる 「姫、あれに見えますのがお父上の建立された大伽藍でござりますぞ」 何もかもが華やかで、ふわふわとした高揚した気分だった。 この時の他に母と外出した思い出は無い。初めての、そしておそらくは唯一の母との遠出だったのだ。 やがて、金堂前の壇上に煌びやかな装束を着けた男性が現れる。それが彼女の父だった。位を極めた妹紅の父は、そこで貴賤を問わず、多くの人々の祝いの言葉と賞賛とを受けていたのだった。 妹紅には、華やかな舞台に立つ父が眩しく見えた。晴れやかなその姿が自分のことのように嬉しかったのだ。羨望と畏敬の籠められた視線を一身に集める、その姿が。 父はあちこちの席を順に廻っていた。高僧たち、皇族、貴族達……。彼方の上席から次第にざわめきが近づいてくる。そして父は妹紅たちの前に歩み寄ると、彼女を抱き上げ、優しく笑いかけてくれたのだった。 たった一度だけの、かすかな記憶。ずっとずっと、その時の父のぬくもりが忘れられなかった。 何時も一人だった母、私の記憶の中の朧なる母は、何時も哀しげだ。世間と交わることも無く、華やかな文化と関わることも無く、ひっそりと孤立した世界で私たちは生きていた。伽藍とした我が家、虚ろな空間。決して貧しくは無かったけれど、私たちの周りには、埋め難い寂寞さが常に立ち籠めていた。 ……それは、もしかしたら私のせい? 今思えば、私は屋敷の外にはほとんど出して貰えなかった。ああ、私は望まれない子供だったのか。 母の悲しみも、私の憧れも、決して満たされることは無かった。栄華を極めた筈の父に、私たちが何かをして貰った記憶は、ただあの一日を除いて全く無い。私と母の日々の暮らしは、繁栄にも権力にも無縁だった。でも。それでも。それでも私は父が誇らしかった。そして父が恋しかった。 だけど、やっぱり、いくら恋しくとも、自分なりに諦めはついていた。そう、それは私達にはどうしようもない、仕方がない事なのだ。父は大事な仕事をしているのだから。多くの人々の命にまで関わる、大切な仕事に就いているのだから。そう自分に言い聞かせていたのだ。そして信じていたのだ、人臣位を極め、華やかな世界で暮らす父は幸せなのだと。だから寂しくはない、……はずだったのだ。 きっと、幼い自分を支えていたのは、そこには居ないはずの父の存在だったのだろう。それなのに―――。 ある日、私は父の栄光に影が差したのを理解した。そして周囲の雰囲気が、僅かずつ歪んでいったことにも、私は気が付いた。母もじいも何も言わなかったけれど、我が家は何も変わってはいないように見えたけれど。私にはその僅かな変化を感じ取ることが出来たのだ。 そして、私は知ってしまった。……あいつのことを。 父の没落はあいつのせいだった。 あいつが。 あいつのせいで。 僅かに甦った幼い日々の淡い思い出が、暗い瞋りに塗りつぶされてゆく。 もう、あの日の気持ちには二度と戻れない。 |
||
※ |
||
| 「……父様」 気が付くと、夜が明けかかっていた。舞は終わった。 |
||
| ▲ | ||
|
|
||
| 幕間狂言 地獄變 | ||
家が燃えていた。屋根が、床が、屏風が燃えていた。熱い熱い。 恐怖に駆られながら、私は母の姿を求めて辺りを見回す。母は、母は何処に居るのだろう。 「姫、お逃げ下され」 「私めは必ず後ほど」 世話係の老人が私を屋敷の外へ押し出してくれた。屋敷がもう手が付けられない状態であることは明らかだった。だが独りになった私は母を捜して引き返す。 ああ、どこもかしこも煙で、真っ赤な炎で一杯だ。炎が私を追ってくる。紅い紅い、目の前が真っ赤に染まり、何も考えられなくなる。そして血の匂いと、真っ赤な炎が辺りに満ちる。血?何故血の匂いがするのだろう。この紅いモノは火ではないのだろうか。 頭を振って気を取り直すと再び私は母を捜す。ふと気付くと、騎馬の武者の影が屋敷の回りにちらちらと見える。検非違使だろうか。何故だ、何故もう検非違使などが屋敷の近くにいるのだ。余りにも早過ぎはしないだろうか。 何故?……まさかあのことが。 あのことは誰も知らないはずなのに。 気が付くと母が坪庭を挟んだ向かい側の縁に立っている。母は私の姿をじっと見ている。ああ、その目は優しく、厳しく、そして儚げで……。 「■■、■■■■■■」 私を見た母の唇はそう動いた。 ……ああ、それは私が捨てた名だ。それは私が普通の人間だった頃の、永遠に失われてしまったものの象徴だ。幼い妹紅はいつの間にか「今」の妹紅になっていて、周りは急速に色褪せた「過去」と変じて行く。――――はて、その後母は何と言ったのか、思い出せない。……その時母は私の姿に何を見たのだろう?母は何を知っていたのだろう?……あの時の私には解っていたはずなのに。 そして母は悲しげに私に微笑みかけると炎に包まれた自らの房へと戻り、二度と現れることは無かった。それが私の見た母の最後の姿だった。 荒れ狂う紅蓮の炎、逆巻く黒煙、そんな中で、私は燃え落ちる屋敷の上に輝く巨大な火の鳥の姿を幻視した。何故かもう火は恐ろしくなかった。私は魅入られたようにその姿を見つめていた。……やがて私は深紅の炎がたまらなく欲しくなった。這い回る舌のような火焔も、天を焦がす火の粉も、素晴らしい魅力的なものに見えてきた。突然私はそんな自分が恐ろしくなった。そしてひたすら目を瞑り、火に背を向けて走り出したのだ……。 私は逃げた、家から、炎から、微笑む母から、そしてかつての自分から……。 こんなはずではなかったのに。私は炎は嫌いだったはずなのに。本当は何も燃やしたくなかったのに。 結局私独りが生き残った。 ……戻る場所はもう無かった。 |
||
| ※ ※ ※ |
||
第二ノ舞 山の神の唄 へ続く |
||
| ▲ | ||
| こんなものを付けて見ました。当に弱気の至り。 もし何か思うところがございましたら……。 |
|
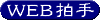 |