| 次頁へ |
蓬莱の舞(2)
| 次頁へ |
| 第二ノ舞 古樂 山の神の唄 | ||
※ |
||
| 山村にして遠野よりさらに物深き所には、また無数の山神山人の伝説あるべし。 願はくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。 柳田國男『遠野物語』 |
||
※ |
||
| 慧音からまた呼び出された。今日も何か見せられるのだろうか。心の底に押し込めていた記憶が呼び出されてゆく予感に不安が募る。だが妹紅には、空き地へと向かう歩みを止めることができなかった。 ああ、空き地の中央に慧音がいる。彼女の周りにあるのは……、雪? ゆるゆると唄が響いてくる。腹の底に染み渡るような不思議な旋律だ。はて、どこかで同じような唄を聞かされたような気がする。失われた過去が蘇る。 そう、大きな、暖かい手が、私は……。 |
||
※ |
||
| あれから何年経ったのか。 ―――私は山の中で暮らしていた。 あれからどのようにして此処に辿り着いたのか、私には記憶がない。ただ苦しくて、寂しくて。……死ぬことはなくとも、傷つけば痛いし、お腹も空く。雪の山中で動けなくなった私を助けてくれたのが、「彼」だった。 「彼」は人里離れた山中で暮らす山の民の一人だった。「彼」は食べ物も道具も、日常生活に必要な殆どの物を山から得ていた。豊かな山の恵みを得て、「彼」は日々を送っていたのだ。 一方で、「彼」にはどこか都人の俤があった。極く稀に出会う仲間の山の民とは異なる、そこはかとない雅な雰囲気が、ちょっとした言動の端々から感じられたのだ。しかし、「彼」は自分の生い立ちや、山で生きるようになった理由を私に語ることはなかった。代わりに「彼」は何故私が山中にいたのかについても何も聞かなかった。私にはそれが有難かった。だから「彼」が山で暮らすようになった理由を私は知らない、「彼」は何も話さなかったし、私も尋ねることはなかった。でも……、今ではその理由が分かる気がする。 思い返してみれば、私は「彼」の本当の名前も年齢も知らなかった。今となってはその顔さえ朦朧たる靄の向こう。ただ、大きく優しかったことを憶えている。 しかし、「彼」は里の民からは山爺とも山人とも呼ばれて畏れられていたのだ。里の者も「彼」も同じ人間なのに。いや、共に暮らした私には判る。「彼」の方が余程人間的だと。むしろ里の者の方が、何でも妖怪呼ばわりして殺してしまう恐ろしい鬼の如き存在ではないか。私は、里の民が外部から訪れる者たちを異人と称して迫害する姿を何度も見ていた。 白髪の私を「彼」は「雪子」と呼んだ。私は「彼」の呼び方に従った。……もう私にとって、名前などどうでも良い事だった。……もしかすると、その名前は「彼」にとっては意味があったのかも知れない。だが、今となっては、真実は膨大な時の彼方へと消え、もはや確かめる術はない。 そして一方で里の者は、私を見かけると「もこう」と呼んで逃げたのだった。 「彼」は吾亦紅の「もこう」だよ、と言ってくれたが、私は本当のことを知っていた。里の者の言う「もこう」とは、人を喰らう化け物の名であることを。子守女は子供をこう叱っているのだ「こら、いい子にしてないと、山からモコウが来て喰われちまうよ!」 それでも、そんな里の事情は二人の山での暮らしに影を落とすものでは無かった。「彼」は様々な事を教えてくれた。食べ物の採り方、薬の処方、寝床の作り方、身の守り方等々、自然の中で生きる術を私は「彼」から学んだのだ。 そして私は「彼」と共に山中をくまなく歩き回った。時には大きな背中に負われて、断崖絶壁を下ったり、険しい峯を攀じ登ったりもした。そこで私は、外の世界に存在した美しい物を始めて知ったのだ。大いなる山の風景、可憐な高原のお花畑、大音響と共に流れ落ちる瀧、深淵に美しい水を湛えた山中の湖……。 時折、「彼」は唄を歌ってくれた。それは都では聞いた事の無い不思議な感覚のものだった。「彼」の大きな、暖かい手の中に抱かれ、私は何度もその唄を聞いたのだ。歌声は山々に響き渡り、聞く者に母なる山々と一体となる陶酔感をもたらした。 「彼」と共に生きたかけがえのない時間、それは私の長い長い歴史の中で、一際暖かく懐かしいものだ。「彼」の傍が、家を失った私にとって、始めての安心できる場所となった。そして、たとえ私が成長しない人間でも、この山の中でなら、「彼」となら、ずっと一緒に暮らしていけそうな、そんな気さえしていたのだ。だが。 穏やかな日々は、ある日突然終わりを迎えた。 里が山を侵した。 その日、山中で里の子供が罠に落ちたという。だが、私も「彼」も罠など使わない。おそらく里の誰かが私たちを標的として仕掛けた物に掛かったのだろう。冷静に考えれば里の者達も、そんなことに気が付かないはずはない。しかし、興奮状態に陥った里はもう収拾が出来ないようだった。―――あるいは、誰かが知っていていて煽動したのかもしれない。 やがて手に手に獲物を持った里人が山へと侵入してきた。山への畏れは恐怖へと変わり、恐怖は人を狂気に駆り立てたのだ。 殺せ殺せ殺せ殺せ殺せ殺せ殺せ殺せ。私は山裾から押し寄せる強烈な悪意に恐怖した。 話し合いが無駄だと覚ると、「彼」は私を連れて山道を逃げた。「彼」は抵抗しなかった。「彼」が狩りの時に見せる業を以てすれば、おそらく、鋤鍬鎌以外の獲物など持った事のない里人を撃退することなど簡単な事だっただろうに。「彼」は私の前に立って道を切り開き、逃げ道を作りながら進んだ。山の峻険な道を進んで行けば、やがて里人は追跡を諦めるだろう。「彼」の背中を追いながら、私はそう考えていた。里の人間にとってはともかく、私達にとっては大したことのない慣れた道、しかし、その油断が私の歩みを誤らせた。突然私は何かに足を取られ、道筋から滑落した。蹲る私に殺意に満ちた里人が迫る。その時――。 そうだ。私はその時、取り返しの付かないことをしてしまったのだ。―――私は「彼」を呼んだのだ、「助けて」と。ああ、それは結局「彼」にとって死を招く悪魔の囁きとなってしまったのだ。 「彼」は私を助けに戻ってきた。自分一人なら逃げられたのに。そして、里人達の恐怖と悪意の込められた白刃を私の替わりに受けたのは「彼」だったのだ。忘れようとしていた苦い後悔の思いが蘇る。 何故私は「彼」を呼んでしまったのだろう。私が言うべきだったのは、「私は死なない、誰も私を殺せない」という一言だったのに。否、黙って斬られれば良かったのだ。死なない様子を見せ付ければ、里人は怖れて逃げ出したかも知れない。そうだ、一撃を受けた後に死んだ振りをしても良かった。私はどんなに傷ついても死ねないのだから。……いくらでも手段は有った筈なのだ。 それなのに、なぜ私は「彼」を呼んでしまったのか。「彼」に危険が及ぶことは判っていた筈なのに。なのに、それなのに、私は「彼」に助けを求めてしまった。そんな時にまで、傷つく事を、痛みを恐れ、「彼」に甘えて。 ああ、きっと私は「彼」の姿に父親を重ねていたのだ。父親にも「彼」のように優しく接して貰いたかったのだ。守って貰いたかったのだ。だから……。 違う違う。「今の」妹紅は思う。そもそも、私が“力”を使えば良かったのだ。普通の人間が何十人いようと、“力”を使えば、追い払う事、いや皆殺しにする事でさえ雑作もない事だった筈だ。 だが、「彼」に助けを求めた私は“力”を使うことさえしなかった。私は「彼」に私の“力”を見せたくなかった。“力”を持つ故に、不死なるが故に、「彼」に嫌われるのが怖かった。又……、二度も捨てられるのは嫌だった。……そんな私の我が儘が、「彼」を殺してしまったのだ。 「……さあ行け。愛しき吾妹子よ」 「彼」の最期の言葉が私の記憶の中でこだまする。 「願わくは、そなたの往く道が幸福ならんことを……。 ……わたしは、いつまでもそなたとともに……」 「彼」は傷つきながらも両手を差し広げて仁王立ちとなり、里人の前進を阻んだ。……そして私を逃がしてくれたのだ。 真っ白い雪の上に真っ赤な血が広がってゆく。鮮やかな赤が視界を占める。 ああ、私の手はまた血塗れだ……。 「彼」の血が、幻の赤い血が、私をも亦、紅く染める。 |
||
※ |
||
| 私は山中へと奔り、妹紅となった。 |
||
| ▲ | ||
|
|
||
| 第三ノ舞 聲名 萬燈萬華 | ||
※ |
||
| 虚空尽き、衆生尽き、涅槃尽きなば、わが願いも尽きなん。 弘法大師空海『性霊集補闕抄』巻八 |
||
※ |
||
| 今日も妹紅は空き地へと向かう。 日一日と、自分の過去が呼び覚まされてゆく。それは彼女が意識の遙か深い底へと沈めた筈の記憶。それは忘れようとして心の奥へと仕舞い込んだ遠い思い出。 だが、その過去は、きっと向かい合わねばならない過去なのだ。誰であれ、他者と共に生きるのを望む者ならば、自らの過去から逃れる事は出来ないのだ。……それは生きるためには避けられない道なのかもしれない。妹紅はそんな事を思う。 ―――これまでは、忘れる事こそが生きるために必要なのだと信じてきたのだけれど。 明るい……。その揺らめく光は、暖かく、優しく周りを包む。それはまるで無数の灯明に照らし出されたかのように。流れ来る調子の良い歌声が、何と耳に心地良いことか。 空を見上げればそこには満天の星、星、星………。 |
||
※ |
||
| その僧に出会ったのは、確か深い深い山の中だった。そう、私は丁度その時、妖怪を山犬の群れごと焼き払ったところだったのだ。人の気配に気づいた私が振り向くと、若い僧と目が合った。 私はその僧が一目散に逃げ出すと思っていた。そして又、この地を離れなければならなくなるだろうとも。 自分達が理解できない対象に対して、人間というものは酷薄で容赦がない。私の能力を知った人間は、始めは私を恐れ、やがてあの手この手で排除を図るのだ。だが、何度もそんな体験を繰り返した私は、やがてそれを気にする事も無くなっていた。所詮人間などそんなものだ。新たな居場所を探すのが少し面倒だが、それだけだ。初めのうちは、逃げ出されると不愉快だったが、今ではもう慣れてしまった。 ところがその日、私の予想を超えた出来事が起きたのだ。 事もあろうにその若い僧は私の方へと歩み寄って来た。粗末で日に焼けた墨染めの衣、痩身ではあるがその両眼は炯々と輝いていた。若い僧は私の記憶にある大きな官寺の僧侶達とは全く異なる雰囲気を纏っていた。このような人里離れた所で唯一人で居る所から見ると、私度僧だろうか。 その僧は恐れる様子もなく私に近づくと、いきなりこんな事を語りかけてきたのだ。 「汝は………。そなた、もしや生命の深秘を、この世界の理を知る者ではないか?」 僧の問いかけは余りに唐突で、私は面食らってしまう。どういう積もりでこんな事を聞くのだろう? (何だ?此奴は) 私の見た目は幼い女の子の筈なのだ。そんな子供に尋ねるようなことだろうか。否、あの炎を見たのなら恐れるのが当たり前だろう。質問内容云々以前に、話しかけてくる事自体が異常ではないか。私は僧の目を見たが、その瞳の奥には知性の光が溢れていた。この僧は決して狂人ではない。 そして私は彼の中に“永遠に追い求める者”の姿を見たのだ。 そんなことを考えつつも私は答えた。「そんな事は知らぬ、私は唯の“人間”だ」と。 それを聞いた僧の残念そうな言葉が甦る。 「そうか……。そなた、雪山童子の物語を聞いた事は無いか? ―――いや、すまない。 私はこの世の真理が知りたいのだよ。世界の人々を救うために」 やがて若い僧は自らの思いを語り始めた。おそらく、自分の思いを打ち明ける相手に長い間恵まれなかったのだろう。どうせ相手なんて誰でも良いのだ、そう私は思っていたのだけれど……。 ――それでも、暫く聞いているうちに、私は知らず知らずのうちに彼の話に引き込まれていた。彼は情熱的に語り続けた。真摯に世の矛盾に憤り、人々に降りかかる災難や苦悩に心を痛めているようだった。そんな彼の言葉の端々からは、彼の持つ高い志を感じ取る事ができた。そこにあったのは若い理想への信頼と、無邪気な程の未来への希望。そして大きな野望………。 一介の私度僧が語るには余りにも大きな夢。だが、不思議な事に彼の話は奇妙な現実感に満ちており、絵空事には思えなかった。何時の日にか、彼の僧は必ず己の夢を実現するだろう。そう思わせる何かがあった。 「この世界を見ろ。苦しみと悲しみとに満ち満ちているではないか。その理由も決して一つではない。それは時には死であり、疫病だ。そして時には天災であり飢饉でもある。老いも若きも、富める者も貧しき者も……」 その日から、私達は時々会って話をするようになった。彼は私の存在の異常さを全く気にしなかった。私が何者なのかなど、彼の関心外の事であったらしい。私の疑問に対しても「そなたは私の話を聞いてくれるし、理解してくれる。それで十分ではないか」と答えるだけだった。 彼は己の夢や哲学、宗教理論を語り、時折私がこれまで見聞きした事や出会った人々について話した。今思い返せば、二人でいたほとんどの時間、彼がしゃべっていたように記憶している。きっと彼も、己の考えを私に向かって語りながら自分の中の迷いと対峙していたのだろう。 私の朧な記憶の中で、彼は語る。 「……私は南都で仏の教えを学んだ。それは執着を絶ち、此の世が空なることを認識することから始まる。そして輪廻転生を繰り返し、やがてそこから解き放たれて涅槃へと至ることを目指す。目指すは欲も苦しみもない透明で静寂な世界。これは確かに素晴らしい教えだ。………でも、本当にそれで多くの衆生を救えるのだろうか。今、この現世で、艱難と闘い苦しんでいる人々を救えるのだろうか。 もう少し生きたい。美味しいものが食べたい。そんな衆生の願いを無下には出来ぬ。子を、親を、妻を愛する心を捨てよとは言えぬ。 私は生きていることが、命への執着が悪いとは思えない。………私は生きて、そのままの人間として得られる悟りを目指そうと思う」 ああ、私は彼のこの考えに惹かれたのだ。 未来から「死」が消えたことで、同時に涅槃へと至る道も閉ざされたと思っていた。そのころの私は、死後に極楽浄土へと生まれ変わることが最大の幸福だという漠然とした知識を持っていたのだ。そう、死ねない人間は色鮮やかな後生を知ることはない。 だが、もしも現世にも救いがあるのなら、この無限の苦輪の中にあっても………。それは私には無間の闇の中に灯された、たった一つの希望の灯火のように思えたのだ。 彼とはどの位話をしただろうか。勿論いつも形而上の議論をしていた訳ではない。彼は変わった知識を沢山持っていたのだ。外国の言葉、呪文、そして薬の知識。加えて今で言う自然科学の知識も豊富だった。いつしか彼との対話は楽しみになっていた。 「………地形を見れば水脈がどこにあるか分かる。地面の様子を、岩の種類をしっかり観察すれば自ずからそれは見えてくるのだよ」 「………こんな変わった術を教わったのだが、そなた、これを知っているか? 南牟阿迦捨掲婆耶奄阿利迦麼利慕利莎縛訶……」(*) ―――――。 そして私は自分の事を彼に話した。人間にそんな話をしたことなど無かったのに。 私が老いも死にもしない身体であることも、過去の罪も。自分でも何故か分からなかったが、彼には何を話しても構わない気がしていた。事実彼は極普通に、まるで世間話を聞くかのように私の話を聞いてくれたのだった。憐れむでも蔑むでもなく、月並みな慰めの言葉も無かった。 「ははは。それは輪廻から解き放たれたと考えれば良いのだ。 この世界には絶対など無い。幸も不幸も捉え方だ。……まあ我等持たざる者のひねくれた智慧かもしれないがな。暗い運命さえちょっと考え方を変えるだけで、素晴らしい希望に変えることができるかも知れぬ。 そうだ、死を得られぬ事は、見方を変えれば闇を超越する事に他ならない。輪廻を繰り返して六道に迷うも又苦しみではないか。 見方や考え方で生き方を変える事が出来るなら、運命を受け入れて前向きに生きられる方が良いに決まっている」 彼はそんな事を言ったのだ。罪と迷いの深く暗い海の底に沈んでいるだけだった私にとって、それは新鮮な感覚だった。 彼は私に言う、いやそれは自分自身への言葉だったのかも知れない。 「生きとし生ける誰もが皆迷いの中にある。そなたはそれに気付いているだけましというものだ。 生きる意味など一生をかけても分からないかも知れぬ。しかし、だからといって己が生、己が死を直視せず、ただ時の過ぎ行くままに流されて生涯を送るのは愚かな事だ」 そう、私はその時あの言葉を知ったのだ。 「三界の狂人は狂を知らず、四生の盲者は盲を識らず。 生まれ生まれ生まれ生まれて生の始めに暗く、 死に死に死に死に死んで終わりに冥し」 思い出が次々と浮かび上がってくる。あの時と同じ感覚を持って、言葉が私の心に深く染み通る。言葉に感応するは心の奥の小さな小さな灯火。 「私も含めて誰もが皆、死を理解できてはいない。どうせ私達は、こうして在る限り死を体験することはできないのだから。その先に本当の死があるかどうかなど、些末なことに過ぎない。 そなたと私と、共に今を生きている。異なる事など何も無い」 「■■■■■。■■■■■■■■」 嗚呼、その時私は何と答えたのだろう。どうしても思い出せぬ。 「そなたは暗い輪廻から解き放たれた存在なのだよ」 それはたった一人の聞き手を前にした説法。 彼に出会うまで、私が聞いた話は全て人生の儚さ、空しさを語るものばかりであった。生きる事そのものが罪であると。俗世は穢れと苦しみに満ち、現世を離れる事こそが救いの道だと。 そう、彼は初めて私を、いや、生きる事を積極的に肯定してくれたのだ。 「此の世は美しい。人生は素晴らしいものだ」 彼はそんな私への気遣いを見せる一方で、こんなことも言った事もあった。 「そなたの思い、悩み、苦しみを知っても、それでも私は実の所そなたが羨ましい。 私にはやりたいことが沢山ある。いくらでも時間が欲しい。この宇宙の真理を知り、衆生を救う方法を学び、天災に備えるための灌漑治水を為し、疫病を克服し、多くの民に文字や英知を伝える。井戸を掘り橋を架けることも必要だ。仏門にある者は、現世での幸せをも与えられる者となるべきだと私は思うのだ。だが、それを成し遂げるには人の一生ではとても足りぬ。 此の世には理不尽な不幸が多すぎる。私は出来るならば総ての人を救いたい」 彼のその切実な願いは、単に長生きがしたい、老いたくないというものでは無かった。永遠の苦難を負ってでも彼には時が欲しかったのだ。その気持ちは永遠を背負う私だからこそ理解できたのだろう。そう、彼は永劫の恐ろしさ、苦しさを理解していたと思う。それでもなお、もし機会があれば彼は喜んで蓬莱人となっただろう。 私はそんな彼の使命感の強さに戦慄さえ覚えた。その一方で、むしろそんな彼が私は少し羨ましくもあった。私は希望も目的も持てず、無限の未来をどう生きるかさえ定かではなかったのだから。目的に向かって真っ直ぐに進む彼が羨ましかった。 |
||
※ |
||
| 彼に最後に会ったのは、いつだったのだろう。まだ寒さの残る早春だったか。 彼はいつもの場所で、いつものように私を待っていた。 「私は決めた。山を下りようと思う。 唐土へ渡って、真の教えを学びたい。それから、人々を俗世の悩みから救うための技術もな。 ……………。 ……一緒に行かぬか。山の外には、否大陸には広い世界がある。大勢の人との出会いもあろう。 彼の地には不死の仙術の話も多く伝えられているという。そなたのような者が居るかもしれぬし、何かそなたの為になる事が分かるかも知れない」 私は黙って首を振った。本当はとても嬉しかったのだけれど。 ……私の手は血塗られている。聖なる目的の同伴者には相応しくない。それに……、私は己が過去を思い出す。……あれ以来、私と関わった人間は皆不幸な最期を迎えている。きっと私のような、呪われた人にして人に非ざる者は辺りに不幸を呼び寄せるのだろう。 そんな私の気持ちを感じ取ったのか、彼は重ねて誘おうとはしなかった。 「きっと私は衆生を救う道を見つけてみせる。たとえどんなに時間がかかろうとも。―――そう、此の世の終わりが来るまで、我が願いは尽きぬ。 そして……、約束だ」 若き僧が別れ際に残した言葉を、今でははっきりと思い出す事が出来る。 「必ずそなたを救ってやろう。 たとえそなたが罪人でも、そしてたとえ不老不死の民であろうとも。 ………そして私はこのことを絶対に忘れぬ。たとえ数えきれぬ季節が我等の上を過ぎ行こうとも。 だから。 絶望が心を満たしても、苦しみに心が折れそうになっても、そんな時は思い出して欲しい。そなたを思っている人間が、少なくとも一人いることを」 彼の目が私をしっかりと見つめていた。彼も私の中に、自分と同質のもの、即ち“永遠に追い求める者”を見出していたのかも知れない。 言葉と共にその時の情景が鮮やかに甦る。彼は私の事を忘れないと言ってくれたのだ。山を下りてゆく若き僧の姿が脳裏をよぎる。 そして今、妹紅は慧音の言葉を思い出す。 「………彼はあの山に今でも居るのだそうだよ」 そうだった、私は確かに彼と約束したんだ……。 今の私に彼と相見える資格があるのだろうか。私は自問する。 永遠のこの命、どう使うかの答はまだ出てはいない。それでも。……煩悩即菩提。彼は私の暗闇を光明に、迷いを悟りに変える事を教えてくれた。そう、人生はこんなにも美しいと。 だから生きる事に後ろ向きではいけない。自分を、未来を諦めてはいけない。精一杯生きて、考えて、私なりの答を出すことが出来たなら。その時はきっと再び彼に会えるだろう。 私もこれまで多くの事を学んだ。沢山の出会い―――。 あれ……。私は独りで生きてきた筈なのに………。どうも記憶が混乱しているようだ。私の“歴史”の断片が、意識の底から断片的に浮かび上がってくる。 ああ、私はあの僧のことさえもずっと忘れてしまっていたのだ。私の事を忘れないと言ってくれた彼さえも。 それでも、あの僧はそんな私のことを覚えてくれているのだろうか。 (忘れられたくない) そう、過ぎ行く季節の中で、残されるのは常に私であった。私を知る者は常に先に逝き、当然忘れるのは常に私の方だった。だが今、私は漸く忘れられる悲しさ、恐ろしさを思い出した。唯一人、時の流れから取り残されてよりずっと忘れていたこの気持ちを。 (私の事を忘れないで) 「……決して忘れぬ」 そうだ、あの時私の心に一つの灯が点されたのだ。暗黒の中の光。私がこれまで闇に溺れることもなく生きてこられたのは、小さくとも未来に希望を見出すこの光があったからだったのだ。それなのに、私の欠けた心がずっとそれを忘れていたのだ。 いつか、その小さな光が幾千万の灯火となり、私の暗い心を明るく照らすようになる日が来るのだろうか……。 |
||
※ |
||
| 満天の星の下、幻想の灯明が妹紅を明るく照らす。たゆとう歌声は妹紅を包み込んで辺りに満ち、彼女は宇宙と一体となる。 そして次の瞬間妹紅は確かに見た、慧音の舞の背後にあの僧の姿を。 舞は終わり、幻想も消えた。 |
||
| ▲ | ||
| ※ ※ ※ |
||
| 脚注 (*)漢字「奄」、「利」、「縛」は実際には口偏が付く。つまり表記は[口奄]、[口利]、「口縛]が正しい。 |
||
|
|
||
| 幕間狂言 修羅 | ||
我が身を濡らすは血か涙か。誰も知ることのない犯罪。それでも。 罪は己が内に宿り、罰は心の中に顕在する。 |
||
※ |
||
| どうやってそいつを見つけ出したのか、憶えていない。いやその時ですら分かっていなかったのだろう。残るは切れ切れの記憶の断片、そして鮮やかな感情の欠片。それは怒り、憎しみ、そして恐怖。 奪ってやる。 奪ってやる。 あいつは姿を消してしまった。散々好き勝手な事をして、私から一番大切な物を奪っておきながら、結局私の手の届かないどこかへと消えてしまった。 だが、私は知った。あいつがこの世界に残していったものがあることを。 奪ってやる。 あいつが父から奪ったように。あいつが私から奪ったように。 たとえ、あいつ本人に手出しは出来ずとも。 奪ってやる。 私はあいつの残していった物をひたすら追った。それが「薬の壺」であることも、その行方を追ううちに知った事だった。私はあいつの影を、「薬の壺」を追い続けた。あいつが育ったという家の跡、貴族の屋敷、禁中、そして帝の使者……。 最早その時には、私は当初の目的を見失っていたのだろう。ただただ、その「薬の壺」を奪う事だけが頭の中を満たしていた。 そしてあの日、遂に私はあいつの影に追い付いたのだ。 奪ってやる。奪ってやる。 あいつの残したものを大事そうに抱えたそいつは、山の頂に居た。何故かそいつは山頂で火を焚き、壺を手にその前に佇んでいたのだ。その時そいつが何をしようとしていたのか、そいつが何者なのか、そんな事は私にはどうでも良かった。「薬の壺」を持っている、私にとってそれだけが意味を持っていた。 私はそいつに忍び寄る。どんな手段を取っても、絶対に「薬の壺」を手に入れるのだ。私の手には……。 奪ってやる。 奪ってやる。奪ってやる。奪ってやる。 奪ってやる。奪ってやる。奪ってやる。奪ってやる。奪ってやる。 ……残るは記憶の断片。真っ赤な記憶。血塗られた記憶。 そして……。 血と涙と、欠けた心を引き替えにして、遂に私は得た。それは……、蓬莱の薬。 目の前が赤く紅く染まる。それは血?それとも薬を焼くための火だったのか。 本当の私は、あの時死んだのだ。 ――一度手を出しゃ、大人になれぬ。 ――二度手を出しゃ、病苦も忘れる。 ――そして……。 |
||
| ※ ※ ※ |
||
第四ノ舞 今様 紺青鬼 へ続く |
||
| ▲ | ||
| こんなものを付けて見ました。当に弱気の至り。 もし何か思うところがございましたら……。 |
|
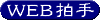 |