

| 秋毘売神 . | 豊かなる穣りの秋を司り給ふと云ふ 命満ちし大地からの恵みを約し 秋深まれば里も山も甘き香りに包まれたり 乙女心と秋の空は移ろい易きものなれど 喜びと富とをもたらすもの也 秋の女神は稲魂の乙女 瑞穂の国の母なる穀霊なり 昨日こそ 早苗とりしかいつのまに 稲葉そよぎて秋風のふく |
| 豊かさと穣りの象徴こと秋穣子嬢です。 姉の秋静葉嬢と共に秋を司る神様です。豊穣を司る神様ということで、ささやかながらも大地母神の小さな化身といった所でしょうか。 大地母神は様々な女神が職能ごとに分化する以前の姿を止めた古き神であり、一神教的な天空神にその役目を譲り渡すまでは最も賢く強く畏るべき神でした。その末端たる秋穣子嬢も本当は強い力を持っているのかも……。 ところで、彼女については公式テキストに、収穫前に呼ばないと云々とあります。これは、作物の実りを祈願する儀礼の多くが春と秋のセットになっていることを反映しているのでしょう。つまり、豊穣祈願の祭礼は本来、農作業前後の両方が揃っているべきで、冬の終わりから春にかけて行われる予祝儀礼やら田の神を迎える行事やらの豊作を願う祭りと、秋の穫り入れに対する感謝を表す収穫祭の双方があって完結するものだという訳です(古代の国家祭祀でいえば春の祈年祭と秋の新嘗祭)。もっとも、こうした儀礼は地域や時代によって千差万別であって、一概にこうと言えるものではありませんが。 一方で、豊穣の女神というと、デメテルとペルセポネの物語に代表されるようにどこかしら死の影を引きずっているようにも思えます。収穫とは作物を殺し、それを喰うことでもあり、豊かな実りは一方で死と表裏の関係にあるのですね。冬になると暗くなるという性質も、冬に訪れる穀霊の死と結びつけられないこともありません。こうしたことを考えれば、彼女が終焉や寂しさといった正反対の性格を持つ姉静葉と共にあるのも当然なのかもしれません。穀霊は死ぬことで収穫をもたらし、暗く厳しい冬を経て活力を得、春に再び甦るのです。 何れにせよ、豊穣を司る女神様とは、私たちの日々の暮らしを支える富(=作物=稲)をもたらしてくれる、大地の力の顕現なのでしょう。 さて、日本の神様の中には天照大神を筆頭に奇稲田姫・稲荷神など豊穣を司る大物は幾柱もおられるわけです。こうした大物は余りに畏れ多いので、大勢いらっしゃる小さき神々を見てみると、その中に秋毘売神という神様がおられます。今回はこの神様の名前を頂きました。大年神の系譜を記した部分に出てくるだけなので、余り詳しいことは分からないのですが、羽山戸神と大気都比売神との間に生まれた第六子、豊熟を守護する神様で、秋に稲の取り入れをするなどして働く女性を神格化したものであるそうです。なお、「秋毘売神」は『古事記』の表記で、『先代旧事本紀』では「秋比女神」と表記されています。系譜の大年神や大気都比売神が出てくる所に豊穣神としての性質が色濃くうかがえます。 秋穣子のまとう衣装は和風ではなく、中央ヨーロッパあたりの民族衣装風です。可愛らしいので、絵柄もそれに倣っています。良いですよね、チロル風。手に掲げているのは豊穣の角、あるいはコルヌコピアと呼ばれるもので、ギリシア神話に登場します。豊穣や収穫を象徴するものとして、絵画や彫刻などによく見ることができます。 詞書きの末尾の和歌は、『古今和歌集』巻四の秋の歌(172)です。詠み人知らずの歌ですが、新撰和歌集や古今和歌六帖にも採られていて、簡潔で平易に秋の田園風景を詠った歌としてよく知られています。苗代から早苗を取って田植えをしたのはつい昨日のことのようなのに、いつの間にか秋風が実った稲穂をそよそよと吹き渡っていく季節になってしまった、といった感じです。月日の経つのが早いことを詠っている訳ですが、そうした寂しさを別として秋の田圃を描写する“稲葉そよぎて〜”の部分も美しくて好きですね。 豊穣の力は大地の恵み、何時までも忘れないでいたいものです。 |
|
| ※ | |
| 余談です。 私は秋穣子を見るといつも思い出すのは玖保キリコの『シニカル・ヒステリー・アワー』に登場したシーちゃんです。ドイツ人とのハーフなんですよね。作中にドイツへ行く話があって、そこに民族衣装を着たカットがあったんです。名前は「しずか」で、むしろお姉さんに近いんですが。 |
|
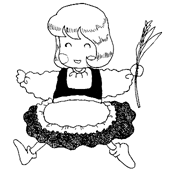 |
|
参考文献
高田衛監修『鳥山石燕 画図百鬼夜行』国書刊行会1992
フレーザー(永橋卓介訳)『金枝篇』岩波文庫1966-7
下中弥三郎編『神道大辞典』平凡社1937(1970複製2版)
小沢正夫校注・訳『古今和歌集』(『日本古典文学全集7』小学館1971)
小島憲之・新井栄蔵校注『古今和歌集』(『新日本古典文学大系5』岩波書店1989)
ほか