![]()
○平成18年4月
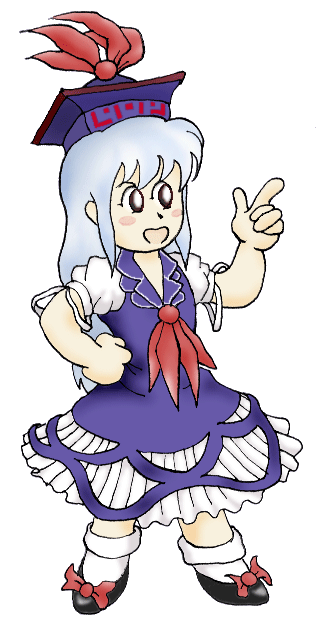 |
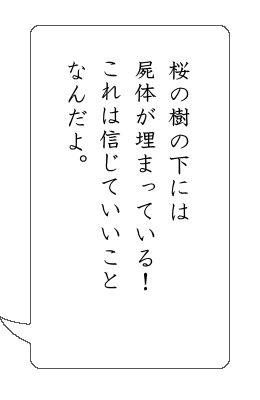 |
桜の樹の下には屍体が埋まっている!
これは信じていいことなんだよ。
梶井基次郎『桜の樹の下には』
 |
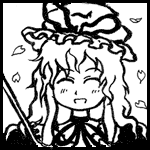 |
| 上白沢慧音 | 八雲紫 |
上白沢慧音 :“人の亡骸を抱いて咲き誇る桜”という巷説の元になったと思われる文
章だ。この文章のある作品については知らずとも、桜に関するこの話は
誰もが聞いた事があるのではないかな。
出典は「桜の樹の下には」、『檸檬』で知られる作家梶井基次郎の短編
だな。昭和3年(西暦1928年)に雑誌『詩と詩論』に発表された作品だ。
八雲紫 :「何故つて、櫻の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことぢ
やないか。俺はあの美しさが信じられないので、この二三日不安だつた。
しかしいま、やつとわかるときが来た。桜の樹の下には屍体が埋まつて
ゐる。これは信じていいことだ」
上白沢慧音 :!……相も変わらず神出鬼没の覗き魔振りだな。
八雲紫 :わたしは何処にでも居るし、何処にも居ないものなの。そして私は視る
モノでもあるわ。識るモノたる貴女になら解るのではなくて?
それにしても貴女、今この話をするのかしら。言わぬが花ということを
知らないの?
上白沢慧音 :??。
……ふふん、やっぱり彼女のことは気になるのか。
八雲紫 :―――――。
もし貴様がそのことに干渉するなら………、この前の様な程度では済ま
ないよ。
上白沢慧音 :ふふ、安心しろ。今回は桜に関する一般的な話しかしないつもりだ。
八雲紫 :ふーん。まあ、よく桜は死と結びつけて考えられるからねえ。
上白沢慧音 :梶井の文章は、美しいものや生というもの対してふと感じられる、漠然
とした不安を作品に昇華させたものなのだろう。だが、桜に関するこの
話がこれ程世間に膾炙したのには、それなりの背景があるのだろうな。
八雲紫 :そうねえ、確かに桜は美しいとされているけど、夜の桜や、あの散り様
に、不安を感じる者もあるかもね。そう言えば、文学などの桜にはそん
なものもあるわね。梶井の文章は屍体の表現が私には合わないんだけど、
坂口安吾の小説には私好みの桜の表現があったわ。
上白沢慧音 :坂口安吾………。ああ、「桜の森の満開の下」だな。
八雲紫 :そうそう、「桜の花の下から人間を取り去ると怖ろしい景色になります」
といやつよ。
上白沢慧音 :「鬼」が出てくるから好みなんじゃないのか?
八雲紫 :無粋ねえ。むしろ私の好みは「孤独」と「虚空」という言葉よ。
「桜の森の満開の下の秘密は誰にも分りません。あるいは「孤独」とい
うものであったかも知れません。………彼自らが孤独自体でありました。
彼は始めて四方を見廻しました。頭上に花がありました。その下には
ひっそり無限の虚空がみちていました。ひそひそと花が降ります。それ
だけのことです。外には何の秘密もないのでした。………あとに花びら
と、冷たい虚空がはりつめているばかりでした」
哀しくて、寂しくて、ぞくぞくしてくるでしょう?
上白沢慧音 :そうだな、山の伝説にも、桜の精に誘われて花びらに埋もれて死んだ男
の話があったはずだ。
民俗社会の俗信やら伝承にはあまり明確に桜と死とを結びつけるものは
無いのだがな。勿論伐ったら血が出たとか、死者を葬った跡に桜が育っ
たといった類の伝説には事欠かないが、これは聖なる樹木一般に伝えら
れる内容と大差はない。椿や柿の木など死や他界と結びつけられる樹木
は多かったのだ。こうした木には様々な禁忌が伝えられているのだが。
八雲紫 :でも、一般に流布したイメージでは、桜と死との結びつきはかなり強固
なものに見えるわよ。西行法師入滅を始めとして、墨染桜の伝説やら、
浅野内匠頭切腹の場面など、桜と死との有名な場面は極めて沢山想起で
きるのではないかしら?
上白沢慧音 :うーん。むしろそうした文芸作品で取り上げられたことで、イメージが
形成されたのではないか。それとやはり散り際こそが美しいという、桜
の花の性質が大きいのではないかな。
八雲紫 :桜の樹には人の気持ちを察するいう様な伝説もあったわね。小式部内侍
の逸話や墨染桜は有名だし、死ぬ前にもう一度桜が視たいと言った老僧
の願いに応えて、季節はずれの花を咲かせたという伝説も聞いたことが
あるわ。
:………あの木は、人の心が分かるどころか、人の精を吸い過ぎね。
上白沢慧音 :??。
八雲紫 :封印、死、桜と死………、何か忌まわしいものもあったような。
上白沢慧音 :………歪んだ武士道の解釈だろう。いや、愛国心かな。
兎に角、桜の美しい散り様が、潔く死ぬことに結びつけられたのだ。
八雲紫 :人間は愚かねえ。
上白沢慧音 :………ああ。桜が我が国固有だという国学者達の誤った思い込みも、こ
の様な解釈に拍車を掛けたのかもしれぬな。彼らは浅はかにもこうあっ
て欲しいと自ら望んだことだけを視ていたのだ。
八雲紫 :あなたは、国学者が嫌いなの?天狗の話の時もそんな様な事を言ってい
たようだけど。
上白沢慧音 :私が嫌いなのは、偏狭なナショナリズムだ。いやむしろ不寛容さと言う
べきかな。盲目的で独善的な排他性だよ。
八雲紫 :なるほどねえ。だから一神教とかも嫌いなのね。
(………あらあら、それにしても、共同体として社会を囲い込み、体制
的秩序を護り仁政を行う帝王の象徴たる白澤が言うことかしら?)
上白沢慧音 :まあ、話を桜に戻そう。
桜はバラ科サクラ属の一群の樹木を指す。東亜細亜に多く分布し、春に
は美しい花を咲かせる。古くから文芸や美術のモティーフとして取り上
げられている。本邦の国花とされてもいるな。
八雲紫 :山桜に里桜、大島桜、彼岸桜、染井吉野………。おびただしい品種があ
るわね。それにしても固有の文化の代表格、ねえ?
上白沢慧音 :万葉集の頃は、花と言えば梅の花のことだったのだが、平安時代の古今
和歌集の頃から花は桜を指す様になる。まあ、嗜好の変化があった訳だ
が、遣唐使廃止に始まる国風文化の隆盛と同期しているからな。桜の花
が、国風文化の一種の代表と捉えられたのではないかな。
八雲紫 :確かに、平安以降、桜に関する芸術作品は数え切れないわね。紋や色の
名前としても定着しているし、とても好まれた花であることは確かね。
そうね………、確か琵琶法師が平家物語を語るとき、それに先だって語
る曲の題名がまさに「桜」だったわね。陰陽道の冥界の神、泰山府君が
桜の花の命を延ばすという内容だったような(あら、こんな所でも桜は
冥界と関わってくるのね)。
:………そもそも何故あの花を「サクラ」と呼ぶんだったかしら。
上白沢慧音 :そういえば「サクラ」の語源には様々な説があったな。美しく花を咲か
せることから来たという説が多かったと思う。例えばサキムラガル(咲
簇)やサキウラ(咲麗)の約転というような説だな。
:『茅窓漫録(ぼうそうまんろく)』や『和訓栞(わくんのしおり)』で
は此花咲耶姫の「さくや」が転じたものと論じている。この女神は桜の
精とされているからだろう。華やかだが儚い命の象徴でもある訳だが。
八雲紫 :………天孫降臨の際、邇邇芸命は妻を娶った。彼は醜い姉石長比売を嫌
い、美しい妹神の木花咲耶毘売を選んだ。そして人間は桜が咲くが如き
栄華を得る代わりに不死性を失い、限りある人生を送ることになった。
貴女お得意の分野ではなくて?
上白沢慧音 :む、そこにも生と死とが現れてくるな。そう、岩の如き永遠の命を象徴
する石長姫は個体としての永続性を表す。一方で桜の花の精たる咲耶姫
はその花としての命は短い。だが、花が毎年春になると再び咲くように、
それは死と再生とを繰り返し、種として繁栄して行くことを表してもい
るのだ。そう、桜の花は本来、死と再生を表すものだったのだ。それが
何時の間にか死ばかりが強調される様になってしまったのかも知れぬな。
八雲紫 :永遠と、限りある生か。件の紅魔館のお守り役なら何と言うかしら。
上白沢慧音 :さあな。ともかく木花咲耶姫は火山の神であり、子安神でもあるのだな。
死と再生、破壊と創造の神なのだ。ま、これには天人の伝説が関わるこ
ともあり、単純ではないがな。
:一方で、農耕儀礼との関わりを指摘する説もある。「サクラ」の「さ」
は、“さおとめ”や“さなえ”と同様に穀霊を表す。そして「くら」は
“いわくら”や“たかみくら”と同じ、神の降臨する神坐の意味だとい
う。この説に拠ればこの名は本来桜に限って用いられた訳ではないこと
になる。実はこれは花見の風習とも関わっている。今では花見は物見遊
山、娯楽に過ぎないが、かつて民俗社会では、ある決まった期日に山な
どで花見の宴を行うという習慣があった。これは本来祭礼と同じく春に
農耕神を迎えるという意味を持っていたと考えられている。桜の花の付
き方で豊作を占うという習俗もこの名残なのだろう。
八雲紫 :ああ、潮干狩りが水辺での祓いに連なるのと同じ事なのね。でも、幻想
郷の連中は昔から単に楽しむ為に花見をやっているようだけど。
上白沢慧音 :それでいいんだよ。習俗や儀礼なんてものは決まった社会でのみ有効な
ものだ。何時でも何処でも同じ事の方が異常だよ。
八雲紫 :まあ、世の中変わってゆくものだしねえ。話は変わるけれど、外の世界
では桜も画一化しているようよ。どこもかしこも染井吉野。
上白沢慧音 :嫌な話題を振るなあ。
:江戸末期に染井の植木屋が売り出したものだろう。最初は吉野桜と言っ
ていたが、吉野とは全く関係はないようだ。江戸彼岸と大島桜の雑種と
する説が有力だな。花は一度に咲くし、葉に先立って開花するから、見
た目は確かに印象的なのだが………。
八雲紫 :やっぱり嫌だった?。私も桜には色んな種類があった方が楽しいけどね。
ただ、幻想郷にも染井吉野は増えてるわ。この百年くらいかしら。
上白沢慧音 :それは、一部の木が外の世界にとって幻想になったからだろう。あの種
類は成長は早いが寿命が短いのだ。長くても百年といったところか。
八雲紫 :ふーん、人間の寿命と同じ位なのね。だから思い入れが強いのかしら。
上白沢慧音 :さて、そんなこともあるかも知れんな。子供の頃若木だった桜が自らと
同じように生長し、老いてゆく。実は染井吉野の人気はこんな所にもあ
ったのかもしれないな。
八雲紫 :美しい花は生を謳歌し、一方でまた美しく散ることで死を暗示する。そ
して春の花は再生と豊饒の象徴でもある。桜と死とは分かち難く――。
西行寺幽々子:さくら〜、さくら〜、彌生の空は〜♪
八雲紫 :!!
上白沢慧音 :うわ、どこから(ここにプライバシーは無いのか)。
西行寺幽々子:あら〜、こんな所にいたのねえ。変わった組合せに思えるけど?
八雲紫 :ゆ、幽々子!。あなた何時から此処に?
西行寺幽々子:え〜。何か桜の話をしてたでしょ〜。
八雲紫 :え、その、箏曲「桜」は作曲者不明、古謡「咲いた桜」を明治時代にな
って文部省が改作、『箏曲第一編』(東京音楽学校)の中に発表したも
ので、一般には「さくらさくら」として知られているのよ〜(棒読み)。
西行寺幽々子:?。花見は美味しいっていう話でしょ。
慧音&紫 :???
西行寺幽々子:花見酒に花見団子、花見弁当、花見餅〜。
慧音&紫 :餅????
西行寺幽々子:桜だっておいしいわよ〜。
:花の綺麗な桜にはさくらんぼがならないのが残念だけどね〜。
八雲紫 :それにしても何か用でも?
西行寺幽々子:ん〜、桜と言えば〜。料理としては、桜鍋、桜煎、桜煮、桜蒸し、桜飯、
桜干、桜粥、桜蒟蒻、桜漬に桜味噌ってところかな?。お菓子なら桜餅、
葛桜、桜菓子、桜飴、桜おこしに桜羹よねえ。外にも桜海苔、桜烏賊、
桜海老、桜ウグイに桜鯛、桜鱒、桜酒なんてのもあったわ。
八雲紫 :………何というか、いや何も言う気が起きないわ。
西行寺幽々子:でね、右前方に長命寺の桜餅の気配がする〜。
上白沢慧音 :うう、しょうがないな。折角来たのだから食べてゆけばいい。その棚の
中にある(妹紅の為に用意しておいたのに………)。
西行寺幽々子:あれっ桜餅がこんな所に、偶然ねえ。山本屋かな?それとも三はし堂?
催促したみたいで悪いわね〜。
慧音&紫 :思いっきり催促していた様な………。
西行寺幽々子:二人とも考えすぎよ〜。桜の花は唯々美しいの。
:何で花見をするのか、何故皆桜の花が好きなのか。………美しいから、
それで充分じゃない。
上白沢慧音 :―――そうかも知れないな。無心に花を愛でる。これこそが本来の姿な
のかもしれない。
西行寺幽々子:ごちそうさまっ。じゃ、またね。
:さくら〜、さくら〜、彌生の空は〜♪
八雲紫 :それでは私も失礼するわ。気が向いたら白玉楼へ花見にいらっしゃい。
………結界は開いておくわ。
♪見渡す限り、霞みか雲か、匂いぞ出づる、いざや、いざや、見に行かん―――――――。
上白沢慧音 :……………弥生は陰暦三月のことなんだが。