![]()
○平成19年2月
 |
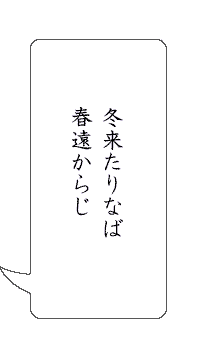 |
冬来たりなば、春遠からじ
If Winter comes, can Spring be far behind?
シェリー「西風の賦」(1920)より
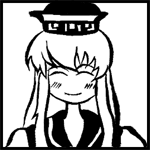 |
 |
| 上白澤慧音 | レティ・W |
| 上白澤慧音 | :If Winter comes, can spring be far behind? :冬来たりなば、春遠からじ………。 :冬の次の季節は春。どんなに苦しい時期があろうとも、いつかはそれを乗り越えることが出来る。困難は永遠ではない、その先には必ず希望があるのだ、というわけだな。 :そう、「夜、明けなんとして益々暗し」といった感じか? :………この詩、本当は冬がやって来る十月、晩秋のものなんだがな。 |
| レティ | :良くないことや辛いこと、厳しいことの喩えが冬っていうのは、ちょっと納得いかないわね。 |
| 上白澤慧音 | :ああ、定番の妖怪が出てきたな。 :最近は暖冬なのどうしているかと思っていたが……。 :そうは言っても仕方あるまい。人間、いやほとんどの生物にとって冬は死の季節なのだから。生命のあふれる春と比較されて負の意味づけがなされるのも必然だな。 :ただな、暗く厳しい冬があればこそ、その後に来る春の喜びも大きくなるとも言える。春の華やかさ、豊かさのイメージは冬があればこそなのだ。勿論、現実にも生命活動は、冬の空の下で春の準備が進められているのだろう。………冬だって無くてはならないものなのさ。 |
| レティ | :まあねえ。 :それにしてもこんな所で珍しいわね。妖怪退治?私は別に人間にそんなに興味はないし、此方からわざわざ何かをする気もないけどね〜。勝手に近づいた人間のことなんて、どうなろうとも知らないけどね。 :う〜ん、白澤の力を見てみたい気もするわねぇ。今の季節ならね〜。 |
| 上白澤慧音 | :冬にそなたとやり合いたくはないな……。そもそも、初めからそなたとは事を構えるつもりは無い。むしろ私は不用意な人間がこちらに迷い込んだりしたい為に見回っているに過ぎない。 :今は冬、そなたが活動するのは当然なのだからな。 |
| レティ | :ふーん、ちょっと残念な気がするけど………。 :冬だって素晴らしいのに。清らかな雪、透明感の増す空気。満天の星空。自然もそうでない物も、冬にこそ、その本質が露わになる。だからこそ冬景色は美しいのよ。 :人間って無粋よねぇ。雪で散々遊んだりする癖にねぇ。 |
| 上白澤慧音 | :(人間だけじゃないと思うが。) :寒さに弱い者も多いからな………。 |
| レティ | :あー、でも、最近は寝ている間の方が長い気がするわー。 |
| 上白澤慧音 | :ん?外の世界で失われた「厳しく寒い冬」がこっちにやってくるかと思っていたが。 :暖冬だとそなたも消えてしまうのか? |
| レティ | :ふふふ。それは無いの。ほら、遙か北の国に比べたら此処だって元々温度は高いのよ。要はそこに住む者達がどう感じるかということ。 :だからね、この幻想郷に四季がある限り、私は在り続けるわ。 :季節が巡るたびに、私は現れることができる。 |
| 上白澤慧音 | :なるほどな。 :自然の力というのは、本来人間ごときが何かした程度では関係ないということか。それはそうだな、人間が居なくなろうが、自然は残るのだからな。 |
| レティ | :そうそう……。 :そういえば、例の言葉、日本語の諺っぽいけど違うのよねー。 |
| 上白澤慧音 | :ああ。そなたなら知っているかもしれないな。ホワイトロックの名を持つ者よ。 :この言葉は英国の詩人パーシー・ビッシ・シュリーPercy Bysshe Shelley(1792-1822)の詩「西風の賦Ode to the West Wind」(1820)の最後の一節だ。日本でも昔から親しまれてきた句と言えよう。 :The trumpet of a prophecy! O, Wind, If Winter comes, can Spring be far behind? (予言の喇叭を吹き鳴らせ!おお、西風よ 冬来たりなば、春遠からじ) :この詩は「西風に寄せる歌」とか「西風に寄せて」とか訳が一定していないが、兎に角も27歳のシェリーがフィレンツェで書き上げたものとされている。10月のある激しい西風が吹く日没に、一気に完成させたと言われているな。 |
| レティ | :あれ、年齢が、……あ、そうか翌年になってから出版されたのだったわね。 |
| 上白澤慧音 | :さて、この詩の解釈についてだが……。 :はじめに西風が破壊的な暴君として描写される。この西風は激しい破壊者であり、厳しい自然であり、詩人の霊感の源でもある。西風は破壊者であると共に創造者であるとも捉えられているようだ。シェリーは西風と一体になろうとし、また西風によって鳴る竪琴になろうとする。それは彼の詩作の原理を表すものであり、彼の思想を表すものでもあるはずなのだ。 :さらには社会体制との関連もあるだろう。西風は革命と復興の象徴ともなるのだ。破壊の後の創造、魂と神性、霊感と言葉、生命の先触れといまだ目覚めぬ大地……。 :加えて詩の形式もおろそかには出来ない。全五連から構成されるが、それぞれは三韻句法の四つのまとまりと各連末尾の対句から出来ている。特に賛美歌などのような形式的呼びかけ(〜よ)で接続されており、宗教的な感覚が持ち込まれているようだ。これらの……。 |
| レティ | :まあ、解釈はどうでも良いじゃない?言葉や形式が美しいというので充分じゃないかしら? |
| 上白澤慧音 | :うーん、そんなものなのか? :ではシェリー本人について述べておこうか。彼はイングランド南部サセックスに生まれる。彼は少年の頃から理科教師ウォーカーの影響を受け、イラズマス・ダーウィン(有名なチャールズの祖父)の流れをくむ思想に興味を持っていたという。さらに実験や機械に興味を持ち、電気や天文学、エネルギーなどに興味を持っていたという。オックスフォードのコレッジに入学してからも、電気や化学、火薬の実験や降霊術の実験などを繰り返したという。今の感覚からみると、科学的な実験と幽霊の実験などが、同一人物の中で同居しているのは異様に思えるが、この時代なら特段変ではないな。 |
| レティ | :そして無神論のパンフレットを出版して放校処分を受けるのだったわね。 |
| 上白澤慧音 | :急進的で反体制的な思想に親近感を持っていたようだな。 :この後のことはどうもわたしには、な。 |
| レティ | :あら、そう。じゃあね、えーと、思いを寄せた従兄弟との結婚を反対されたので失望し、その後妹の学友ハリエットに同情して駆け落ちするのよねー。でも知人の社会主義思想家ウィリアム・ゴドウィンの娘メアリーが気に入ってしまい、メアリーを妻として、ハリエットを“霊の妹”として三人で暮らしたいとか言い出すのよ、大まじめで。結局ハリエットは投身自殺。ひどいわ〜。 :ああ、イタリアに行った後も、友人のエドワード・ウィリアムズの妻ジェーンに思いを寄せて、詩を詠んだりしてるわねー。 |
| 上白澤慧音 | :……………。詩人としては、能力のある人間だったのだがな。 |
| レティ | :そうね〜。『鎖を解かれたプロメテウス』とか良いわよね〜。 |
| 上白澤慧音 | :(それにしても、何時本なんて読んでいるのだろう?) :いずれにせよ、イギリス浪漫復興期の代表的な詩人であることは確かだ。ワーズワース、バイロン、キーツなどが同時期の詩人だな。特にバイロンとは親しい友人関係にあったようだ。 :代表作には『鎖を...』の他に『マッブ女王』、『アドネイス』など、勿論「西風の賦」も代表作と言えよう。 :そうそう、彼は人外との関わりもある。彼の二度目の妻、メアリー・シェリーはかの“フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス”の生みの親だ。この小説は、無聊を慰めるため、一人一人恐怖小説を書くという別荘での思いつきによって書かれたものだな。因みに、この時バイロンの主治医ポリドリの書いた「吸血鬼」は吸血鬼小説の始めとも言われている。 :余談になるが、日本語訳については、次のようなエピソードが伝えられている。この詩を巻頭に掲げた英国の作家ハッチンソンの小説"If Winter Comes"が訳出される際に、訳者の木村毅は「冬来なば」と訳したという(岩波の世界大衆文学全集)。ところが、これを映画化した作品が、大正14年に日本で公開されるに当たり、何の手違いか「冬来たりなば」になってしまったという。結局この誤用が流布した形となっている。5+7より7+7の方が語感が良かったからかもしれないな。 |
| レティ | :そして彼は海の嵐の中に消えた。そうでしょ。 |
| 上白澤慧音 | :ああ、彼はエイリエル号とともにスペツィアの沖合で海の藻屑となったの。墓石には彼の愛したシェイクスピアの『嵐Tempest』の一節が刻まれているわ。妖精エイリエルの歌う句がね。 :「骸は朽ちず海神の 力によりて豊かにも 奇しきものとなりにけり」 |
| レティ | :彼の心臓は不思議にも焼けず、今はメアリーと共に眠っている、だったわね。 |
| 上白澤慧音 | :彼が冬の先に、嵐の先に見ていたものはなんだったのだろう。 |
| レティ | :さあねえ、でも彼の詩はこうして残っている。詩人としては幸福なのではないかしら。 |
| 上白澤慧音 | :ふ、考えが前向きなのだな。 |
| レティ | :あなたが悲観的すぎるのよ。 |
| 上白澤慧音 | :そうなのか、な。 :それにしても、望まれずに毎年決まってやって来て、……寧ろ消えることを望まれる。自らの意志とは関係なく寒さと共に現れ、春の訪れと共に消える。それの繰り返しなのだろう。時には春を呼ぶために打ち払われることもあるのだろう? :それでも何故、そう楽観的でいられるのだ? |
| レティ | :そうねぇ、別に春眠も悪くないしね。 :私は大自然の理なのだもの。これは私の在り方なの。 :冬は死の季節、でもそれは新たな生へと連なる創造の季節。陰極まれば陽萌す。私自身はそれを見ることは出来ないけれど…、冬こそ欠くべからざる生命の源、豊饒の種。 :そう、それにね、私が消えると寂しく思ってくれるものもいるわ。だから………。 |
| 上白澤慧音 | :そうか。………少し、羨ましいな。 |
| レティ | :あら、なーんだ。すこし、なのね。 :―――――。 :季節は巡る、何時までも、まるで永劫に変わらないかの如く。 :でも、それは矢張り違う。今年の冬は今年だけのもの。貴方との出会いも、その他冬の間の様々な出来事も、二度とはない一度きりのもの。 :さあ、もう残り少ないけれど、貴方も今年限り、たった一度の冬を楽しんでね。 |