![]()
○平成19年6月
 |
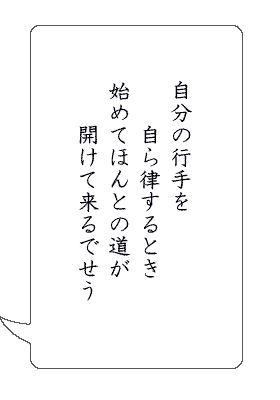 |
自分の行手を自ら律するとき
始めてほんとの道が開けて来るでせう
後藤慶二「過去とも将来とも付かぬ対話」
(『建築』第200号、大正5年7月)
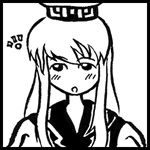 |
 |
| 上白沢慧音 | 八雲紫 |
| 上白沢慧音 | :自分で自分の進む道を切り開いてゆくことは、簡単なことではない。 :だが、もし何かを創造しようとするのなら、いや、より良い生を送ろうとする全ての者にとって、それは必要なことなのだろう。 |
| 八雲紫 | :人間は、弱いからねぇ。物理的にも、精神的にも……。 :それにしても、今回のテーマで、呼ばれたのが何故私なのかしら? :技術に関わることならば、私より適当な種族がいるでしょうに。あー、眠いわ。 |
| 上白沢慧音 | :……いや、別に呼んでないぞ。勝手に出てきて、勝手にしゃべってるじゃないか。 :それに今回のテーマは、技術にとどまらない。むしろ哲学的な命題だ。 |
| 八雲紫 | :あら、そうかしら? :でも、今回の人物は一般的には知られてないわよねぇ。これまでと方針を変えるの? |
| 上白沢慧音 | :決してそういう訳ではないのだが。まあ、歴史上の優れた人物で、余り知られていない人物の紹介もしてみたいという思いはあるがな。 :でも、特定の分野ではかなり有名人だぞ。 |
| 八雲紫 | :……こんなところで紹介しても、たかが知れてるけどね。 :兎に角、此処を見ている人の中には、そんな特定の分野の人など殆どいないのだから、まずは人物から紹介しなさいよ。 |
| 上白沢慧音 | :そうだな。今回の言葉は「自分の行手を自ら律するとき始めてほんとの道が開けて来るでしょう」。これは建築家の後藤慶二(1883-1919)の言葉だ。 :後藤慶二は日本近代建築史で欠かすことのできない重要な建築家だな。代表作は旧豊多摩監獄(中野刑務所)だ。残念ながら、刑務所の移転と共に解体されて、その大部分は現存していない。僅かに中野区平和の森公園内に、煉瓦造の表門のみ現存している。 |
| 八雲紫 | :まあ、まずはそんな所かしら。 :作品数は少ないのに、そんなに重要な人物とされるのは何故なのかしら? |
| 上白沢慧音 | :そうだな。作品が少ないのは、彼が僅か37歳の若さで亡くなってしまったからなんだ。もし、彼が長生きをしていたら、日本の建築史は全く変わっていたとも評されている。 :デザインだけではない、彼は構造技術にも造詣が深かった。つまり、一流のデザイナーであり、かつ一流の構造学者でもあったのだ。 |
| 八雲紫 | :そうね。それに彼は始めて近代的な「自我」を追求した人でもあったわ。 :それまでもデザインが達者な人なら居たけれど、それはあくまで西洋からもたらされた規範的なデザインを駆使しているだけ。本当の意味で自ら創造したとは言えない面があるわ。 |
| 上白沢慧音 | :……知っているなら聞くなよな。 :その通り。それから彼は意匠と構造という、いわば二元論に対して、真摯に取り組んだのだ。ただ芸術的な美を追究するのでも、単純に機能主義に依拠するのでもない。機能や構造を律する、高い規範として自我を位置付けたのだ。そこで如何にして自我を追求してゆくかも課題となったのだ。 :今回の言葉はそうした文脈で語られたものだ。外部の法則や規範に従っているのでは十分ではなく、自らの内に法則を見出すべきだと、そう彼は主張したのだ。彼はこう述べる。 :「欠陥は法則を他から求めて自己を律しようとするところから起こるので、之を超脱しやうとならば自己の内に法則を見い出さなければなりません」 :これらの文章は、本来はあくまで建築論だが、あらゆる創作活動、いや人間の生き方にまで展開が可能なものだろう。 |
| 八雲紫 | :そして彼の思想は、すぐ後の世代の、近代建築運動へと連なって行ったのね。 :それが大正9年(1920年)の分離派建築会の旗揚げ。でも、こうした新しい世代の建築家達の、華やかで自信に満ちた態度に比べると、その足場を築いたとも言える彼の姿勢は、余りに謙虚で、余りに控えめね。 :後の「進歩的建築家」は、その多くがエリートで、先覚者意識が強い。それに自分が世の改革の先頭にあって、愚民を啓蒙してくのだという類の、指導者意識が余りに強いように思えるわ。つまり、「自分が大衆を導いてやる」というような特権意識ね。 :ある時期までは、歴史主義的なデザイナーが主流で、自分たちが少数派だったという面があるにせよ、余りに自意識が強く、独善的。謂わば被害者意識の裏返し。 :……きっと彼等は、自分たちが間違っているかも知れない、なんてことは、考えもしなかったのではないかしら。 |
| 上白沢慧音 | :随分と手厳しいな。まあ、基本的には同意せざるを得ないがな。 :後藤は自分の論を展開するときも、極めて慎重だった。彼の考え方は、彼の先輩達の持っていた、国家的意識や忠誠心とは違い、そして後の世代の先覚者意識とも違う。それは静かだが、一番共感できる。 :彼は独断を嫌ったのだろう。それは次の様な言葉からもうかがうことができよう。 :「無数の法則はすべての点に於て一致するものではないのですから、屡々互いに相互矛盾撞着することを免れません(中略)第二の解決は、只一つの法則を残して他は皆捨てゝしまふことです、これは妥協を脱して如何にも徹底的に見えます。然しそれはほんとの徹底ではない、単に問題を回避したに止まります、総てを一つの力の下に統一したのでなくして、多くの法則は抹殺して独断的に一個の法則に即しただけの話です、何でも単純に解決が出来るかはりにこの結論は盲目的で偏狭なことを免れますまい」 |
| 八雲紫 | :ああ、今の世の中には独断と自己欺瞞、皮相な単純化が溢れているわ。 :彼の理論と警告は今にこそ必要とされているのではないかしら。 |
| 上白沢慧音 | :全くだ。 :彼の夭折が惜しまれてならない。 :彼は自分が天人性だと書いている。何事にも恬淡で諦めがよい、と。そんな人物が、豊かな才能を持って人間界に生まれたことこそが奇跡のようなものだったのかもしれない。……でも、彼は基本的に人間というものを信じていたのだと思う。そして未来も信じていたのだろう。愛すべき人間達は、時に迷い、時に立ち止まっても、いつか輝かしい未来へとたどり着けるのだと。例え自分でそれを目にすることが叶わずとも。 :そんな彼も、死を目前にした時には、幼い息子や妻のことを非常に心に懸けていたようだ。そればかりではない、きっとやりたいこと、究めたいことがまだまだ沢山あったろう……。 :画家になりたかった一人の人間は、長く生きることを許されなかった。それでもその思想は、思いは彼の後に続いた多くの者達に受け継がれ、生き続けているだろう。いや、そうだと信じていたい。 |
| 八雲紫 | :儚き人間は、限られた僅かな時間を懸命に走る。 :……月並みな言葉だけど、人生の価値は長さではないわ。 :だから、彼は立派に生き、価値ある人生を送ったのよ。……そう考えることが、今は亡き偉大なる先人への敬意。 |
| 上白沢慧音 | :……ああ、そうだな。 :そういえば、彼は歴史についても価値ある文章を残している。まあ、機会があればそちらも紹介したいな。 :最後に建築史家の後藤慶二評を紹介しておこう。日本近代建築史の泰斗、村松貞次郎はこう記している。 :「豊かな芸術的感性と緻密な構造学者としての頭脳とが彼の一身に融合していたのである。日本の近代建築史上に貴重な存在で、彼の前にも後にもそれに匹敵する建築家・建築学者を、私はついに発見することができないのである」 |
| 八雲紫 | :じゃあ、私は彼の先輩で著名な建築家、岡田信一郎の追悼の時の後藤評を引用しようかしら。あ、岡田は明治生命館や歌舞伎座を設計した人よ。 :「趣味豊潤なる美術家として、精緻周到なる構造学者として、青年建築家中の白眉と目されし人」 |
| 上白沢慧音 | :これを機に、少しでも後藤慶二のことを知る人が増えることを願おう。 |
| 八雲紫 | :そうね……。 :そうそう、あなた知ってるかしら?後藤慶二のお父さん。 |
| 上白沢慧音 | :ん?後藤牧太(1853-1930)だろう。福沢諭吉の弟子で物理学者。東京高等師範学校(後の筑波大学)教授。物理学の教科書を執筆したりもしているな。 :うん、つまり学者の一家だというわけだ。 |
| 八雲紫 | :やっぱり知ってた? :じゃあ、千里眼事件と関わったことも?有名な御船千鶴子の公開実験、後藤牧太氏も参加してたの。実験についての記事を雑誌『東洋学芸雑誌』に掲載しているわ。 :確か、内容は実験条件が不完全とか、そんな感じだったと思うわ。 |
| 上白沢慧音 | :むー。それにしても、何と言うか、そういった怪しげなこととのつながり、良く知ってるよなあ。どっから嗅ぎつけてくるんだか。 :………なんだか、変な豆知識を出してくるせいで、雰囲気が壊された気がするな。 |
| 八雲紫 | :そんなことないわよ。 :こういう胡散臭い話の方が、食いつきが良いんだって。 |
| 上白沢慧音 | :胡散臭い……って、自分で言うなよな……。 |
| 八雲紫 | :………。じゃ、おやすみなさい。 |
| 上白沢慧音 | :って、こら。ここで寝るなー。 |
参考文献
・中村鎮『後藤慶二氏遺稿』後藤芳香1925
・村松貞次郎『日本近代建築の歴史』日本放送出版協会1977
・稲垣栄三『日本の近代主義建築[その成立過程]』鹿島出版会1979
・日本建築学会編『近代日本建築学発達史』丸善1972
・近江栄・堀勇良『日本の建築[明治大正昭和]10』三省堂1981
・間組『旧豊多摩監獄解体調査報告書』間組1984 ほか