![]()
○平成19年7月
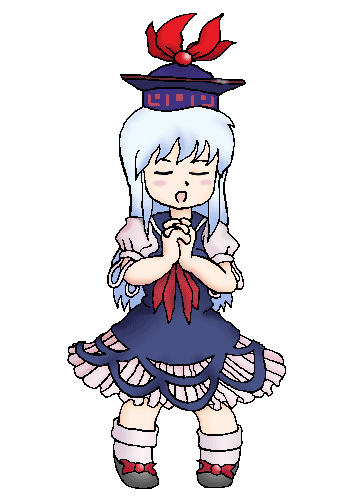 |
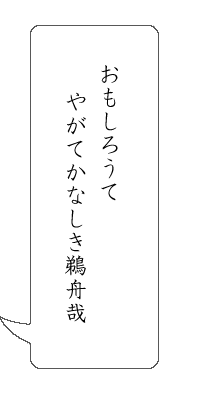 |
おもしろうて やがて悲しき鵜舟哉
松尾芭蕉『曠野』
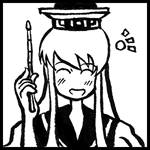 |
 |
| 上白沢慧音 | ルナチャイルド |
| 上白沢慧音 | :さて、今回の課題はこの句だ。松尾芭蕉の句だな。夏の句としても有名だろう。 |
| サニー | :ねーねー、そんなことよりもさー。 :なんで生徒役が私達なのかな〜。 |
| ルナ | :そーよねー。人間相手の学校のはずなのにねー。 |
| チルノ | :ZZZ……。 |
| 大妖精 | :って、チルノちゃん!最初っから居眠りは流石にまずいって、ねぇ。 |
| サニー | :大体さー。ここの管理人って、三月精は単行本しか読んでないじゃん。 |
| スター | :ちっちっちっ。人間の里を舞台にしたら、オリジナルな子供達を出さざる得なくなるでしょ。 :つまり〜、ここの管理人には、オリジナルキャラを描写する能力も勇気も無いわけ。 |
| 上白沢慧音 | :―――――。 |
| ルナ | :なるほどねー。 |
| サニー | :あー、だからおバカ嫌いとか言ってる癖に、妖精が出てきたのね。 |
| 上白沢慧音 | :………(怒)、いい加減にそういうメタな話は止めなさい。 |
| スター | :わー、頭突きよ頭突き! |
| サニー | :きゃー。チョークの弾幕よ。 |
| チルノ | :むにゃ?強敵? |
| ルナ | :角よ角!! |
| 上白沢慧音 | :い・い・か・げ・ん・に・しなさい! :……………。 :日出づる国の天子お見舞いするぞ! |
| サニー | :―――――。妖精は勉強なんてしないのよ! |
| 上白沢慧音 | :………そう堂々と宣言されてもなあ。 :今回は嫌でも付き合って貰うぞ。 |
| ルナ | :……ま、偶には変わったことをしてみるのも、面白いかもね。 |
| 上白沢慧音 | :はぁ〜。 :では本題に戻る。これは元禄二年(西暦1689年)に刊行された『曠野』を始め幾つかの句集に収められている。芭蕉の代表作の一つと言えよう。 :この句は元禄元年に、彼が長良川で鵜飼い見物をした際、吟ぜられたようだ。『笈日記』には「稲葉山の木かげに関をまうけ盃をあげて」とある。 :鵜飼いは、月の無い夜に篝火を焚いて川を下りながら行う夏の風物詩だ。芭蕉はそれを岸から見物していたのだな。 :この句についての詳しい解説は後でするとして、まずは作者の松尾芭蕉について、解説してみようか―――。 |
| サニー | :その前に、げんろくってなーに? |
| スター | :ぎふってなーに?ながらがわって? |
| 上白沢慧音 | :あう。 :元禄はある年代を表すための年号、今から大体320年程前だ。それから、岐阜も長良川も外の世界の地名だよ。 |
| チルノ | :ふーん。 |
| 上白沢慧音 | :(これは先が思いやられるな……) :さすがに、松尾芭蕉ぐらいは知っているよな? |
| スター | :大相撲夏場所? |
| ルナ | :違うわよ。近世になって輸入された外来植物で、美人に化けるのよ。鳥山石燕も取り上げてるわ。芭蕉の精は化けるもの、謡曲にもなってるし有名よ。 :「夜深更に此の中を独行する時は必ず蕉妖に逢ふ。その形は皆婦人なり。敢えて人を害あることを聞かずと云ふ」ってね。 |
| サニー | :へぇ〜。ルナってすごーい。 |
| 上白沢慧音 | :……………。う、うーん。 :いや………。まあ、間違っている訳ではないのだが。それは芭蕉違いだな。 :今話題にしているのは、植物とか妖怪の芭蕉じゃなくて、人間の松尾芭蕉だよ。 |
| ルナ | :え?あれ?? |
| 上白沢慧音 | :松尾芭蕉は正保元年(西暦1644年)に伊賀上野に生まれた。下級武士の家柄で、隠密という伝説はこの出自によるものだろうな。やがて江戸に出た彼は俳諧を芸術的に高めてゆくことになる。 :江戸深川の草庵に住み、その庭に芭蕉を植えて芭蕉庵と称した。自分の号もそれに因んだものと言われている。旅を愛し、奥の紀行文を残している。中でも「奥の細道」が有名だろう。 :結局彼は元禄七年(西暦1694年)、旅の途中の大阪で病を得て没するのだ。木曽義仲に共感を持っていた彼の墓は近江の義仲寺にある。最後の句も有名で―――。 |
| スター | :ハイカイ? :俳句じゃあないの? |
| 上白沢慧音 | :うん。俳句という語は意外と新しいものだ。そもそも俳諧とは、機知や滑稽を主とする連歌のことを示し、これは室町時代がからのものだ。これを文芸の一分野として確立したのが芭蕉と言っていいだろう。 :中でも、俳諧の最初の一句は発句と呼ばれ、完結した一つの文学形式として独立する方向性を持っていた。芭蕉や与謝蕪村、小林一茶などの良く知られた句はこれに当たる。 :そして明治時代になって、正岡子規がこの文学形式を俳諧の発句、縮めて「俳句」と名付け、以後これが定着したのだよ。 |
| チルノ | :全然分かんないよー。 |
| 上白沢慧音 | :………そうだな、もう文学史の話は止めよう。 :それから、作風や理念についての話も又の機会と言うことにしよう。 |
| ルナ | :じゃ、句について説明して。 |
| 上白沢慧音 | :ふむ。 :「おもしろうて やがて悲しき鵜舟哉」 :鵜舟とは鵜飼いで使用する鵜飼舟のことだが、ここでは鵜飼いそのものを指す。「やがて」というのは、“すぐに”という意味ではなくて、“しばらくして”、“そのうちに”の意味になる。 :闇夜に篝火を焚いて行う鵜飼いはなかなか興味深いが、やがては鵜舟も通り過ぎ、篝火も消える。賑わいの後であればこそ、また哀愁深い。という訳だな。 |
| サニー | :トリの虐待じゃなーい?私達には関係ないけどー。 |
| スター | :関係ないけどー。 |
| 上白沢慧音 | :これは強く無常観を感じさせる句とも言える。万物流転のこの世界、華やかなものも、快楽も所詮は一時的なもの、永続的なものなどは無いのだ。それを考えれば、ある出来事が面白ければ面白い程、それが終わった後の哀しさ寂しさは大きくなるものだ。 :まさに、歓楽極まって哀愁深しの感があるな。 |
| ルナ | :迷ひの多き浮雲も、実相の風荒く吹いて、千里の外も雲晴れて、真如の月や出でぬらん |
| 上白沢慧音 | :ほう。 :それは謡曲の「鵜飼い」だな。芭蕉のこの句は、おそらくこの謡曲を踏まえた上で吟ぜられたのだろう。この「鵜飼」には“面白さ”と“悲しさ”が対照されている部分が二箇所有る。 :「鵜追ふ事の面白さに、殺生をするはかなさよ………鵜舟に燈す篝火の、消えて闇こそ悲しけれ」、「罪も報いも、後の世も忘れ果てて面白や………不思議やな篝火の、消えても影の暗くなるは、思ひ出でたり月になりぬる悲しさよ」 :この謡曲は、殺生の罪によって地獄で苦しむ鵜飼いを生業とした老人が、法華経の功徳によって救われるという内容のものだ。 :表向きは法華経の功徳を扱うものだが、むしろ殺生を行わずば生きていけない庶民の苦悩と、罪なことと認識しながらも鵜飼いを面白いと感じてしまう人の業とが表現された作品と言えよう。 |
| サニー | :くらーい |
| スター | :くらーい |
| チルノ | :??? |
| 大妖精 | :うるうる……。 |
| 上白沢慧音 | :まあ、そんな背景は兎も角、この少ない言葉の中に籠められた、華やかな鵜飼いの情景と、それ後に訪れる哀愁との対比を鑑賞して貰いたいな。 |
| 大妖精 | :はい! |
| スター | :えー。未来のことなんて、考えたことないしなー。 |
| サニー | :うーん、先のことって、次の悪戯をする時までしか考えたことないや。 |
| チルノ | :あー、明日急に寒くなったりしないのかなー。 |
| 上白沢慧音 | :はぁ。 :妖精は死を意識せず、今を生きる、か。自然現象そのもののそなた達には、死ぬべき生物の気持ちを理解するのは難しいかも知れないな。 :そもそも、強烈な快楽も、その空しさも、そなた達には無縁のものかも知れぬ。否、逆に無縁でいられるからこそ無邪気な妖精でいられるのか―――。 |
| ルナ | :私は、何となく分かる気がするわ。 |
| 上白沢慧音 | :ん?そなたは月の、………そうか、なるほどな。 :まあ、こういうものを読んで、人間の考え方を知ることも悪くはないだろう? |
| サニー | :それって、悪戯の役に立つかしら! :いやいや、それより逃げる時の役に立って欲しいわ。最近げんそーきょうえんぎとか言うもののせいで、妖精を捕まえようとしたり、仕返ししたりする人間が増えたわ。まったくも〜。 |
| 上白沢慧音 | :(いつの日か、彼女たちがこの句を理解する時が来るのだろうか。) :(もし来るとしたら、それは彼女たちにとってどういう意味を持つのだろう?それは良いことなのだろうか、それとも悪いことなのだろうか?) |
| 妖精達 | :ねーねー。続き続きぃー。 |
| 上白沢慧音 | :ああ、では続けよう―――。 |
| いくら話をした所で、妖精達が果たしてそこから何かを得てくれるのか、それは分からない。 明日になればほとんどのことを忘れてしまうのかも知れない。 それでも、こんな授業も悪くないと、慧音は思った。 |
参考文献
・大谷篤蔵/中村俊定校注『芭蕉句集』(『岩波古典文学大系45』)岩波書店1962
・野上豊一郎編『謡曲全集 五』中央公論社1971