![]()
○平成19年9月
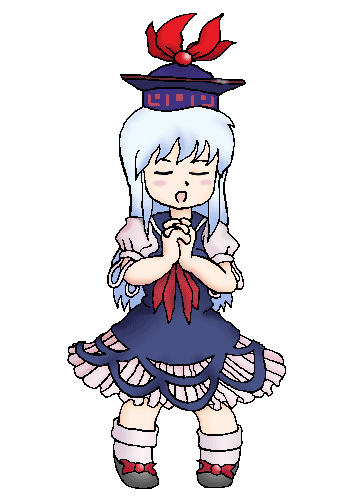 |
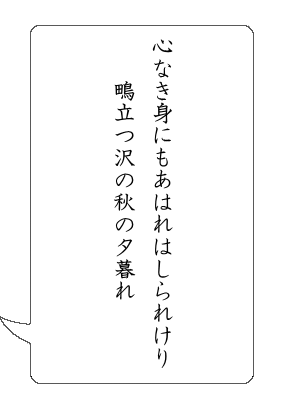 |
心なき身にもあはれはしられけり 鴫立つ沢の秋の夕暮れ
西行法師『新古今和歌集』
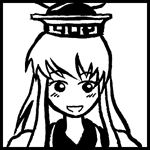 |
 |
| 上白沢慧音 | 西行寺幽々子 |
| 上白沢慧音 | :高い空、虫の声、今年も秋がやって来た……。 :さて、今月は秋の和歌を紹介したいと思う。秋を詠んだ歌は数多いが、今回は西行法師作のこの歌を取り上げる事としよう。 :「心なき身にもあはれは知られけり 鴫立つ沢の秋の夕暮れ」 :これは『新古今和歌集』に採られた有名な歌だ。巻四、秋上にあるな。 :元々は西行の歌集「御裳濯川歌合」に収められていた歌だ。そして――。 |
| 西行寺幽々子 | :秋は〜、食欲の秋〜。 :林間に酒を煖めて紅葉を焼き…………。 |
| 上白沢慧音 | :………。 :古来「三夕の歌」として親しまれてきたものだ。秋の歌としては抜群の知名度を誇る歌と言えよう。 |
| 西行寺幽々子 | :あれ、完全無視ですか? |
| 上白沢慧音 | :………西行の歌ということで、来て貰ったのだが、間違いだったな。 |
| 西行寺幽々子 | :えー。 |
| 上白沢慧音 | :この歌での「心なき身」というのは、出家した西行自身を表す。 :寂しさや悲しみ、愛憎悲喜の心をすっかり捨てたはずの身、ということだ。 :「鴫立つ沢」は鴫の飛び立つ水辺のことで、特定の地名ではない。 |
| 西行寺幽々子 | :実際には西行伝説を伴う「鴫立沢」は存在するのよね。 |
| 上白沢慧音 | :ん? そう。 :相模(神奈川県)大磯の伝承だな。この歌を詠んだ地とされている訳だが、これはずっと後になって、小田原の崇雪という人が尊敬する西行の記念のために選び、鴫立沢の標石を立てたものだ。その後は俳諧道場鴫立庵として今日まで続いている。 |
| 西行寺幽々子 | :西行返しの松の類の伝説もあったわね〜。 :『千載集』にこの歌が採られなかった事を知った西行が、その場で引き返したのよ〜。 |
| 上白沢慧音 | :話を元に戻すと、この歌の内容は、“寂しさ悲しみなど俗世の心を全て捨てて出家した我が身にも、秋のしみじみとした趣は自ずから感じられる。鴫の飛び立つ沢の秋の夕暮れよ”、と言った所か。 |
| 西行寺幽々子 | :こんな風景は、外の世界ではもう失われてしまったのかしら……? |
| 上白沢慧音 | :………さあな。 :兎も角、俗世を離れた西行の心にも、自然と秋の儚い美しさ哀れさが感じられたのだ。それ程この秋の景色が印象的だったのだろうな。 |
| 西行寺幽々子 | :そ〜ね〜。 :このリズムと「秋の夕暮れ」の終わり方が良いのよね〜。 |
| 上白沢慧音 | :そう、この三句切れで「秋の夕暮れ」の体言止めで終わる三つの歌が“三夕の歌”なのだ。 :西行の歌に加え、寂蓮法師の「さびしさはその色としもなかりけり まき立つ山の秋の夕暮れ」、そして藤沢定家の「見渡せば花ももみぢもなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮れ」を合わせて三夕という訳だな。 :三夕の歌は何れも『新古今和歌集』巻四、秋上に収められている。 :寂蓮の歌は「寂蓮法師集」、あるいは「左大臣家十題百首」に題しらずとして載っているものだ。 :歌の内容は、“自分の心の寂しさは、どこがどうという事も無いものである。常緑の真木が茂る山の秋の夕暮れの寂しさよ”、と言うようなものだろう。 |
| 西行寺幽々子 | :直訳調ね〜。 :山の秋の夕暮れ、その寂寥は何とも言いようがない、って言えばよいのよ〜。 |
| 上白沢慧音 | :……わざと直訳調なんだよ。 :ここは鑑賞ではなく、解説の場だからな。 :ともあれ、寂蓮法師(?-建仁2年(1202))は、俗名を藤原定長と言い、歌人の藤原俊成の甥でその養子となった。従五位上中務少輔に至る。しかし、俊成に男子が産まれたために出家したという人物だ。当然定家や慈円と言った文化人との交流も深かった。新古今集の撰者でもある。 |
| 西行寺幽々子 | :百人一首にも選ばれているわね〜。 |
| 上白沢慧音 | :ああ、そうだな。 :藤原定家(応保2年(1162)-仁治2年(1241))はわざわざ説明するまでもないだろう。 :藤原俊成の三男、新古今集の中心的歌人だな。 |
| 西行寺幽々子 | :豆知識よ〜。 :彼は名前を光季、季光、定家と変えてるの〜。さらに天福元年(1233)には出家して明静という法名を得てるわ〜。他にも京極中納言とも称したりしてるのよ〜。 |
| 上白沢慧音 | :え〜と……。 :この定家の歌「見渡せば花ももみぢもなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮れ」は、「拾遺愚草」あるいは「二見浦百首」によるとされる。文治2年(1186)の歌だという。これには「西行法師、すゝめて百首歌よませ侍りけるに」という詞書きが付いている。 :意味は大体、“遠くから広く見渡すと、花が咲いているわけでも、紅葉が美しいというのでもない。ただ海辺の海人のわびしげな家があるだけの秋の夕暮れだが、それが面白くまた物哀れである、と言う感じだろうな。 |
| 西行寺幽々子 | :明石の巻ね〜。 |
| 上白沢慧音 | :?。ああ。 :これは『源氏物語』の明石巻に「中々春秋の花紅葉の盛なるよりも唯そこはかとなう茂れるかげどもなまめかしきに」を踏まえているのだろうな。 |
| 西行寺幽々子 | :「秋の夕暮れ」で終わる歌は、三夕の歌の他にもあるわよ〜。 |
| 上白沢慧音 | :そもそも“秋の夕暮れ”ということ自体が、新古今集の頃に好まれた歌題であったのだ。それは勅撰集では『後拾遺集』以降に現れる特徴だが、新古今集に至って急増する。「六百番歌合」には“秋夕”の題があり、歌題として定着していた事が分かる。 :「秋の夕暮れ」で終わる歌としては、百人一首に採られている作品が有名だろう。それらは現代でも良く知られている歌と言えるだろうな。 :まずは三夕の歌の寂蓮法師による、「むらさめの露もまだひぬ真木の葉に 霧たちのぼる秋の夕暮れ」だな。 |
| 西行寺幽々子 | :あー。一字決まりね〜。 |
| 上白沢慧音 | :それから良暹法師の「さびしさに宿を立ちいでてながむれば いずこもおなじ秋の夕暮れ」だな。 :この歌は『後拾遺集』から採られているが、三夕の歌の形成にこの歌が大きく関わるという意見もあり、また三夕の歌にこの歌が入る異説もある。 |
| 西行寺幽々子 | :何にせよ、親しみやすい良い歌よね〜。 |
| 上白沢慧音 | :そうだな。 :だが、三夕の歌の起源はよく分からないらしい。大まかに室町期以降と考えられているようだな。 :例えば、室町時代成立の謡曲「西行塚」に「鴫立つ…」の歌について「三夕の随一」との表現があるし、又「和歌伊勢海」に「三夕和歌」と見える事から、天文年間(1532-55)には既にあったらしい。 :ちなみに、江戸時代の随筆『槐記』(享保14年(1729))には「後陽成院の御時(※戦国時代)より始まれり」とあり、山岡浚明(まつあき)編著の『類聚名物考』(1780頃まで)の和歌部には「長嘯子(※木下勝俊)より始まる」とある。なお木下長嘯子は江戸時代初期の歌人としても知られるが、豊臣秀吉の妻北政所の甥で一時は小浜城主だった人物だ。 |
| 西行寺幽々子 | :ど〜でも良いことよね〜。 |
| 上白沢慧音 | :ふふ。 :まあ、こんなことよりも大切なのは、これらの歌の内容が、時代を超えて我々の心に響いたということだろう。 :秋の夕暮れというものは、何時どんなときでも心に沁みる風景なのだな。それは時が移り人が代を重ねても変わらなかったのだ。 :だから今でも我々はこの歌に共感を覚える事が出来る。 |
| 西行寺幽々子 | :うんうん。 :「菜もなき膳にあはれは知られけり 鴫焼茄子の秋の夕暮れ」 :やっぱり、食欲の秋よね〜。これはきっと時代を超えた真実なのよ〜。 |
| 上白沢慧音 | :………それは唐衣橘洲の狂歌だよ。 |
参考文献
・久松潜一/山崎敏夫/後藤重郎校注『新古今和歌集』(『日本古典文学大系 25』岩波書店1958)