![]()
○平成19年10月
 |
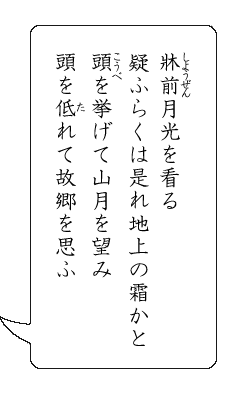 |
牀前 月光を看る
疑ふらくは是れ 地上の霜かと
頭を挙げて 山月を望み
頭を低れて 故郷を思ふ
李白「静夜思」
 |
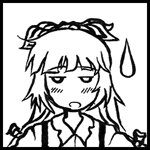 |
| 上白沢慧音 | 藤原妹紅 |
| 上白沢慧音 | :ああ、月の光が――。 :疑ふらくは是れ地上の霜かと……、か。 |
| 藤原妹紅 | :…………やあ。 |
| 上白沢慧音 | :妹紅か……。 :こんばんは。 :こんな時間にどうした? :―――――ああ、そうか。……いつもすまないな。 |
| 藤原妹紅 | :否、大したことじゃないさ。 |
| 上白沢慧音 | :本当は私が行くべきなのだが………。こんな夜には私が里を空けてしまうと色々と、な。 |
| 藤原妹紅 | :解っているさ、気にするな。 :何、偶には感謝されたり世間話を聞いたりするのも悪くない。 |
| 上白沢慧音 | :そう言って貰えると有難い。 |
| 藤原妹紅 | :それに………。 :……………もう慧音の悲しむ顔は見たくないから。 |
| 上白沢慧音 | :ん? 何か言ったか? |
| 藤原妹紅 | :いや……。 :それより、先程の詩は李白のものだったか。 |
| 上白沢慧音 | :ああ。あれは「静夜思」の一部。静かなる夜の思いという題を持つ李白の詩だ。 |
| 藤原妹紅 | :確か月明かりの中で故郷を思う詩だったよね。 |
| 上白沢慧音 | :そう。 :牀前看月光(牀前月光を看る) :疑是地上霜(疑ふらくは是れ地上の霜かと) :擧頭望山月(頭を挙げて山月を望み) :低頭思故郷(頭を低(た)れて故郷を思う) |
| 藤原妹紅 | :故郷を思う、か。 |
| 上白沢慧音 | :冴え渡る月の光の中に浮かび上がる人の哀しみ。 :李白の詩の中でも特に優れ、古来から愛唱されているものだ。 :故郷を想ってうたう、眠ろうとしても眠れぬ旅人の思い。故郷を遙かに離れたその身には輝くばかりの月の光が降り注ぐ。何気ない言葉を用いながら、僅か20文字の中に悲愁の心を見事に表現していると言えよう。 |
| 藤原妹紅 | :感情を排した言葉の方が、より深い内面を感じさせるのかな。 |
| 上白沢慧音 | :うむ。流石は絶句に優れ詩仙と称された李白の代表作だな。 :この詩の「静夜思」は、彼が好んだ楽府題の一つ。正確には唐代になって古い形式に倣って作られた“新楽府”と呼ばれるものだ。形式は五言絶句、しかし、実はこの詩は第二句と三句の平仄が規則から外れている。そのために厳密に言うと五言古詩に分類すべきものだ。だだ『唐詩選』では基準をゆるめて五言絶句に含めており、一般的にもそう見なされている。 :文法的に言えば光・霜・郷が平声の陽韻となる。また第三句と四句は対句になっている。 :いささか興を削ぐかもしれないが、注釈を加えておこう。 |
| 藤原妹紅 | :……ふふっ。どんなときにも「先生」なんだ。 |
| 上白沢慧音 | :まあ、そう言ってくれるな。 :まず、牀(床)とはベッド、寝台のことだが、大陸での牀は部屋の中心に位置し、西洋のベッドかそれ以上の大きさを持つ。しかもそれは寝るためだけではなく、昼間にくつろぐ場所でもある。 :第二句は部屋に差し込む月明かりが、あたかも地上に降りた霜のように白くきらきらと光っている、という内容だ。そして、月光が輝くのは部屋の床(ゆか)に敷石が用いられているからなのだ。 :副詞としての「疑ふらくは」という読み方は訓読における独特の用法だ。「く」とか「らく」は上に付く語を名詞化する働きを持っていて、「曰く」や「恐らく」、「思へらく」などの例があるな。 |
| 藤原妹紅 | :あう。完全に漢文の授業だねぇ……。 |
| 上白沢慧音 | :第三句、第四句は対句になっていて、振り仰いでは山上の月を眺め、うなだれては懐かしき故郷を思い出すという意味だ。 :さて、この詩は『唐詩選』を始め多くの詩文集に収められているが、実はテキストによっては細部が異なっている部分があるのだ。例えば『唐詩三百首』などでは題を「夜思」とし、「看月光」、「望山月」が「明月光」、「望明月」となっている。 :現在の中国で流布しているのはどうもこの『唐詩三百首』系のテキストのようなのだが……。どうもこの辺りは微妙でな。中国の古典文学研究に関わる世界には色々とあるようなのだ。元々、大陸で失われた古書籍が日本だけに残されていることも多く、そんなことも含めて本家との関係に微妙なものがあるのだろう。これは何というか、おそらくは文学や歴史の問題ではなく、むしろ政治的感情的な問題だろう。 |
| 藤原妹紅 | :ふ〜ん。 |
| 上白沢慧音 | :まあ、これは措いておこう。 :次に作者の李白について少し述べておこう。字は太白、自ら青蓮居士と号した。彼は長安一年(西暦701年)に西域で生を受けた。母が身籠もったとき、長庚星を夢見たとも伝えられる。蜀の地で育ち、若い頃は遊侠の徒と親交を結んだという。諸国を遍歴してその生涯を過ごした。 :一時は玄宗皇帝に仕え、翰林供奉となったこともあるが、その奔放な性格からか長くは続かなかったようだな。権力をものともしない人を喰ったようなエピソードが沢山残されているな。安史の乱では玄宗の第十子永王の幕僚となったが、永王が新皇帝の粛宗と対立し、逆徒として夜郎(貴州省)に流されることになった。結局その途中で大赦に会い、その後は再び各地を放浪した。そして宝応一年(西暦762年)、当途(安徽省)の県令李陽冰の下で病没した。 :船上で酔い、水面の月を捕えようとして水死したという伝説があるくらい、酒好きで知られている。もっともこれはあくまで伝説で、李華による墓誌銘には臨終の詩を賦して死んだとあるし、李陽冰も危篤の李白が詩稿一万巻を出してその整理を依頼したと言っている。何にせよ突然死んでしまった訳ではないらしい。 |
| 藤原妹紅 | :自ら称す臣は是れ酒中の仙と……。 :酒好きで、月が好きかぁ。誰かさんだったら気が合いそうねぇ。 |
| 上白沢慧音 | :太白は一斗百篇、筆を援りてたちどころに成る。 :自由奔放な作風で、明るく雄大な表現が多い。酒と侠と仙を愛す超俗的な人柄とその詩風から「詩仙」と称された。細かな規則に囚われない天才肌の詩人と言えよう。 |
| 藤原妹紅 | :我歌へば月徘徊し、 :我舞へば影凌乱す。 |
| 上白沢慧音 | :それは李白の「月下独酌」だな。 :そう、彼には月と酒の詩が多い。いつか他の作品を紹介することも有るかもしれないな。 |
| 藤原妹紅 | :授業はお終い? :―――――。 :―――――。 :遠い昔と比べたら、月も変わったと言うけれど……。 :それでも変わらず夜空にあることに違いはない。 :――私は何度、眠れずに月を眺めたのだろう。 |
| 上白沢慧音 | :妹紅……。 |
| 藤原妹紅 | :はは。 :私の故郷は遙かなる時の彼方。それはどんなに想えども決して届かぬ所。 |
| 上白沢慧音 | :……………。 |
| 藤原妹紅 | :いや、すまない慧音。 :大丈夫、今の私は幸せだ。生きていることが素晴らしいと感じられるからね。 :私が生きている意味、私の存在意義……、何時の日かそれが見つかると思えるようになったのだから。 :それに、今は共に月を眺める友がいる。 :何れにせよ私は永遠の時を超えて駆ける旅人、そして時の壁は絶対に越えられない。諦めもつくさ。 :その点―――――。 |
| 上白沢慧音 | :ん? どうした。 |
| 藤原妹紅 | :え、ああ。 :その点、手に届きそうな所に故郷がある方が苦しいのかな、なんてね。 |
| 上白沢慧音 | :ほう。 :永遠亭の連中か?:? |
| 藤原妹紅 | :いや、その、……………。うん。 :中には限られた時しか持たぬ者もいる。……あいつらは頭上の月をどんな想いで眺めるのだろうか、ふとそんなことを思っただけだ。 :まあ、例の時には平気で幻術を使っていたし、何とも思っていないのかもしれないけどな。 |
| 上白沢慧音 | :ふふふ。 |
| 藤原妹紅 | :! 何か可笑しいか? |
| 上白沢慧音 | :何、……いつの間にか、他者の心を思う気持ちが戻ってきたのだな。 |
| 藤原妹紅 | :ふ、ふん! :慧音と出会って、今また巫女達と出会って、……私が弱くなったんだよ。 |
| 上白沢慧音 | :否、そんなことはないさ。 :他人の痛みを理解してこそ本当の意味で強くなれるんだ。 |
| 藤原妹紅 | :ちぇっ。言葉じゃ慧音に敵わないよ。 :(慧音は自分の過去のことについて、何も言わない癖に……) |
| 上白沢慧音 | :この季節は本当に月が美しい。 :―――――。 :……私はそなたの旅路を共に行くことは出来ぬ。だが例え僅かの間でも、同じ季節を二人が共有するこの今は、憎しみ悲しみを忘れ、美しき太陰を愛でようではないか。 |
| 藤原妹紅 | :………そうね。 :……月光を看る、疑ふらくは是れ地上の霜かと…。 |
二人を玲瓏たる月の光が包み込む。 不死ならざる半獣は頭を挙げ、仮初めの幸福を幻視する。 故郷を喪った蓬莱人は頭を低れ、……一体何を思うのだろう。 |
参考文献
・吉川幸次郎/三好達治『新唐詩選』岩波新書1952
・目加田誠『唐詩選』(『新釈漢文大系19』明治書院1964)
・前野直彬注解『唐詩選』(下)岩波文庫1963
・松枝茂夫編『中国名詩選』(中)岩波文庫1984
・松浦友久編訳『李白詩選』岩波文庫1997