![]()
○平成20年1月
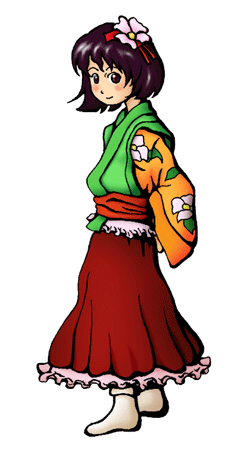 |
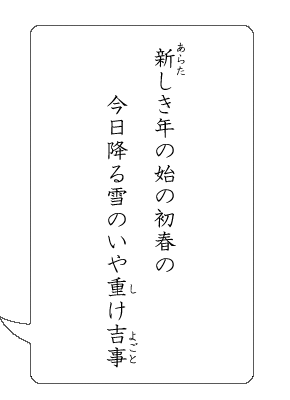 |
新しき年の始の初春の 今日降る雪のいや重け吉事
(新年乃始乃 波都波流能 家布敷流由伎能 伊夜之家餘其騰)
大伴家持 『万葉集』より
 |
 |
| 魂魄妖夢 | 稗田阿求 |
| 稗田阿求 | :さあさあ、折角だから上がっていって。お餅も沢山余っているはずだから、好きなだけ持って行ってね。 |
| 魂魄妖夢 | :……。年の初めから本当に申し訳ありません。 :どうしてもお餅のおかわりが欲しいとねだられましたので、里へやって来たのは良いのですが……。お店がお休みだということをすっかり忘れていました。 |
| 稗田阿求 | :良いから良いから。お客様は歓迎よ♪ :……………。 :新しき年の始の初春の今日降る雪のいや重け吉事。 |
| 魂魄妖夢 | :何だかおめでたそうな歌ですね。 |
| 稗田阿求 | :これは万葉集の巻二十に収められた最終の歌なんですよ。 :「右の一首、守大伴宿禰家持作る」とあり、作者は大伴家持です。詞書きには「三年春正月一日に、因幡国の庁にして、饗(あへ)を国都の司等に賜ふ宴の歌一首」とあります。「三年」とは天平宝字三年(西暦759年)のことです。原文は漢文と万葉仮名ですが。 |
| 魂魄妖夢 | :そうなのですか。本当にお正月の歌なのですねえ。 :万葉集と言えば、とても古い歌集と聞いておりますが――。 |
| 稗田阿求 | :そうですね。はっきりしたことは伝わっていませんが、我が国最古の歌集であることは確かですね。奈良時代までの歌が集められています。おそらく年月を掛け、複数の選者によって編まれたのでしょう。完結させたのは大伴家持と言われていますね。 :今回取り上げた歌が万葉集の中の最も新しい歌で、天平宝字三年に作られたものです。従って成立はそれ以降ということになります。今の定説では、宝亀年間(西暦770〜781年)ないし延暦初期(延暦年間:西暦782〜806年)に完結したとされているはずです。 |
| 魂魄妖夢 | :ああ、その撰者の大伴家持という人のことは私も知っています。 |
| 稗田阿求 | :かつては平城天皇の代の勅撰であるとか、橘諸兄が撰者であるとか言われたこともあったようですが……。 :兎に角も、二十巻で四千五百首余りの歌がある訳ですから。これも数え方によって4313首から4560首と幅があるのですけれどね。 :そんな訳で、万葉の言葉も、万の世で多くの時代の歌を万代に伝えるという意味だという説の他に、数多の歌のたとえという説もあるのですよ。 |
| 魂魄妖夢 | :そうなんですか。万葉集には私でも知っている歌が結構ありますよ。 :“あかねさす紫の行き標野行き 野守は見ずや君が袖振る”とか。 |
| 稗田阿求 | :ああ、額田王の歌ですね。第一期から第二期にかけての歌人ですね。 |
| 魂魄妖夢 | :第二期? |
| 稗田阿求 | :万葉集の歌は時代によって四期に分けられるのです。持統天皇や柿本人麻呂は第二期、山上憶良や山部赤人は第三期の歌人です。大伴家持は最後の第四期ですね。 :撰者の大伴家持は養老二年頃に生まれ、延暦四年に没した(西暦718?〜785年)歌人、政治家です。最終的には中納言従三位まで進んだ人ですね。そもそも大伴氏は、古来からの武力を以て朝廷に仕える有力な軍事氏族でした。しかし家持や彼の父である旅人は、伯母の坂上郎女と共に武人・政治家としてよりむしろ歌人として高名ですね。 |
| 魂魄妖夢 | :百人一首にも選ばれていましたよね。 :えーと、“かささぎの渡せる橋におく霜の白きを見れば夜ぞふけにける”。 |
| 稗田阿求 | :ええ。それは万葉集ではなく「家持集」にある歌です。これは定家好みの歌なんでしょう。 |
| 魂魄妖夢 | :定家好み、と言うことは、家持の歌は率直・具象的・素朴な万葉調というより繊細優美な古今風なのですね。 |
| 稗田阿求 | :そう、彼は万葉から古今への過渡期にあった歌人とも言えるのではないかしら。 :家持は始め純情な相聞歌を詠み、次いで越中守時代に風物を詠んだ時期があり、そして内面的な深さを深めていったとされてます。その作風は総じて繊細優美で感傷的ですね。 :古今風と言いましたが、彼は歌によって、現実を離れた想像の美を築こうとしていたようにも見えます。……この頃には既に大伴氏は政治上の勢力を失いつつあり、凋落の兆しを見せていたのですが、彼の作風にもそんな雰囲気が現れているような気がします。 |
| 魂魄妖夢 | :なるほど。 :……そういえば、「新しき」の読み方って、「あたらしき」では無いのですね。いつ頃から変わったのでしょうか?。 |
| 稗田阿求 | :さあ、私の記憶では平安時代くらいかしら。 :そう……、この歌の意味は、“新年の始めの今日、めでたく降り積もる雪のように、いよいよ吉事の重なれかし――ますます良い事が重なって欲しいものだ”ということね。 :詞書きにもあるように年頭のお祝いの歌なのです。 :新年正月の大雪は豊年の瑞兆であると考えられていたようです。この祝言性の豊かな歌を末尾に置くことで、この歌集を祝福し、末永く伝わって欲しいという願いを込めたのでしょう。 :古くからの有力氏族でありながら、藤原氏の政治的謀略によって次第にに圧迫された大伴氏の代表としての大伴家持の心情を表すという解釈もあるのですが、私は純粋に祝意を籠めたものと考えたいです。 |
| 魂魄妖夢 | :よくご存じですね。さすがは……、あれ?稗田阿礼さんって、同じ時代でしたっけ? |
| 稗田阿求 | :はは、ちょっと違うわね。そう、丁度第三期に当たっているのかしら。山部赤人や大伴坂上郎女が同世代になるのかしら?大伴家持は次の世代ね。 :折角だからもうちょっと万葉集について聞いていく? :万葉集には長歌、短歌、旋頭歌などの様々な種類形態の歌が収められているばかりでなく、あらゆる階層の人々による歌が集められていることが特色ね。収集された土地も全国に渡っているわ。東歌や防人の歌が典型的なものかしら? :丁度この頃は律令体制が確立し、歴史書や地誌をまとめる事業が行われていたの。万葉集もきっとこの事業の一つだわ。だからこそ全国の歌が、そしてあらゆる階層の人の歌が集められたのでしょうね。 |
| 魂魄妖夢 | :歌い方は素朴で直接的ですよね。 |
| 稗田阿求 | :そう、方言が使われたりしているし。「あゆのかぜ〜」とかね。 :その一方で万葉集の時代にはまだ、歌も一種の呪術と見なす意識が残っていたようだわ。 |
| 魂魄妖夢 | :言霊のようなものでしょうか。 |
| 稗田阿求 | :ええ、荘重な表現はそのような意識から生まれたものなのでしょう。 |
| 魂魄妖夢 | :ただ、やっぱり万葉的な歌より古今新古今調の歌の方が親しみやすいというか、分かりやすいというか、そんな感じもするのですが。 |
| 稗田阿求 | :うーん、そうねぇ。なんだかんだで和歌の主流は古今風なのだと私は思います。でもこうした芸術至上主義的なものは必ず行き詰まる。そんな時に参照されるのが万葉集なのではないかしら。実際、平安時代にはすっかり忘れられた感があったのだけど、やがては勅撰集とみなされて尊ばれるようになったわけ。特に人麻呂は歌聖と仰がれ、神と崇められたりしているわ。 :ま、そんな時でも、後世に変形を受けた形の歌として受容されたのだけれど。 |
| 魂魄妖夢 | :変形されたのですか? |
| 稗田阿求 | :ええ、「夏来たるらし……衣ほしたり」を「夏来にけらし……衣ほすてふ」にしたり、「田子の浦ゆうちいでて見れば真白にそ」を「田子の浦にうちいでて見れば白妙の」にしたりするのです。万葉集の実体が明らかになるのは近世以降の実証的な研究の成果を待たなければならないわ。 |
| 魂魄妖夢 | :今では随分尊重されていますよね。 |
| 稗田阿求 | :そう、近代以降はちょっと万葉偏重だと思うわ。写実主義が主流となった点は構わないのですが……。万葉的なものの過度な賞揚は、私に言わせれば曲解に基づいているものなのだけれど。 |
| 魂魄妖夢 | :曲解ですか? |
| 稗田阿求 | :そうです。“万葉の精神”なんてものを余りに純粋化してしまっているのですよ。思想としては余りに素朴ですよね。それから“ますらおぶり”なんて言うのが一人歩きしたりして、偏狭なナショナリズムに利用されたりもしたし。ばかばかしい限りよ。 |
| 魂魄妖夢 | :あー。上白沢さんとか、怒りそうな話ですねえ。 |
| 稗田阿求 | :そんなイデオロギーを抜きにして、ただ歌を味わえばいいのよ。 :だから、この歌も、そのままに一年の幸福を願う歌として見れば良い……。きっと作者の思いもそこにあるのだもの。 |
| 魂魄妖夢 | :そうですね……。 |
| 稗田阿求 | :??? :何だかすっきりしない顔ですね? :私としては、ぎりぎりの所で暗鬱な話に振らずに上手くまとめたつもりなのですが。 |
| 魂魄妖夢 | :あ、勿論です。ですが………。 :えと、あの、その。なんと言いますか、不安なんですよ。これまで、こんなおめでたい内容の事って無かったように思うんです。正月でも、春も秋も何というか、こう暗い話ばかりだったような……。 :だから、今月も何か落とし穴があるような……。 |
| 稗田阿求 | :……………。 :それは気にしすぎでしょう。 |
| 魂魄妖夢 | :それならば良いのですが……。 |
| 稗田阿求 | :それでは皆さん、今年が良き年でありますように。 |
| 魂魄妖夢 | :?? 皆さん、なんですか? |
| 稗田阿求 | :ああ、気にしないでね。 :……………。 :あ、よく考えると、正月早々「冥界からの使者」が出ている時点で、めでたくないようにも思えますねぇ……。 |
| 魂魄妖夢 | :え、あ、う。 :(しゅん……) |
参考文献
・高木市之助,五味智英,大野晋校注『萬葉集』(4)(『日本古典文学大系7』岩波書店1962)
・小島憲之,木下正俊,佐竹昭広校注・訳『萬葉集』(4)(『日本古典文学全集5』小学館1975)