![]()
○平成20年3月
 |
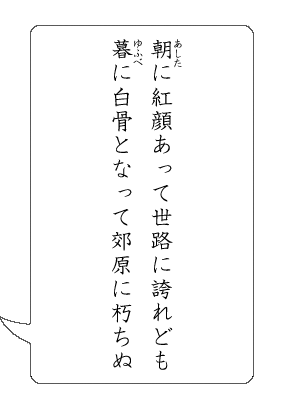 |
朝に紅顔あって世路に誇れども
暮に白骨となって郊原に朽ちぬ
藤原義孝(「無常」『和漢朗詠集』巻下より)
 |
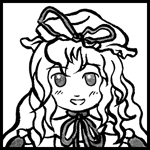 |
| 上白沢慧音 | 八雲紫 |
| 上白沢慧音 | :もうすぐ春がやってくる。……もう何度季節は巡ったのだろうか。時の流れは余りに速い。 :共に過ごした時間は最早私の記憶の中に残るのみ。総ては流転する、命もまた然り。 :そして、いつかは私も……。 :「朝に紅顔あって世路に誇れども、暮に白骨となって郊原に朽ちぬ」 |
| ??? | :「すでに無常の風きたりぬれば、すなはちふたつのまなこたちまちにとぢ、ひとつのいきながくたえぬれば、紅顔むなしく変じて、桃李のよそほひをうしなひぬるときは、六親眷属あつまりて、なげきかなしめども、更にその甲斐あるべからず。さてしもあるべき事ならねばとて、野外にをくりて、夜半のけぶりとなしはてぬれば、ただ白骨のみぞのこれり」 :……………。 :「朝に紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり」 |
| 上白沢慧音 | :む、何故こんな所に? ――ああ、そうか。 |
| 八雲紫 | :ふふ。こうした三昧の地は人間の里の周縁部にあるもの。則ち此処は境界の地。私の統べる場所よ? |
| 上白沢慧音 | :まあ、確かにそうだったな。 :そう言えば、そなたの言葉は蓮如の「白骨の御文」だな。私の述べたのは『和漢朗詠集』なんだが……。 |
| 八雲紫 | :無粋な人ね、教師ってみんなこんななのかしら? どうでも良いじゃない。 |
| 上白沢慧音 | :ま、そう言われればそうなんだが。 |
| 八雲紫 | :貴女のは「白骨の御文」の謂わば元ネタでしょ。確か少将藤原義孝の作だったわね。 |
| 上白沢慧音 | :そう。『和漢朗詠集』の中でも有名な詩とは思うのだが……。でもやはり、ここまで人口に膾炙したのは蓮如がこれを自分の文章中に引いたからなのだろう。 :現在でも「白骨の御文」は、世の無常を表す言葉として良く知られているし、真宗の葬儀や法事でも聞くことが出来るものだからな。 |
| 八雲紫 | :優れた言葉には、時代を超える力があるものなのよ。 |
| 上白沢慧音 | :義孝の詩は『和漢朗詠集』の下巻の「無常」の項に載っている。 :ちなみに、『和漢朗詠集』というのは、長和二年(西暦1013年)頃に成立した詩文と和歌のアンソロジーだ。藤原公任(康保三年(西暦966)〜長久二年(西暦1041年))の撰というのが通説だ。公任はあの藤原道長と同時代人だ。彼は藤原政権の高級官僚であるとともに、和歌、漢詩両面での学才が謳われた芸術家でもあった。 :「朗詠」とは平安中期の歌謡の一つで、漢詩文の佳句や和歌に節を付けて謡うもののことだ。始めは音読が多かったのが、やがて訓読へと変化していたのではないかと言われているな。 :『和漢朗詠集』には白居易や菅原文時の詩文から取られた佳句が589首あり、柿本人麻呂等の和歌216首が添えられる。美しく親しみやすい詩句が多く、広く読まれた作品だ。後世の文学へも与えた大きな影響も見逃せない。詩文は勿論、軍記物のような語り物や梁塵秘抄のような謡い物、唱道文学、説話文学への影響も小さくない。 |
| 八雲紫 | :……………。 :貴女、教師は天職ね……。 |
| 上白沢慧音 | :――話を元に戻そう。 :朝有紅顔誇世路 (朝(あした)に紅顔あって世路に誇れども) 暮為白骨朽郊原 (暮(ゆふべ)に白骨となって郊原に朽ちぬ) :これは七言詩の一聯の体裁だ。 :朝には浮き世を我が物顔で誇らしげにしていた若く華やかな人が、夕には白骨となって野外の塚に埋もれ朽ちてしまうかもしれない。生ある者は必ず、老い、死すべきものであり、人生は無常である。 :この詩に込められているのは、こんな意味なのだろうな。 |
| 八雲紫 | :美しい女性の死を悼んで作った詩なのよね。 |
| 上白沢慧音 | :そう。美人だった冷泉院の后が25歳で崩じた時に作ったと伝えられる。註には「是ハ三代前冷泉院ノ后、麗景殿女御、日本第二ノ美人也、廿五而死シ給タル事ヲ歎ジテ作也」とあるな。 |
| 八雲紫 | :そしてこの悲劇には続きがある、のだったわね |
| 上白沢慧音 | :世の無常を嘆いた義孝自身もまた、間もなく世を去ったのだ。享年二十歳。父親伊尹(これまさ)が摂政太政大臣という、恵まれた青年貴族も病には勝てなかったのだな。 |
| 八雲紫 | :この詩はあたかも自分自身への哀悼歌のようね……。 |
| 上白沢慧音 | :……同感だな。 :一方の「白骨の御文」は、浄土真宗の僧蓮如による「御文」の中にある一文だ。東本願寺では「御文」、西本願寺では「御文章」と呼んでいるそうだが。 :作者の蓮如は応永二十二年(西暦1415年)に生まれ、明応八年(西暦1499)に没した、浄土真宗の中興の祖とされる僧だ。諡号を慧灯大師という。京から近江、越前と渡り歩き、北陸に真宗を広めた。結果として彼一代の間に本願寺を巨大な教団に育て上げたことになるな。 :蓮如は布教のために平易な文章で教祖親鸞の教えを説いた。この教学を述べた手紙形式の文章が「御文/御文章」と呼ばれるもので、「白骨の御文」もこれに含まれている。 :面白いのは、後になる程文章が短くなっていることだ。これについて本人は「このごろのものは、ものを聞いてもすぐに退屈してしまうので、肝要のことを理解できるように、御文を短くしたのだ」と言っていたそうだ。 :何というか、時代が変わっても“教える者の悩み”というのは変わらないもののようだな。 |
| 八雲紫 | :ふふふ。そうねぇ。 :しかし、広く庶民へと布教するには良い戦略だったわね。平易な仮名書きの「御文」には、真宗の全ての教えが集約されているといっても良いではないかしら。この国では基本的に仏典の和訳を作らなかったのにね。 |
| 上白沢慧音 | :確かにそうかも知れないな。まあ、イスラム教の例もあるから、聖典を翻訳しないことが悪いとは限らないが。 |
| 八雲紫 | :それはそうと、浄土真宗は絶対的な他力思想よね。念仏も、阿弥陀仏への感謝を示す為のものという認識だったはずだし……。 :私には何だか基督教みたいな一神教に近い雰囲気が感じられるわ。 |
| 上白沢慧音 | :うん。確かにそうだ。 :一説には真宗を含めた浄土系宗派の本尊である阿弥陀仏は、ゾロアスター教の光明神アフラ・マズダの仏教化したものという。だから一神教というか、絶対的な創造主を想定する教えに近いと感じられるのも当然なのかも知れないな。 |
| 八雲紫 | :アフラ・マズダねぇ……。ああいう二元論はちょっと馴染めないわ。 :……………。 :……それにしても、貴女は何故こんな所に来ているのかしら。最早香華を手向けに来る者も無いのに。私たち人ならざる者にとっては一人一人の人間なんて、儚い影のようなものでしょう? :それに――。 |
| 上白沢慧音 | :祖霊は墓所にのみ在るのでは無い。祖霊は山に、海の彼方に、そして家族のもとにいる。人間の里というものは、過去の人間たちが積み重ねた歴史の上に存在しているのだ。 :墓所はあくまで生死の“けじめ”をつけるためのものだ。だから、謂わばここは失われた人の俤を偲ぶための契機を与える所なのだ。墓所が祭祀の場で在る必要など無いのだよ。 :それにな、喩え今生きている人間たちに忘れられてしまったとしても、かの者たちは私の中では生き続けているのだから。 |
| 八雲紫 | :人間達の思い、ねぇ。 :―――――。何故そこまで人間を想うことが出来るの? :……私はあなたが人間の里で受けた扱いを知っているのよ。人間なんて、排他的で猜疑心が強い自分勝手なイキモノだわ。貴女に心から感謝しているのかどうかさえ怪しいわ。 :移り変わるのは人の心。生きる長さは関係ない。そんな人間たちを護ろうとするのは何故なの? |
| 上白沢慧音 | :確かにな。人は「外部」を想定し、異質な者たちを排除してゆくことで共同体を維持している。これはそなたにとっては、良く解ることだろう? :このような方法の選択は、超常の力を持たぬ個々の普通の人間がこの世界で生きて行くためにはやむを得ない事だろう。生きたいと願うのは当然のこと。そのために持てる力を振り絞った結果に過ぎない。同じく死すべき存在の我等にはそれを責めることはできぬ。 :「一生すぎやすし。いまにいたりて、たれか百年の形体をたもつべきや。我やさき、人やさき。けふともしらず、あすともしらず。をくれさきだつ人は、もとのしづく、すゑの露よりもしげし」 :……私は人間が好きだ。そう、誰もが限りある生を懸命に生きているのだから。 :ここに眠る者たちも、皆そうだった。決して聖人君子ではなかったかもしれぬ。それでも愛すべき者たちだった。夢を追い、家族や里を護り、そして旅立っていった。誰もが精一杯生きたのだ。 :そして我々もまた、彼らと同じではないのか? :「生ある者は必ず滅す。楽しみ尽きて哀しみ来たる。天人なお五衰の日に逢わん」 |
| 八雲紫 | :分からないわね……。 :人間も、世界も変わってしまう。移り行く時の中では、護るものも又いつか空へと帰す。貴女はそれも良く分かっているのでしょう? :我等人ならざる者は己が時間を生きる。その自由こそ私達の本質の筈。そして私達は世界と一体となって生きるわ。人間達のように彼我を分離するのではなく、この大地、風、水と共に在るの。 :何故自由に生きない?何故己が為に生きない? この幻想郷ではむしろそんな姿は不自然だわ……。 |
| 上白沢慧音 | :それが私の在り方だからな。私の中の理、これは譲れないものだ。それに……。やはり私は人間たちが好きなのだ。 :……そなたがこの幻想郷を愛し、護っているのと同じにな。 |
| 八雲紫 | :……………。 :……ふん。 |
| 上白沢慧音 | :私は幻想郷の歴史は総て分かるのだ。そなたが此処に来た訳さえも――。 |
| 八雲紫 | :さぁて。私はもう行くわ。こんな所にずっと居たら気分が滅入ってしまうわ。 :だいぶ暖かくなってきたし、巫女でもからかいに行くわ。 |
| 上白沢慧音 | :……………。 |
| 唐突に境界に潜む妖怪は姿を消し、慧音は辺りをゆっくりと見回しました。 そして気付いたのです。辺りに春の気配がはっきりと感じ取れる事に。 木々に、大地に、萌え出でようとする新しい生命の息吹が満ちていました。 花咲く春はもう間近までやって来ていたのです。 |
参考文献
・川口久雄・志田延義校注『和漢朗詠集 梁塵秘抄』(『日本古典文学大系73』岩波書店1965)
・笠原一男校注『蓮如文集』岩波文庫1985