![]()
○平成20年9月
 |
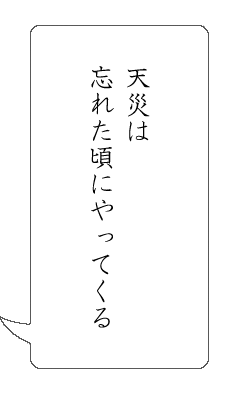 |
天災は忘れた頃にやってくる
寺田寅彦
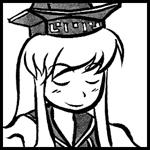 |
 |
| 上白沢慧音 | 永江衣玖 |
| 上白沢慧音 | :!! :何で貴女が此処に? :神社には要石が差されたはずではないのですか? |
| 永江衣玖 | :あ、いや、別に……。 :あの、違うんです。今日は地震を知らせに来たのではないのです。 :実はその、例の要石のために此処へ降りてくる必要は全然無くなってしまったのですが……。いつぞや神社で出会った方々に又会いたくなりまして。あの紅白の巫女とか。 :今までこんな事はなかったのですが……。 :それはそうと、私が降りてきていたことがよく分かりましたね。神社にはいつもは里人は寄りつかないと聞いていますし、こっそり行けば騒ぎになることもないかと思っていたのですが。 |
| 上白沢慧音 | :ああ、貴女もですか。 |
| 永江衣玖 | :?? |
| 上白沢慧音 | :兎に角、貴女は龍宮の使いなんですよ? :貴女のような存在が地上に居れば、私のような者には直ぐ分かります。少し鋭い人間も気付いているかも知れない。貴女は自分の持っている力が大きいことを理解すべきです。 |
| 永江衣玖 | :そ、そうですね。中途半端な行動は、却って疑惑を招きかねないですね。 |
| 上白沢慧音 | :むしろ、堂々と真っ直ぐ神社へ向かえば良いのです。あそこでなら、何が起こっても皆納得しますから。 :……………。 :特に今は時期が悪い。今頃貴女が出て来ると、どうしても思い出してしまうのですよ。 |
| 永江衣玖 | :え? ああ、今から80年ちょっと前くらいでしたか。 |
| 上白沢慧音 | :そう。……もっとも、今生きている人間たちの多くは忘れてしまっているが。 |
| 永江衣玖 | :そんなものなのですか? まあ、私たちとは生きる長さが全然違いますし、仕方がないのでしょう。 |
| 上白沢慧音 | :――そうとばかりも言えない。 :人は辛いことや悲しいこと、失敗の経験などを思い返すのは不得意なのです。思い出したくないから“忘れてしまう”のですよ。地震は人力では避け得ない恐ろしい災害だったのですから。 :「鳥にあらざれば空をも翔りがたし、龍にあらざれば雲にも又上りがたし」 :……まあ、それでもやはり長さの影響も大きいでしょうね。大地震のような天災が頻繁に起きていれば、忘れることもないでしょうし、厭でも対策を立てざるを得ない。 |
| 永江衣玖 | :雨風や暑さ寒さに備えるように、ですか。 |
| 上白沢慧音 | :そうです。でもそれは叶わぬこと、結局「天災は忘れた頃にやってくる」のですから。 :……過去の知識を後世に伝え、それによって一人一人が短い寿命しか持たぬ人の身ながら文明を築いてきた筈なのに。きちんと過去の経験を、悲劇の原因を忘れないでいれば、……多くの悲劇は防ぐことができたのだ。 :――だから、悲劇の多くは天災ではなく“人災”なのだ。 |
| 永江衣玖 | :天災は……。ああ、その警句は聞いたことがありますね。 :ふふ。別に地震そのものは意思を持っている訳ではないので、その時期も場所も人間たちの活動とは無関係ですけれどね。ってこの前の惣領娘様の件は極めてイレギュラーな事で……。 |
| 上白沢慧音 | :理屈では確かにそうなのですが……。 :私たちにとっては、必ずしもそうではないのです。 |
| 永江衣玖 | :どういう事です? |
| 上白沢慧音 | :人間が大地震などの天災に意味を与えるのですよ。 :“これは天の警告である”とか“政治の乱れに対する大地の怒りである”と言った風に。 :貴女も要石やそれを司る神社に関わっているなら知っているのでしょう?かつて地震は世直しの象徴とも見なされていたことを。金持ちや支配層に打撃を与える庶民の味方、世直しの神の御業と。 |
| 永江衣玖 | :――ああ、あの頃は私たちと人間たちの距離がもう少し近かったような気がします。 |
| 上白沢慧音 | :そうやって「意味」を与えることによって、人間は得体の知れない恐怖から免れようとしたのです。 :私たちは弱い生き物だ。それでも“天災”に意味を与えれば、それを防ぐために為すべきことが見いだせる。そうやって人間は生きてきたのです。 |
| 永江衣玖 | :そんな人間でも、見たくないものは「忘れてしまう」のですね。 |
| 上白沢慧音 | :そんな人間だからこそ、なのかも知れませんが。 |
| 永江衣玖 | :あれ、そう言えば件の警句、「天災は忘れられたる頃来る」ではなかったですか? ん? 「天災は忘れた頃来る」でしたっけ。 |
| 上白沢慧音 | :ああ、実はこれは元々“書かれたもの”ではなかったらしい。だから様々な形で伝わっているようなのです。 :この警句の作者は一般に寺田寅彦とされています。明治十一年(西暦1878年)に生まれ、昭和十年(西暦1935年)に亡くなった物理学者、随筆家ですね。熊本の五高で夏目漱石に出会い、以後親しく交わることとなります。 :漱石の『三四郎』の野々宮宗八、『吾輩は猫である』の水島寒月のモデルになったと言われています。 :自らも、吉村冬彦等のペンネームを用いて随筆をさかんに発表していますね。随筆には中々素晴らしい作品が多い。また、科学者としては、当時珍しい仮説提示型の研究者であったようです。 :原子物理学の先駆けとなり、また地球物理学者として地震やその防災対策にも取り組んでいました。弟子に雪の結晶の研究で有名な中谷宇吉郎がいます。 |
| 永江衣玖 | :へぇ。面白い人なのですね。 |
| 上白沢慧音 | :この人の文章には考えさせられるものが沢山あります。何時か又触れることもあるでしょう。 :話を元に戻すと、寺田寅彦自身が残した文章の中に、この言葉は無いそうです。 |
| 永江衣玖 | :え? そうなんですか? |
| 上白沢慧音 | :これを寺田の言葉として紹介したのは、弟子の中谷宇吉郎らしい。 :寺田の残した文章には無いことや、流布する元になったのが自分の書いた記事らしいということを、自ら書き残しているのです。 :経緯としては、まず昭和15年(西暦1940年)前後に、中谷が東京日々新聞上の「天災」という短文で「天災は忘れた頃来る」という言葉を“千古の名言である”と紹介。さらに戦時中、朝日新聞が一日一訓の類を編集した時に、九月一日の項目として採用されたということらしい。 :中谷によれば、寺田の話にしばしば出た言葉であり、中谷自身も、改めて調べるまで雑誌か何かに寺田が発表した言葉であったと信じていたらしい。 |
| 永江衣玖 | :では、その言葉は中谷宇吉郎が作った言葉と言えるのでしょうか? |
| 上白沢慧音 | :それはどうでしょう。寺田は同じような内容のことを、幾つかの文章で書いていますし(※1)、中谷も「書かれたものには残っていないが、寅彦の言葉にはちがいないのであるから、別に嘘をいったわけではない」と言っています(※2)。 :中谷の意図から見ても、寺田寅彦の言葉と見なして構わないのではないでしょうか。 |
| 永江衣玖 | :そうですね。近くにいた人がその人の言葉と認識していた訳ですしね。 |
| 上白沢慧音 | :そう言えば、中谷は同じ文章の中で、やはり寺田寅彦の弟子である地球物理学者の坪井忠二も、この言葉が寺田の随筆中にあると思い込んでいたと書いています。また、昭和24年(西暦1949年)に刊行された地震学者今村明恒の遺著『地震の国』にも寺田寅彦が何かの雑誌に書いた警句として、「天災は忘れた時分に来る」という言葉を紹介しています(※3)。 :一般に広まったのは、中谷宇吉郎の文章によるとしても、それまでに関係者の間にはこの言葉が寺田のものとして広まっていたのかも知れませんね。 |
| 永江衣玖 | :有名な言葉なのにも関わらず、なんだか分からないことも多いのですねぇ。 |
| 上白沢慧音 | :ええ、ですから、言葉にも様々なバリエーションがあるのでしょうね。 :例えば、高知の旧居跡にある寺田寅彦記念館には、同郷の牧野富太郎の筆による記念碑がありますが、そこには「天災は忘れられたる頃来る」とあるのです。 |
| 永江衣玖 | :ああ、私が聞いたのはその形のような気がします。 |
| 上白沢慧音 | :寺田がこのような警句を発するきっかけとなったのは、かつて起きた地震や火災の記録が、関東大震災の時に全く生かされなかったことを知ったためと言います。 :関東大震災の時には、揺れよりむしろ火災による被害が大きかったのですが、中でも本所被服廠跡では四万人が焼死したと言われています。この時にはハンブルグ現象とも称される火災旋風が起きたのですが、寺田は記録を調べてかつて江戸の火災の際にもこうした現象が起きていたことを知りました。人間は過去の経験を何も生かすことが出来なかったのです……。 :彼は地震の予測は統計的、確率的にしか評価できないと考え、予防対策を重視することを主張しました。それでも、何時来るか分からない地震への対策は中々進みませんでした。大震災の教訓も時が経てば忘れられてしまうのではないか、そんな危惧が現れた言葉でもあるのでしょう。 |
| 永江衣玖 | :成る程。人が歴史に学べるかどうか、長い時間間隔を持って現れる問題にきちんと対峙できるのか、その難しさを的確に言い表した言葉でもある訳ですね。 |
| 上白沢慧音 | :……………。 :人は困難を乗り越えて来た。過去に学び、未来を信じて。時に打ちのめされても、必ずまた立ち上がるのです。 :数多くの地震を見てきた貴女なら分かるでしょう? |
| 永江衣玖 | :―――――ええ。 :……そして悲劇もまた繰り返されてきた訳ですが。 :まあ、今度こそ歴史に学ぶことができる、そう信じるのも悪くはないでしょう。希望は前を向いて生きるためには欠かせないものですからね。 :―――――。 :これまでは私が地上へ下るのは、ただ龍神の意を伝える時のみでした。特に人間の行動に関心も無かったし、季節が巡って行くのをただ見守るばかりでした。 :でも。 :あなた方に出会って、なんだか此方の世界にも興味が出てきてしまいました。下界の者と会話するというのも、中々楽しいものなのですね。……惣領娘様の気持ちも少し分かるような気がします。 :地震が無いから来ないというのでは、なんだか勿体ない気がしてきました。 |
| 上白沢慧音 | :あの者はあらゆる存在を惹き付ける性質を持っているようですね。 :参拝客は余り集められていないようですが。 :あ、でも羽衣の扱いとか、注意して下さいよ。色々な意味で人は弱いんです、ごたごたは起こさないで下さいよ。 |
| 永江衣玖 | :ふふふ。分かっていますよ。……でも、みんなが期待したら、応えてしまうかも。 :偶に主役になるのも、悪くはないかもね。 |
| ※1:例えば、寺田寅彦は次のような文章を残しています。 ○「大正十二年のような地震が、いつかは、恐らく数十年の後には、再び東京を見舞ふだらうといふことは、これを期待する方が、しないよりも、より多く合理的である。その日が来たときに、東京はどうなるだらう、おそらく今度と同じか、むしろもっとはなはだしい災害に襲はれさうである(中略)もし百年ののちのためを考へるなら、去年くらいの地震が、三年か五年に一度ぐらいあったほうがいいかもしれない」(寺田寅彦『鑢屑』1924より) ○「平生からそれに対する防御策を講じなければならない筈であるのに、それが一向に出来ていないのはどうふいふ訳であるか。そのおもなる原因は、畢竟さふいふ天災が極めて稀にしか起らないで、丁度人間が前車の顛覆を忘れた頃にそろそろ後車を引き出すやうになるからであらう」(寺田寅彦『天災と防国』1938より) ※2:中谷宇吉郎は次のように記しています(『百日物語』文藝春秋社1956より) ○「実はこの言葉は、先生の書かれたものの中には、無いのである。しかし話の間には、しばしば出た言葉で、且つ先生の代表的な随筆の一つとされている『天災と国防』の中には、これと全く同じことが、少しちがった表現で出ている」p.128 ○「もともとこの言葉は、書かれたものには残っていないが、寅彦の言葉にはちがいないのであるから、別に嘘をいったわけではない(中略)これは、先生がペンを使わないで書かれた文字であるともいえる」p.129 ※3:今村明恒は次のように記しています(『地震の国』文藝春秋社1949より) ○「三五 天災は忘れた時分に来たる(中略)天災は忘れた時分に来る。故寺田博士が、大正の関東大震災後、何かの雑誌に書いた警句であったと記憶してゐる」p.197今村 |
参考文献
・中谷宇吉郎『百日物語』文藝春秋社1956(初出は『西日本新聞』1955年7月〜9月のコラム)
・西尾光一校注『鈴木三重吉・森田草平・寺田寅彦・内田百間・中勘助集』筑摩書房1971(『現代日本文学大系』29)
・角川源義編『寺田寅彦』角川書店1961
・太田文平『寺田寅彦』新潮社1990
・今村明恒『地震の国』文藝春秋社1949
・竹内均監修『科学の先駆者たち』教育社1985
・竹内均編『ひらめきと執念で拓いた地球の科学』ニュートンプレス2002
・『産経新聞』2003年9月14日,10月5日