![]()
○平成21年4月
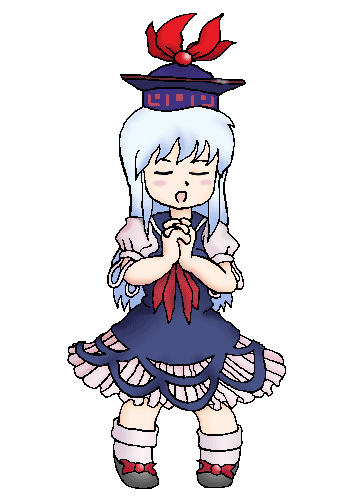 |
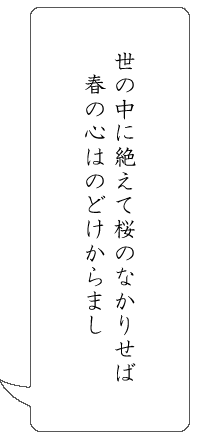 |
世の中に絶えて桜のなかりせば
春の心はのどけからまし
在原業平『古今和歌集』巻一春上−五三
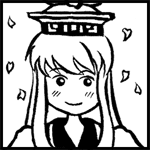 |
 |
| 上白沢慧音 | 西行寺幽々子 |
| 上白沢慧音 | :あれからどれだけ経ったか……。又花咲く季節がやってきたな。 :……ふふ。もう里では憶えている者も無くなったが。それでも。 :私と、この木が憶えているさ。 |
| ??? | :いざ桜〜我も散りなん、一盛りぃ。 :誘う嵐も心して〜、月も曇らぬ天の原ぁ〜。 |
| 上白沢慧音 | :おや、これはこれは。珍しく客人があるようだ。 |
| 西行寺幽々子 | :どうしたの? 折角のお花見なのに、賑(にぎ)やかな宴(うたげ)はお嫌い? |
| 上白沢慧音 | :ま、偶(たま)には静かに花を楽しみたい時もある。 |
| 西行寺幽々子 | :ふーん。そういうものかしら。 :―――――。 :あら、この樹は……。ああ、随分長生きなのねぇ。 |
| 上白沢慧音 | :最近増えてきた里桜とは違うからな。白玉楼の桜程じゃないけれどね。 |
| 西行寺幽々子 | :……誰かの思い出の木なのね。 |
| 上白沢慧音 | :そう、人の想いを受け継ぎ、里を見守り続ける木という訳だ。 :木々は人間と違って長生きだからな、そういった思いを受け止める対象となるのだろう。何れ人間の暮らす世界はそうしたモノに満ち満ちている。 :今の私たちは、過去に生きた人々の思いの上に生きているのだ。こうした木々が命短き人間と、積み重ねられた過去との縁となっているのだろう。 |
| 西行寺幽々子 | :桜の樹はそうした対象としてうってつけというわけね。 :えーと、里や神社で咲いている、あの里桜もそうなのかしら。 |
| 上白沢慧音 | :どうだろう? あれは主に染井吉野、寿命は百年前後だろう。染井吉野は人間とともに成長し、そして老いてゆくのだ。 :そのライフサイクルはむしろ人間に近い。だから、あの種の桜の樹は、むしろ個人の一生に比べられ得るものなのではないだろうか。 |
| 西行寺幽々子 | :なるほどね。 |
| 上白沢慧音 | :もっとも、大切に世話をすれば長生きも可能らしいし、植え継がれてゆけばまた異なる位置づけとなるかも知れぬがな。 |
| 西行寺幽々子 | :何れにせよこの国の人間が桜が大好きだと言うことには変わりはないわね。 :まあ、私たちのような“元人間”もそうだしね。 |
| 上白沢慧音 | :そうだな。 :人間は、その社会さえも桜の季節と結びつけているように思えるなあ。丁度年度の変わり目が桜の季節なのだ。別れと新たな出会い、そんな節目の行事が桜咲く下で行われている訳だから。 |
| 西行寺幽々子 | :ふふふ。春が近づけば何時咲くか、何時咲くかと心をざわめかせ。咲いたら咲いたで何時散ってしまうかと心配する。 |
| 上白沢慧音 | :桜花は、春の訪れと旺盛で新しい生命力を象徴するものであり、一方で儚く散りゆく死の象徴でもある。 :そう、桜咲く春は希望と歓喜、不安と怖れ、そして無常観さえも混在する、心騒ぐ季節なのだ。 |
| 西行寺幽々子 | :そうねぇ。古人は斯く詠っているわ。 :「世の中に絶えて桜のなかりせば、春の心はのどけからまし」(※1) |
| 上白沢慧音 | :ああ、在五中将(※2)か。ならばこう返すべきか。 :「散ればこそいちど桜はめでたけれ、うき世になにか久しかるべき」(※3) |
| 西行寺幽々子 | :そうよねぇ。 :―――――。 :ああ、桜が散ってゆくわ。 :「月やあらぬ春や昔の春ならぬ、わが身ひとつはもとの身にして」 :―――――。 :いつの日か皆、そう、大切な友でさえも私の元を去ってゆくわ。その時私は……。 |
| 上白沢慧音 | :―――――。 |
| 西行寺幽々子 | :ふふっ。やはり桜は罪ねぇ。ただ見ているだけなのに、こんなにも心乱される。 :花は静かに、美しく咲いているだけなのに。 |
| 上白沢慧音 | :私たちが桜に強い思い入れを持つのは、その花が美しいだけではない。 :おそらくそれは、人々の想いを受け止めて呉れているように見えるからだろう。 |
| 西行寺幽々子 | :うんうん。それに、桜の花を見ることで様々なことを考えさせられてしまうからではないかしら。 |
| 上白沢慧音 | :そうだな。……過去の想い、未来への希望、そして今を生きる私たち。 :……生と死をも超えた全てが、桜の花舞う今この一瞬に交叉している。 |
| 西行寺幽々子 | :……………。 :……。 :われも散りなん、一盛り……。 |
| 上白沢慧音 | :妙なる花の景色かな……。 |
| 脚注 ※1:『古今和歌集』(巻一春上)に収められた在原業平朝臣の歌。この歌は他にも、『新撰和歌集』一、『古今六帖』六、『業平集』などにも採られています。詞書きには「渚の院にて桜を見てよめる」とあります。「渚の院」とは、交野(かたの)の郡(現大阪府)にあった文徳天皇の離宮のこと。後に在原業平と親しかった惟喬(これたか)親王の持ち物となりました。当時交野は桜の名所として知られていました。 歌の意味は、“この世の中に、あの美しい桜というものが全く無かったとしたら、散ることを心配し心痛めることもなく、春の人の心はさぞかしのどかでいられるだろうに”といった所です。「〜せば…まし」は反実仮想の表現で、“もし〜だったなら、…だろうに”の意味です。ここでは、いっそ桜などなければ…といった意味で使われています。勿論逆説的に桜の美しさを表現している訳ですが。 ※2:在原業平(ありわらのなりひら)(西暦825-880年)。平安時代の貴族・歌人。平城天皇の孫、さらに母方の祖父は桓武天皇でしたが、臣籍に下り在原氏を名乗りました。惟喬親王(文徳天皇の皇子、同じく文徳天皇の皇子であった清和天皇と皇位を争ったと伝えられる、小野宮として木地師の伝説にしばしば登場します)に仕えました。 伝説では容姿端麗な風流人として描かれ、『伊勢物語』の主人公は在原業平とされています。様々な恋のエピソードが伝えられています。 業平は和歌に優れ、六歌仙のひとりとされます。30首が採られるなど、『古今和歌集』における代表的歌人です。彼の歌は、情熱的でしかも技巧にも優れていたと評価されています。 ※3:在原業平を主人公とする歌物語『伊勢物語』には、(※1)の歌について、より詳しく詠まれた状況が記されています。 「むかし、惟喬の親王と申す親王おはしましけり。山崎のあなたに、水無瀬といふ所に宮ありけり。年ごとのさくらの花ざかりには、その宮へなむおはしましける。その時、右の馬の頭(かみ)なりける人を、常に率(ゐ)ておはしましけり。時世をへてひさしくなりにければ、その人の名忘れにけり。狩はねむごろにもせで、酒を飲みつゝ、やまと歌にかゝれりけり。いま狩りする交野(かたの)の渚の家、その院の桜ことにおもしろし。その木のもとにおりゐて、枝を折りてかざしにさして、上中下みな歌よみけり。馬の頭なりける人のよめる。 世の中に絶えて桜のなかりせば春の心はのどけからまし となむよみたりける。又人の歌 散ればこそいとゞ桜はめでたけれうき世になに久しかるべき」(『伊勢物語』八十二段より) ここでの「右の馬の頭なりける人」とは、ぼかした表現ではありますが、右馬頭であった在原業平を指しています。同時に詠まれた(※2)の歌の意味は概略、“散るからこそ、いっそう桜の花は素晴らしいのです。この憂き世の中には、久しく永らえる存在などありはしないのですから”というものです。 |
参考文献
・佐伯梅友校注『古今和歌集』(『日本古典文学大系8』岩波書店1958)
・小沢正夫/松田成穂校注・訳『古今和歌集』(『新編日本古典文学全集11』小学館1994
・大津有一校注『伊勢物語』岩波文庫1964
・阪倉篤義校注,大津有一/築島裕校注,阿部俊子/今井源衞校注『竹取物語・伊勢物語・大和物語』
(『日本古典文学大系9』岩波書店1957)