![]()
○平成21年5月
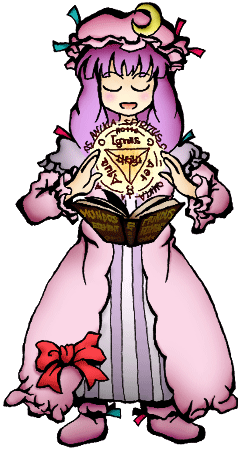 |
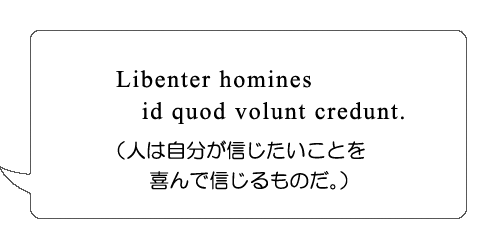 |
Libenter homines id quod volunt credunt.
Gaius Julius Caesar "Commentarii de Bello Gallico" 3-18
人は自分が信じたいことを喜んで信じるものだ
ガイウス・ユリウス・カエサル『ガリア戦記』第3巻18
 |
 |
| 霧雨魔理沙 | パチュリー・K |
| 霧雨魔理沙 | :ああ、気候が良いと気分も良い。読書にもぴったりの季節だぜ(※注1)。 |
| パチュリー | :……他人の書庫で何をやっているのかしら? |
| 霧雨魔理沙 | :ん? 図書館は本を読む所じゃないか。 |
| パチュリー | :ここは公共図書館じゃないのよ。 |
| 霧雨魔理沙 | :まあまあ、有効利用された方が本も喜んでるって。 :おお、何々? それとも私に外に連れて行って欲しいのか? |
| パチュリー | :……あのね。 |
| 霧雨魔理沙 | :本っていうのは、私たち共通の財産だ。図書館の目的は単なる知識の収蔵庫じゃないんだぜ? :広くこの叡智の恩恵を行き渡らせる、それが図書館の理想的な在り方だ。 |
| パチュリー | :恩恵って、それを受けるのは貴女だけでしょう。 |
| 霧雨魔理沙 | :人間は寿命が短いし、優先順位が先だろう? 取り敢えず、この辺りには魔女で人間なのは私だけだから、私が読んで、後々お前さんが回収すれば全然OKじゃないか。 |
| パチュリー | :……………。 :ああ言えばこう言う。 |
| 霧雨魔理沙 | :私の魔法知識が増えれば、異変もすぐに解決されるしな。良いことずくめじゃないか。 :鬼やら天人やらに大きな顔をされなくても済むし、パチュリーとっても喜ばしいことだろう? |
| パチュリー | :―――――。 :Libenter homines id quod volunt credunt. |
| 霧雨魔理沙 | :何だって? |
| パチュリー | :……リーベンテル・ホミネース・イド・クォド・ウォルント・クレードゥント :人は自ら望むことを喜んで信じる……。全くだわ。 |
| 霧雨魔理沙 | :あー、それ、どっかで聞いたことがあるな。あれ、誰かに言われたんだっけか? |
| パチュリー | :……これはユリウス・カエサルの言葉よ。ジュリアス・シーザーの方が通りがよいかしら。 |
| 霧雨魔理沙 | :古代ローマの偉い人、だよな。 |
| パチュリー | :そうね。急速に膨張したが故に混乱していたローマ社会の再建を目指した人物よ。……志半ばに倒れたのだけれど。 :そんなカエサルがガリアでの戦役を記録した文章、『ガリア戦記』の中に現れる言葉ね。 :「およそ人は自分の望みを勝手に信じてしまう」 :……この言葉は、元々は人間の心理を利用した戦略に関しての言葉なのだけど、人の本質を鋭く突いた言葉なので、今ではより普遍的な価値がある言葉として知られているわ。 :「人間なら誰にでも、すべてが見えるわけではない。多くの人は、自分が見たいと欲することしか見ていない」、「人間は、見たいと思う現実しか見ない」(※注2) :此処の言葉では色々な言い回しがあるようだけど、本質は変わらないでしょ。 |
| 霧雨魔理沙 | :う〜む。確かにな。望まない真実を直視するのは勇気が必要だな。 :でもな、そもそも自分に都合の良いばっかりの世界なんて面白くない気がするがなぁ。困難があるからこそ達成感もあるし、やる気も起きると思うんだけどなぁ。 |
| パチュリー | :……あなたはちょっと特殊だわ。 :そうね……。歴史を振り返ってみると、悪い方向へ悪い方向へと自ら進んで行くように見えることが良くあるの。後世から見れば、ちょっと考えれば分かるはずのことが、不思議なことに当事者には分からない。充分な知性も経験も持っている筈の人物が破滅して行くの。 |
| 霧雨魔理沙 | :その原因が、この考え方だと? |
| パチュリー | :そう。そうしたことの多くは、この見たいと思う現実を進んで信じてしまうという認識の方法、否、人間の性と言っても良いのだけれど……、それがが原因なのでしょうね。 |
| 霧雨魔理沙 | :……………。 :なんだか悲しいものだな。 |
| パチュリー | :何れにせよ、人間を良く理解していたからこその言葉ね。 :でもね、先見性も鋭い知性も、カエサルの人間性によって生かされたのね。……単に優れた人物というだけでは、多くの人々を導くことはできないもの。 |
| 霧雨魔理沙 | :でもローマを民主主義政体から帝政へと変えてしまった人物じゃないのか? :独裁者というイメージもあるけどなぁ。 |
| パチュリー | :帝政は当時のローマに最も相応しい政体として選択されたもの。個人の野望という観点からのみ、それを評価する訳にはいかないわ。 :それにね、カエサルは人間同士の誓約を重んじたの。それは一神教のような神と個人との契約ではない。人と人との信頼に基づく約束ね。 :それだけではないわ。カエサルが政策の基本としてあげたのは寛容(クレメンティア)だった。強い感情、特に憎しみの力は強い。寛容こそが文化や習慣の異なる人々の間に調和をもたらすことができる、そう彼は考えていたの。だからカエサルの奉納した神殿は「寛容の神」に捧げられたわ。彼は人間を信じていたのね……。 :……だけど、彼が暗殺された後、その後を継いだオクタウィアヌスが神殿を捧げたのは復讐の神だった。カエサルの思いは同時代の人間たちには理解されなかったのね。彼が後継者として見込んだオクタウィアヌスでさえも。 :やはり、多くの人は見たいと思う現実しか見なかった……。。 |
| 霧雨魔理沙 | :……………。 |
| パチュリー | :そうそう、ローマに国立図書館を設立したのもカエサルだったの。 :その仕事を任されたのは、カエサルに敵対したポンペイウスの将軍でもあったテレンティウス・ヴァッロ。彼は敵を罰したり処刑したりしたことはほとんど無かった、……例え許した者が再び彼に敵対したとしてもね。それが彼の信念だったのよ。彼の最期を思うと、複雑だけれど。カエサルはこう言っているわ。 「わたしが自由にした人々が再びわたしに剣を向けることになるとしても、そのようなことには心をわずらわせたくない。何ものにもましてわたしが自分自身に課しているのは、自らの考えに忠実に生きることである。だから他の人々も、そうあって当然と思っている」(※3) |
| 霧雨魔理沙 | :ふふふ。私は知ってるぜ。戦争が強いだけじゃない……。カエサルはもてまくりのプレイボーイだったんだよな。しかも相手に絶対に嫌われたり恨まれたりしなかったという。 :うんうん、人間が“デキテル”と違うよなあ。 |
| パチュリー | :う、ぐ。 |
| 霧雨魔理沙 | :そうそう、確か借りまくりの借金王でもあったんだよなぁ。何だか凄く親しみが湧いてきたぜ。 |
| パチュリー | :うう、なんだか、逆効果だったような……。 |
| ※脚注 1:この文章は本来昨年9月用だったので、ここの元々の台詞は「読書の秋だぜ〜」でした。 2:塩野七生の『ユリウス・カエサル −ルビコン以前− ローマ人の物語V』には、この言葉は『内乱記』にあると記されています。 3:塩野七生『ユリウス・カエサル −ルビコン以後− ローマ人の物語V』新潮社1996,p.337より。 |
参考文献
・塩野七生『ユリウス・カエサル −ルビコン以前− ローマ人の物語V』新潮社1995
・塩野七生『ユリウス・カエサル −ルビコン以後− ローマ人の物語V』新潮社1996
・ユリウス・カエサル(近山金次訳)『ガリア戦記』岩波文庫1942
・柳沼重剛編『ギリシア・ローマ名言集』岩波文庫2003