![]()
○平成21年12月
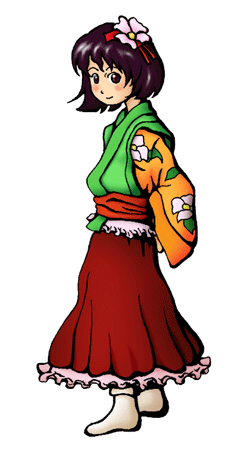 |
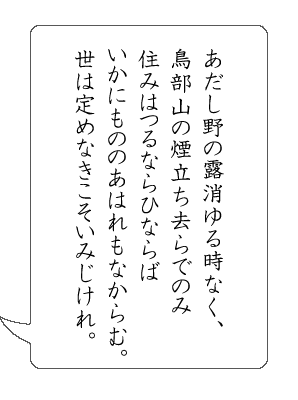 |
あだし野の露消ゆる時なく、
鳥部山の煙立ち去らでのみ住みはつるならひならば、
いかにもののあはれもなからむ。
世は定めなきこそいみじけれ。
兼好法師『徒然草』(第七段)(※註1,註2)
| (意訳) |
| あたかも化野の墓所の露が消えゆくように命は儚く、鳥部山に火葬の煙が絶え間なく立ち上るように人は皆死んでゆくものだ。 ところがもし、そうあるべき露が消えないように、また煙が溶けてゆくことなく永遠に漂い続けるように、人が死ぬことも無く生き続ける慣わしであったとしたら、情緒は失われ、何事かに深く感動することさえもなくなってしまうであろう。 やはり人生とは儚い幻のようなものであって、予測不能でうつろいゆくからこそこの世界は素晴らしいのだ。 |
 |
 |
| 稗田阿求 | 上白沢慧音 |
| 稗田阿求 | :あ、わざわざお呼び立てして申し訳ありません。 |
| 上白沢慧音 | :いやいや稗田の、私も授業で使う史料についていつも世話になっているからな。しかし稗田の、そなたなら私に相談することなど無いのではないか? |
| 稗田阿求 | :いいえ、そんなことはありません。私の能力は限られたものですし、やっぱり異なる視点からの見解というのも必要だと思うのです。 |
| 上白沢慧音 | :そうか。私はそなたとの議論は楽しいので良いのだがな。 |
(少女議論中) |
|
| 稗田阿求 | :なるほど、里の外ではそんなこともあったのですね。 :……あれ、どうかされましたか? |
| 上白沢慧音 | :何だかそなたが随分変わったように思えてな。 |
| 稗田阿求 | :えっへん。そんなに綺麗になりましたか? |
| 上白沢慧音 | :ははは……。まあ、そんな所だ。 |
| 稗田阿求 | :えーと、小さい頃はそんなにかわいげが無い子供でしたでしょうか。 |
| 上白沢慧音 | :いや、そうではなくてだな。……何と言うか、もっと醒めていたと言うか、諦観を醸し出していたように思うのだが。 |
| 稗田阿求 | :……最近は楽しいのです。こうして調べ物をすることも、幻想郷縁起の改訂をすることも。 |
| 上白沢慧音 | :そうか、それは重畳。 |
| 稗田阿求 | :ええ。これまで私は埃を被った史料と限られた客人、そして己の持つ僅かな経験の中だけで生きてきました。過去の御阿礼の子らの残した記録を見ると、これまでもずっとそうだったようです。 :でも、最近になって改めて私は知ることが出来たのです。この世界が広く、そして素晴らしいことに。知らないことが何と多かったことか……。 :霊夢さんは里の人間では知り得ない、様々な話を聞かせてくれました。魔理沙さんは未知の場所へと私を連れて行ってくれました。そして慧音さん、貴女もです。 :みなさんを通じて、私は沢山の人や妖怪と出会い、貴重な体験をすることができました。 :―――――。 :そして私は初めて本当に理解できたのです。幻想郷はこんなにも素晴らしい所なのだと。今なら、幻想郷縁起をまとめる意義がはっきりと解ります。 :おかげで改訂すべき内容がどっさり溜まってしまいましたけれどね。ふふふ。 |
| 上白沢慧音 | :幻想郷縁起を書き続ける意義、か。 |
| 稗田阿求 | :はい。私には先代までの記憶はありません。ただ縁起に関することのみが受け継がれるのです。 :ですから、初めはこんな私の運命を恨んだこともありました。ただ縁起というモノの為にだけの存在なのかと。私の人生には選択肢というものが無い。短く、決められた軌道の上をひたすら走るのみ。そう思っていた時もありました。 :でも今は違います。この世界に住む者たちがより良く生きてゆく為に、僅かではあれ縁起が役に立つと思えるのです。何より、執筆の過程でこうして皆さんと話すことが楽しいのです。 :たとえ阿求としての私の命が尽きようと、この幻想郷縁起がある限り、私は幻想郷と共にあり、そして幻想郷を見守り続けることができる。……今ではそう思えるのです。 :……たとえ、たとえ私が皆を忘れてしまっても。……皆が私を忘れてしまっても。 |
| 上白沢慧音 | :阿求……。私たちはそなたを忘れはしない。特別な能力など無くとも、こうして共に過ごした時間の記憶は誰にも消せはしない。 |
| 稗田阿求 | :ああ、すみません。役目を完遂するためとはいえ、転生が約束されている自分が、こんなことを言うのは贅沢かもしれませんね。 |
| 上白沢慧音 | :……………。道半ばで倒れるのは辛いことだ。だがこの世に生まれてきた者は皆、多かれ少なかれ道半ばにて果てる運命なのだ。 :むしろ永遠に巡る時の輪こそ最大の苦しみかもしれぬ。 |
| 稗田阿求 | :そうですね。ですから私は、阿求としての人生が一度きりであることに今では感謝しています。もっとも、皆さんとこうして時間を過ごしていると、この時間がずっと続けば良いと思うことはありますけれど。 |
| 上白沢慧音 | :「存命のよろこび、日日に楽しまざらむや」、か。 |
| 稗田阿求 | :ええ、でもやっぱり思うのです。私もこうして限られた一生を生きているからこそ、充実した時間を過ごせているのだと。 :「あだし野(註3)の露消ゆる時なく、鳥部山(註4)の煙立ち去らでのみ住みはつるならひならば、いかにもののあはれもなからむ」 |
| 上白沢慧音 | :「世は定めなきこそいみじけれ」 :徒然草だな。 |
| 稗田阿求 | :ええ、そうです。それに短い短いと言っても、生き物の中にはもっと寿命が短いものもいます。そんなことを思えば、軽々しく不幸だなんて思えません。 :「命あるものを見るに、人ばかり久しきはなし。かげろふの夕べを待ち(註5)、夏の蝉の春秋を知らぬ(註6)もあるぞかし」と続いていますもの。 |
| 上白沢慧音 | :そして「つくづくと一年をくらすほどだにも、こよなうのどけしや。あかず惜しと思はば、千年を過ぐすとも、一夜の夢のここちこそせめ」(註7)とな。 |
| 稗田阿求 | :はい。 :だから、慧音さんも変に気を使わずに、時に厳しく、時に楽しくいつものように接して下さいね。 :………その日が来るまで。 |
| 上白沢慧音 | :ああ、勿論だよ。 |
幻想郷の人間の里、暮れの夜は更けてゆく 二人の話題はいつまでも尽きない……。 |
| ※脚注 | |
| 註1: | 『徒然草』は鎌倉時代後期の随筆。作者は兼好法師(卜部兼好)。 『枕草子』、『方丈記』と並び日本三大随筆の一とされる。序段を含め、全二百四十四段からなる。元弘元年(西暦1331年)兼好四十九歳の頃に書かれたらしい。書名は冒頭の「つれづれなるままに」から採られている。 後年教訓の書、あるいは教養の書として広く読まれるようになり、江戸時代には国民的常識書とまで見なされるようになった。江戸期の文化に影響を与え、また注釈書の類も多い。 隠者文学の代表の一つ。無常観に基づく仏教思想を中心に、無為自然を説く老荘思想を加えたものを根本思想としている。一方で兼好には平安朝の文化への憧れがあり、古典的な価値観を説く段も多い。内容は人生観や処世訓から、逸話や珍聞奇談、趣味論まで多岐広範にわたる。そして、何れの場合にもにも鋭い批判 精神をうかがうことができる。 本文の文体は和漢混淆文と和文の混在である。また兼好の好みから平安朝の文体に近いと言われる。兼好は平安朝文学の伝統を受け継ぎつつ、漢籍・仏典に加えて説話集の表現、政治・有職故実に関する諸文献の記録性を取り入れることで、簡潔かつ風雅な文体を作り上げたという。 また、未完成の美、あるいは推移の美などが扱われていると見ることができる。そのことから、『徒然草』を室町以降の中世文化を予告するものとして位置づけることもできる。 |
| 註2: | 兼好法師(卜部兼好)、『徒然草』の作者。卜部氏のうち吉田家系統に属することから、近世以降吉田兼好と通称される。卜部家は代々神祇官を勤めた。生没年には諸説あるが、弘安六年(西暦1283年)に卜部兼顕の三男として生まれ、文和元年(西暦1352年)以降に亡くなったという。三十歳頃に出家し、隠遁者として生きた。和歌を良くし、当代の和歌四天王(他の三人は頓阿、浄弁、慶運)と評された。歌集に「兼好法師集」がある。 兼好法師の生きた時代は、鎌倉幕府の末期から南北朝時代に当たる。まさに動乱の時代だったと言える。彼が生まれたのは弘安の役(西暦1281年)の直後であり、『徒然草』を成立させた頃(西暦1331年前後)は丁度元弘の変(西暦1331年)に始まる鎌倉幕府の滅亡期に当たる。すなわち正慶二年/元弘三年(西暦1333年)には幕府が滅亡し、有名な二条河原の落書の事件は翌1334年に起きている。その後も政情は安定せず、南北朝の争い(湊川の戦は西暦1336年)が続いた。そして兼好法師の亡くなった時期も足利氏の内紛である、観応の擾乱(観応年間、西暦1350〜52年頃)のただ中だった。 無常観を基盤に置く『徒然草』の成り立ちも、こうした時代背景を抜きにしては語ることが出来ない。 |
| 註3: | 化野(あだしの):京都愛宕山の麓(京都市右京区嵯峨野)にあった墓地。 |
| 註4: | 鳥部山(とりべやま):京都清水寺(京都市東山区清水)の下にあった火葬場。 |
| 註5: | 『淮南子』の「説林訓」に「蜉蝣(ふゆう=カゲロウ)は朝(あした)に生まれて暮に死ぬ。而してその楽しみを尽くす」とある。カゲロウは儚い命の代表例。カゲロウは朝生まれて夕刻には死んでしまうが、それでもなお生きる楽しみを尽くすのである。 |
| 註6: | 『荘子』の「適遥遊」に「朝菌(ちょうきん=朝生えて夕刻に枯れてしまうキノコ、あるいはカゲロウ、むくげ)は晦朔(さく=太陰暦における月の第一日)を知らず、[虫恵]蛄(けいこ=セミ)は春秋を知らず」とある。 |
| 註7: | 『徒然草』第七段の前半の原文は以下の通り。 「あだし野の露消ゆる時なく、鳥部山の煙立ち去らでのみ住みはつるならひならば、いかにもののあはれもなからむ世は定めなきこそいみじけれ。命あるものを見るに、人ばかり久しきはなし。かげろふの夕べを待ち、夏の蝉の春秋を知らぬもあるぞかし。つくづくと一年をくらすほどだにも、こよなうのどけしや。あかず惜しと思はば、千年を過ぐすとも、一夜の夢のここちこそせめ」 以下意訳。 「あたかも化野の墓所の露が消えゆくように命は儚く、鳥部山に火葬の煙が絶え間なく立ち上るように人は皆死んでゆくものだ。ところがもし、そうあるべき露が消えないように、また煙が溶けてゆくことなく永遠に漂い続けるように、人が死ぬことも無く生き続ける慣わしであったとしたら、情緒は失われ、何事かに深く感動することさえもなくなってしまうであろう。 やはり人生とは儚い幻のようなものであって、予測不能でうつろいゆくからこそこの世界は素晴らしいのだ。 この世に生きる生物を見回してみると、人間だけがだらだらと長生きをしている。朝生まれたばかりのカゲロウは日暮を待って死に、夏を生きるセミは春も秋も知らないで死んでしまう。そう考えると、のんびりと日々を過ごすことができるということさえも、実に暢気なことだと思えてくる。いつまでも充足すること無く不満を抱え、死にたくないなどと思っていれば、たとえ千年生きていても、その人生はたった一夜の夢となんら変わらない儚い気持ちがするだろう」 |
参考文献
・吉田兼好(西尾実、 安良岡康作校注)『徒然草』岩波文庫1985
・鴨長明(佐竹昭広校注)/吉田兼好(久保田淳校注)『方丈記・徒然草』(『新日本古典文学大系39』
岩波書店1989)
・鴨長明(神田秀夫校注解・訳)/吉田兼好(永積安明校注・訳)/道元述 ・懐奘編(安良岡康作校注・訳)
/親鸞述・唯圓編(安良岡康作校注・訳)『方丈記・徒然草・正法眼蔵随聞記・歎異抄』(『新編日本古典
文学全集44』小学館1995)
ほか辞典・便覧類