![]()
○平成18年8月
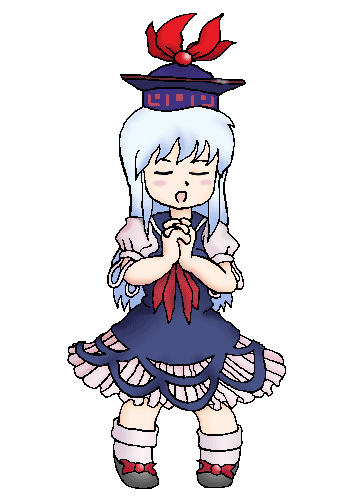 |
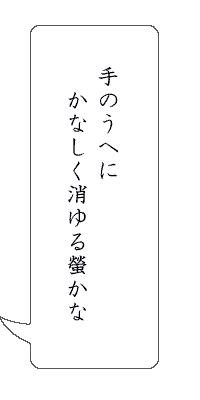 |
手のうへに かなしく消ゆる 螢かな
向井去来『去来発句集』
 |
 |
| 上白沢慧音 | リグル・ナイトバグ |
| 上白沢慧音 | :……………かなしく消ゆる螢かな。 :これは亡き妹への追悼の句だな。作者は向井去来、松尾芭蕉の高弟だ。彼の句集『去来発句集』及び山本荷兮篇の『阿羅野』(『曠野』とも)にあるものだ。『去来発句集』の前書きには「妹千子(ちね)身まかりけるに」、『阿羅野』には「いもうとの追善に」とある。かけがえのない兄妹だったのだろうな………。 |
| リグル | :えー、暗ーい。螢が消えちゃう言葉なんて縁起でもなーい。 |
| 上白沢慧音 | :騒がしいな。ああ、お化け螢か。 :全く何を言っているのだか。螢は儚いもの。だからこそ美しく、皆にも好かれているのだぞ。螢二十日に蝉三日などとも言うだろう。まあ、蝉よりはましということだ。 |
| リグル | :私は儚くなんか無いよ。光だって眩しいくらいに、こうやって………。 |
| 上白沢慧音 | :そなたは化け螢だからな。でも所詮は一面ボスだから。 |
| リグル | :そうそう、「兄ちゃん、螢何故すぐ死んでしまうん?」って、うぎゃあああああ。 :――――――――――――。 |
| 上白沢慧音 | :―――――。静かになったかな? :向井去来(慶安四年〜宝永元年)(西暦1651〜1704年)は蕉門十哲に数えられる、芭蕉の弟子の一人だ。長崎出身で京都に住んでいた。彼の一家には学者や俳人が多く、彼自身も各種の武芸学芸、特に天文・暦数を修め、一時は堂上家に仕えていたという。高潔篤実な人格者であり、多くの人に慕われたそうだ。作風も師の芭蕉の教えに忠実だとされているな。今も残る彼の嵯峨の別荘、落柿舎へは芭蕉が来訪したこともある。元禄四年(西暦1691年)、野沢凡兆と共に蕉風俳諧の最高峰『猿蓑』の編纂を行ったことでも有名だろう。 :妹千子も俳諧を嗜んでいたようだ。貞享三年八月、彼は伊勢へと旅行しているが、そのとき千子も同道している。商家の清水藤右衛門に嫁し、一子をもうけたが、元禄元年(西暦1688年)五月十五日に死去したのだ。まだ二十代だったとも言う。 |
| リグル | :えー、暗ーい。………あれ、何の話をしていたんだっけ? |
| 上白沢慧音 | :……………。 :去来の句は千子の辞世の句に唱和したものだ。彼女の句は「もえやすく又消えやすき螢かな」だ。 :大切だった妹を掌中の儚い螢に喩えた句。………深い悲しみが伝わってくる句だな。 :因みに、彼女の死に対し、芭蕉も「なき人の小袖も今や土用干」の句を贈っている。 |
| リグル | :湿っぽいなあ、もう。 :でも、螢は和歌やら俳句やら、文学にたくさん取り上げられているよねー。 |
| 上白沢慧音 | :そう、儚さを象徴するばかりでなく、静かに燃える思い、恋の炎の喩えとしても良く用いられているな。加えて自然の持つ生命力の象徴でもあるのだ。 :文学だけではない。我が国を含めた東洋では螢に関する伝説は数多いのだ。 :まあ、西洋でも様々な出来事を、その光り方で予告するなどと伝えられているがな。 |
| リグル | :ほーたーるのひーかーり、まどのゆーきー。 :でもね、ただの螢じゃあ何万匹集めても本は読めないよ。 :私みたいに力を持ってないとね。人間を惑わす光!、ほらほら、まるで地上の星みたいに………。―――あっ、別に人間に危害を加え………、きゅー。 :――――――――――――。 |
| 上白沢慧音 | :…………………。 :「蛍雪」は苦学の喩えだな。そしてスコットランドの送別歌“Auld Long Syne”の旋律を用いた「蛍の光」は別れの歌の定番になっている。 :螢の伝説についてだが、有名なのは源三位頼政が宇治で平家に敗れ、螢となったというものだろう。螢合戦もこれに関わって語られるな。小泉八雲『骨董』内の「蛍」には様々な文学に登場する螢や伝承、当時の風俗などが記されているぞ。 :かつては螢狩りが夏の風物詩だったが、今ではそれも珍しくなってしまったな。 |
| リグル | :暗ーい。大丈ー夫だって。幻想郷では私がいるし。むしろ螢は増えてるよ。 :ん、あれ?、何でこんな話をしてるんだっけ?? |
| 上白沢慧音 | :…………………………。 :ま、東洋では主に光る成虫、それも飛翔する雄ホタルが注目された訳だ。だから普通に螢と言った場合は、この光りながら飛ぶ虫を指す訳だな。だが、西洋では飛びまわる雄の出す光が弱かった為か、地上にいる幼虫や雌の方が注目されたのだ。西洋の種は地上の雌が強く光るのだ。 :例えば英語で螢を表す語には“firefly”と“glowworm”とがあるのだが、歴史的に見てみると、glowworm系の名が本来の様だ。そしてこの“glowworm”とは「光る蛆」の意味なんだ。 |
| リグル | :うんうん、こっちの主要な種類、ゲンジボタルやヘイケボタルでは成虫が強く光るけどね。でも一応水中の幼虫やら地上の雌も光るよ。自分で言うのも何だけど、幼虫やら雌やらは結構キモいよ?大体、光る蟲なんて、大概はキモイの。 |
| 上白沢慧音 | :そうだな、我が国で言う樹上で毛虫やヤスデが光るという話は、実際にはマドボタル類の幼虫のことだな。こういう地上で暮らす螢の雌や幼虫のことを、一般に土蛍(つちぼたる)と称するのだ。ん、そういえば“firebug”という言い方もあったな。 :そういえば、フランス語でホタルは“ver luisant”(ヴェール・ルイサン)、「輝く虫」という意味だ。こう言い換えるとなんだかお洒落だな。 |
| リグル | :ふーん。 :………で、何の話をしてるんだっけ?? |
| 上白沢慧音 | :(ムッ)………………………………。 :………こうしたホタルの光は化学反応なのだ。ルシフェリンという発光物質を酸化させることで発光している。この時働いている酵素をルシフェラーゼという、そして何とこの反応では熱は発生しないのだ。ルミネッセンス(冷光)というやつだな。それにしても自然の仕組みとは良くできているものだ。 |
| リグル | :えーと、あ、そうか。光る蟲はキモイという話ね。 |
| 上白沢慧音 | :……………まあ、そういえないこともないが。 |
| リグル | :(ニヤニヤ) |
| 上白沢慧音 | :??。何が嬉しいのだ? |
| リグル | :ほら、お互いキモイ同志? |
| 上白沢慧音 | :(怒) :貴様は公式、私はキモくない!!! |
| リグル | :あっちの水は甘いかな〜? :………ん〜?。あれ、人間の里のワーハクタク、こんなところで何やってるの? |
| 上白沢慧音 | :(このお馬鹿螢………) |
| リグル | :え?、何で何で〜?。何で怒っているの? |
| 上白沢慧音 | :(ゴゴゴ……………) |
| リグル | :って、ふぎゃ〜。 :――――――――――――。 |