![]()
○平成22年1月
 |
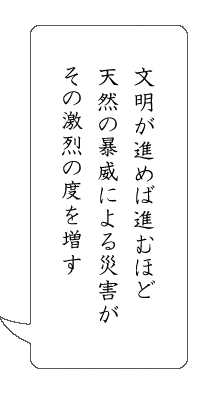 |
文明が進めば進むほど
天然の暴威による災害がその激烈の度を増す
寺田寅彦『天災と国防』(昭和13年)
 |
 |
| 河城にとり | 上白沢慧音 |
| 河城にとり | :やっほー。元気してるかな? |
| 上白沢慧音 | :おや、これは谷河童の……。今日は子供達はもう帰ってしまったぞ。 |
| 河城にとり | :んー、いいのいいの。今日は里の様子を見に来ただけだから。 :ほら、最近便利なエネルギー源が出来たでしょ。これまで構想だけだった道具がどんどん実現してるんだ。まさに技術の革命だね! |
| 上白沢慧音 | :山での技術革新については色々噂は聞いている。強力なエネルギーだそうだが平和に使われているようで何よりだ。 |
| 河城にとり | :えへへ。この頃は山の神社や里の道具屋さんを通じて人間にも色々使ってもらっているんだよ。 |
| 上白沢慧音 | :ほう。 |
| 河城にとり | :特別な力が無くたって、離れたところにいる友達と話したり、沢山の情報を瞬時に遠くへ送ったりすることだって夢じゃなくなるんだ。 :「外」から流れて来る不思議な機械だって使いこなせるようになるかもしれないんだよ。 |
| 上白沢慧音 | :……そうか。 |
| 河城にとり | :あれ、あんまり嬉しそうじゃないね。 |
| 上白沢慧音 | :いや、そんなことはない。 :便利さや日々の生活を守っているのは他ならぬ技術の力だからな。 |
| 河城にとり | :ううん。そうだよね。 |
| 上白沢慧音 | :それに技術や情報が独占されている状況は決して好ましくない。歪んだ権力を生んでしまう。 |
| 河城にとり | :んー。そうかもねぇ。 :でも、独り占めしたい気持ちは分からないでもないなぁ。それに、あんまり当たり前と思われちゃうのも癪だよねぇ。 :ほら、かつては技術を担う職人や技術そのものさえ畏れを持って受け止められていたし、信仰の対象にさえなっていたわけだし。 |
| 上白沢慧音 | :それと共に妖をも生んでしまったのだがな。……ま、何事も表裏があるということだ。 |
| 河城にとり | :そ、そうなんだ。 |
| 上白沢慧音 | :技術や知識は、特にそれが独占され隠されてしまうと、畏怖だけでなく、人々の心に歪みをもたらしもするのだ。だから知識や技は広く皆が使えるようになった方が良いのだ。たとえその神秘性が失われてもな。 :そなた達の種族なら、本当は分かっているだろうに。 |
| 河城にとり | :う、うん。私達が作っているものは、どれもみんなが幸せになるためのものだもんね。 :ま、まあちょっと位有り難がってくれた方がいい気もするけど。 |
| 上白沢慧音 | :はは。同感だな。ああ、もちろん便利になることは悪いことじゃない。社会の成熟を助け、文化的にも豊かになるきっかけともなるしな。 |
| 河城にとり | :ふっふっふ。期待しててね。外の世界に負けない便利な世界にしてみせるよ。もちろん妖怪も人間もみんなが使える形でね。 |
| 上白沢慧音 | :外の世界か……。 :うむ、どちらかというと外の世界の轍を踏まないように、とすべきかもしれないな。 |
| 河城にとり | :?? |
| 上白沢慧音 | :外の世界は今、様々な問題を抱えているようなのだが、その原因を科学技術の発展とする見方があるらしい。 |
| 河城にとり | :ええっ!? |
| 上白沢慧音 | :つまり、外の世界には科学技術に対する根強い不信があるらしいのだ。科学や技術は非人間的で冷たい、そして自らを滅ぼすものはその科学技術ではないか、とね。 :戦争、疾病、自然破壊、そして様々な社会の歪(ひず)み、何れもそれをもたらしたのは発展し過ぎた科学技術ではないかというわけだ。 :実際に悲劇をもたらした例もある。人間達は科学技術を発展させていくことによって便利さを得、同時に自分自身を破滅させることさえできる力さえも手に入れてしまったのだね。 |
| 河城にとり | :そ、それは一面的には正しい部分もあるかもしれないけど。やっぱりそれは技術を使う側の問題だよ。技術そのものは善でも悪でもないよ。 |
| 上白沢慧音 | :もちろんその通りだよ。外の世界の人間達は行き詰まり、目指すべき展望を見失ってしまっているのだろう。だから分かりやすい“敵”が求められているのだろうな。 :もっとも、これはそれまでの余りに無邪気な、そして楽観的な期待の裏返しといえないことも無いのだが。 :まあ、この幻想郷ではその点の心配は余りしていない。概念の棲み分けはきっちりしているし、全くの「悪」や「善」なんて無いことは皆分かっているのだから。 |
| 河城にとり | :そうだよねえ。でもさ、それならもっと喜んでくれてもいいんじゃないかと思うんだけど。 |
| 上白沢慧音 | :そうだな……。私が気になっているのは科学技術そのものの是非じゃないんだ。それは技術の進歩を人間が自らの進歩と勘違いしてしまうことなんだ。 :便利さはあくまで効率の問題だし、技術は文化を支えるものでこそあれ、人間の存在そのものの“進歩”には直接結びつくものではない。そう、それは大いなる勘違いなんだ。そしてそれは驕りへと、自分自身への過大評価へつながってしまう。ちょっと昔より便利になり、物事を効率よく動かすことができるようになったというだけで、現在の自分達は過去に比べて無条件に優れていると、「進歩」していると考えてしまうのだろうな。 :ふっ。決して自分達自身が偉くなった訳ではないのだがな。 :自分達がこの世界の一部であることを忘れ、まるで自然界を自由にできるかのように。 |
| 河城にとり | :あはは。まっさかぁ。私たちは大自然の表れでもあるんだよ。そんな大切なことを忘れっこな――そっか、人間たちは忘れてしまったのか……。 |
| 上白沢慧音 | :外の世界ではおそらく、な。 |
| 河城にとり | :その一方で技術に対しても不満と不信があるんだね。なんだか寂しいねぇ。 |
| 上白沢慧音 | :もちろん外の世界でも、こうした技術への過信や単純な進歩史観の危うさに気づいていた人はいた。その一人が寺田寅彦(※註1)だ。 :彼はこんな言葉を残している。 :「文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がその激烈の度を増す」 |
| 河城にとり | :寺田――ああ、「天災は忘れた頃にやってくる」(※註2)って言った人だね。 |
| 上白沢慧音 | :そうだ。社会の“進歩”は必ずしも安全性の向上につながる訳ではないということだ。 :文明が進むことで構築された精緻で巧妙な社会システムというのは、むしろ突然の災害に対しては脆いものなのだ。社会が便利になったことが逆に被害を増加させることさえもあると言う訳だな。 :それだけじゃない。この言葉は驕る人間達への警告でもあるのだよ。自然を畏れる気持ちを忘れちゃだめだ、という警告なのだ。 |
| 河城にとり | :天然の暴威、かぁ。うんうん。大丈夫、私たちは忘れてないつもりだよ。技術はこの世界の理を上手に使うこと、大自然の力をちょっぴり分けてもらうことなんだ。だから、決して私たちがその力を支配している訳じゃないってことをね。 |
| 上白沢慧音 | :ああ、この幻想郷ではまだ私達と世界との間に調和が保たれている。それはきっと大切なことなのだ。たとえどんなに技術革新が進み、社会が便利になったとしてもね。 |
| 河城にとり | :……うん。 |
| 上白沢慧音 | :ああそうだ、寺田寅彦はまた、過去に学ぶことの重要さをも理解していたのだ。「天災は――」の言葉もそうした考え方を表すものだ。 :……もっとも私の見る限り、人間達は現在もこの警告に応えられているとはとても言えなさそうだがな。 :人の一生は短い。過ちを繰り返さないと言うことは存外難しい事なのだ。 |
| 河城にとり | :ふーん。その辺は私たちと違うねぇ。生きてるスパンが違うからしょうがないのかな。 :でも、過去を振り返ることもせず、科学技術の将来にも絶望してしまった外の世界はどうなってしまうのかな。なんだか心配だね。 |
| 上白沢慧音 | :……悲しいことだが、外の世界では科学技術の未来に対する希望まで幻想となってしまったのかもしれないな。そしていつか私達の世界も――。 |
| 河城にとり | :ううん、きっと大丈夫だよ。 :技術を生み出す心はものの本質を見定めようとする心が生み出すものだもの。私たちを駆り立てるのは、そんな決して失われることのない好奇心や夢なんだ。だから私たちは希望を持って前に進んでいく。しっかりと地に足をつけて。 :たとえ外の世界がそれを失ってしまっても。 |
| 上白沢慧音 | :そうだな。幻想郷は外の世界の歴史をなぞって行くばかりではなく、異なる可能性を持っている。 :幻想郷に生きる私達はまだ失っていないのだから――己が存在への真摯な視点を、人智を超えたものへの畏れを、私達を取り巻く世界との一体感を、そしてまだ見ぬ明日への希望を。 :だから私は信じよう。“明るい未来”を。外の世界では今や失われてしまったそれを。 |
| ※脚注 | |
| 註1: | 寺田寅彦(1878〜1935)は日本の物理学者、随筆家。夏目漱石の友人であり、漱石の作品の登場人物のモデルになったと言われている。 吉村冬彦などのペンネームを用いた随筆家としても著名。当時としては珍しい仮説提示型の研究者であり、原子物理学、地球物理学など多彩な研究活動を行った。地震やその防災対策に取り組んだことでも知られる。 詳しくは過去の御言葉「天災は忘れた頃にやってくる」の解説を参照のこと。 |
| 註2: | 寺田寅彦による警句として知られる。寺田の弟子で雪の結晶の研究で知られる中谷宇吉郎が紹介し流布したもの。註1と同様、詳しくは過去の御言葉「天災は忘れた頃にやってくる」の解説を参照のこと。 |
参考文献
・寺田寅彦『天災と国防』岩波書店1938
・西尾光一校注『鈴木三重吉・森田草平・寺田寅彦・内田百間・中勘助集』筑摩書房1971
(『現代日本文学大系』29)
・角川源義編『寺田寅彦』角川書店1961