0.はじめに
1.境目に潜む妖怪
2.出雲の八重垣
3.色鮮やかな縁
4.高貴なる色彩
5.怪異を招く色
6.神隠しの主犯
6-1.黄昏の迷い子
6-2.幻の楽園
6-3.九ツ谺の向こうに
7.覗き見るモノ
8.異界への入口
9.彼岸への架け橋
10.境界の護持者
終.境の殺戮
付.参考文献
さて、前章では主に高貴な色としての紫について述べてみました。が、ムラサキにはそれだけでない複雑な性格を持っているようです。紫色は、赤や青などのはっきりとした原色とは異なる中間色であることから、曖昧な不可思議な色彩としてもとらえられていた節があります。すなわち、怪談・妖怪で語られる色彩に、しばしば紫色が登場するのです。
紫色が登場する現代の怪談の代表的なものとして、「紫鏡(ムラサキカガミ)」と「紫婆(ムラサババア)」を挙げることができます。これらはしばしば子供達の間で語られ、所謂「学校の怪談」として括られる種類のものです。一種の世間話であり、現代伝説(都市伝説)の一部と言うこともできるでしょう。

***
「紫鏡」の話は、この言葉(ムラサキカガミ)を大人(大概二十歳)までに忘れないと不幸になるというものです。実際のところ、不幸を招く言葉自体にはヴァリエーションがあり、他には紫の亀や、赤い沼、イルカ島と数多くあります。また、子供の間で語られる怪談に良くあるように、様々な救済手段も同時に語られます。それは、横断歩道の白い部分を踏むとか、“水色の鏡”や“白い水晶玉”などの言葉を言うなどです。多くの場合、不幸の言葉にも救済の言葉にも紫や赤、黄、白といった色彩が取り込まれています。色の持つ属性は子供でも分かり易いものであるからかもしれません。
この怪談は割と近年(1970年代後半?)になってから語られるようになったものだそうです。ところで、紫鏡の由来譚として、しばしば手鏡を絵の具で紫に塗ってしまった女の子の話が語られます。しかし、これはおそらく紫鏡の怪談が先にあり、後付として誕生した話だと思われます。
なお、鏡の持つ神秘性については今回は余り触れません。魔除けとなるとともに魔を招く呪具ともなる事、異界との接点となる事くらいを認識していれば十分でしょう。
***
一方「紫婆」は学校の便所に現れる妖怪です。民俗学者常光徹が東京都で採取した話に登場します。女子トイレに現れる正体不明のもので、紫色の老婆とも言います。あるいは、服と持っている風呂敷の色が紫色なのだとも。人を驚かせるばかりでなく、肝を取るという話もあります。紫色の物を持って「ムラサキ、ムラサキ」と唱えると退散させることができるという話もあります。この噂は近隣の学校に広がり、低学年の学級ではパニック状態になった所もあるそうです。常光はこの妖怪が初めて現れたのは1979年頃ではないかと推測しています。これも比較的新しい怪異譚のようです(なお、赤マントの噂は戦前からあるらしい)。この「紫婆」は神出鬼没で、トイレの鏡の中から出てきたり、破れた壁の穴から出てきたりするらしい。あら、ちょっと似てるかも?
加えて、これらの怪談との関わりは分かりませんが、紫肝という俗信があります。これは五月五日生まれの男子と三月三日生まれの女子の内蔵は紫色で、これを河童が好んで抜き取って喰うというものです。河童は便所(厠)や手の怪との関わりが深く、何らかの影響があるのかもしれません。
なお、学校の怪談に代表される子供達の怪異譚には、○○時ババアなど、老婆の姿で登場する怪異が数多く語り伝えられています。
それでは、何故トイレ(便所)を舞台に多くの妖怪話・怪談が語られるのでしょうか。皆さんも、「赤い紙青い紙」とか、「赤いはんてん」とかトイレを舞台にした怪異譚をご存じだと思います。それは便所が一種の非日常的空間であるからと考えられます。孤立して隠すべき行為を行うということや、あちこちに隙間のある不完全に隔離された空間、知らずに受け継いだ伝統的な感情などが不安な精神状態をもたらすのでしょう。これは一見近代的で衛生的な明るいトイレでも変わらないことです。また、民俗学者の宮田登は便所の境界性に関して「この世とあの世の霊魂の出入り口というとらえ方があったのではないか」(『神の民族誌』)と述べています。
こうしてトイレ(便所)には様々な異類のものが跋扈することになったのです。例えば、江戸時代にも、厠で神隠しに遭った話が伝えられていたそうです。
同じように、トイレに現れる手の怪異については、古くから民間に伝えられてきた厠から出る手(正体は河童の場合が多い、また「加牟波理入道」と「かいなで」とかいう名で語られることもある)の要素を引いているとも考えられます。
しかし、それらとの直接的な繋がりを考えるより、一部の要素を借りて新たなハナシを構成したとしたほうが良いかもしれません。今日の話にはその手の正体たる河童や川獺の影を見つけることはできません。そしてむしろそうした非文脈性が怪談の不気味さを増しているとも言えましょう。
さらに、色について考えてみると、古い厠の神に紫姑神と呼ばれる女神があるのですが、しばしばトイレの怪異に紫色が登場するのは、この女神(紫姑神)の記憶を受け継いでいるという説もあります。ただ、やはり私は、紫姑神からの直系として現代の怪異譚が有るわけではなく、何か人間の心理に共通のモティーフ(紫色・手等)が受け継がれたのだと考えています。例えば、紫色という色は怪異と結びつきやすいと考える心情が、昔から受け継がれたのではないでしょうか。
***
上記してきたように紫色と怪異とが結びつけられた要因としては、どのようなことが考えられるのでしょうか。
まずは、紫色が一種曖昧な色であるということが挙げられるでしょう。赤や青といった原色に比べ、中間色の紫色には曖昧なイメージが与えられます。曖昧さは不安さに繋がります。怪異は曖昧な色彩、即ち境界の色をまとって現れるのかもしれません。また、紫色に夕暮れ時の空の色のイメージがあることも、要素として考えられます。夕暮れの誰彼時は妖怪の支配する時間ですから。
さらに、本稿の目的からは外れるかもしれませんが、「ムラサキ」という読み方もその要因かもしれません。「アカ」、「アオ」といった比較的単純な音に対し、「ムラサキ」という響きにはなにやら不思議な気分をもたらすものがあるような気がします。
***
参考として、日本や中国などの東洋を離れて、西洋の色彩感覚にも軽く触れておきましょう。紫色は西洋では、キリスト受難に関わる色として、負のイメージを持たれていると言います。例えば受難節では、教会にある様々なものに紫色の衣が懸けられ、司祭の着る祭服も紫色です。西洋ではかつて、紫色が喪服の色として用いられたこともありました。
***
ところで、「紫婆」の噂が囁かれている中で、その正体は「掃除のおばさんが紫色のゴム手袋を女子トイレの扉に挟んだまま忘れてしまったもの」だという情報も語られていたそうです。しかし、このことについて情報源を辿ることはできず、話の信憑性を確かめることはできなかったそうです。
つまり、一見合理的かつ客観的なような情報なのですが、実際の所どこまでが本当かわからない「噂」であった可能性が高いのです。つまりこの「合理的説明」は怪異騒動の後から新たに生じたもう一つのハナシ(対抗神話)であったと思われるのです。
このように、噂には別の噂を「合理的」に説明付けようとする、もっともらしい物もあるのです。例えば、先に少し触れましたが、戦前の赤マント騒動について、それは陸軍が噂の伝播速度を計測するために流した意図的なものだったという説(噂?)があります。これも先の紫婆の正体説明と同じような物(一種のハナシ)だと思います。
学校の怪談・現代伝説(都市伝説)についての図書としては、次の四冊が参考となると思います。常光徹『学校の怪談』(ミネルヴァ書房1993),池田香代子ほか編著『ピアスの白い糸』(白水社1994),近藤雅樹ほか編著『魔女の伝言板』(白水社1995),池田香代子ほか編著『走るお婆さん』(白水社1996)。
***
6−1.黄昏の迷い子
本章では彼女に与えられた属性の一つ、「神隠しの主犯」について、考えてみたいと思います。
それでは「神隠し」とはいかなる現象を指すのでしょうか。
一般には「神隠し」とは、ある日突然人が日常世界から消え失せてしまうことを指します。かつての民俗社会では、これを超自然的存在にとって異界へと誘われ、「隠された」と考えたのです。
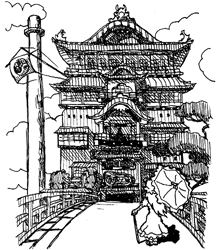
一方、『山の人生』は「山に埋もれたる人生ある事」に始まる情感溢れる興味深い論考ですが、「今も少年の往々にして神に隠さるゝ事」、「殊に若き女の屡隠されし事」などの章があり、神隠しの考察は山人等と並ぶ重要な位置を占めています。また、民話研究で知られる松谷みよ子編の『現代民話考』の第一巻「河童・天狗・神かくし」にも多くの神隠し談が採られています。
以下ではこれらの書籍に掲載された様々な神隠し譚や解説、そして神隠しを扱った小松和彦の『神隠し』(文庫版では『神隠しと日本人』と改題)を元に考えてゆきたいと思います。
まず、こうした例を見てゆくと、神隠し譚には幾つかの共通点が見えてきます。代表的なものには、子供や女性が多く遭遇するというものがあります。また、柳田は時刻や季節にもきまりがあると述べていますが、これには異論もあるようです。さらに、「返せ、戻せ」と大勢で呼ぶ光景は、こうした神隠しに遭った子供を捜す際の典型であるわけですが、東京など都市部でも戦前までは見られたと言います。
なお、こうした呼びかけが行われるたのは、この行為が子供の“捜索”ではなく“奪還”であったからだと柳田は述べています。また、松谷みよ子編『現代民話考』にも、捜索者が神隠しに遭うのを恐れて体をお互い縄で繋ぎ、点呼をしつつ行方不明者を捜すという風景が記載されており、神隠しへの畏れの深さをうかがうことができます。
蛇足となりますが、ここで鉦太鼓など鳴り物の意味についても言及しておきたいと思います。鉦や太鼓などの音は、行方不明者への信号としての現実的な意味の他に、神隠しを引き起こすと考えられた雑小な神霊への交信の手段であったと考えられます。また、普通の手段では手の届かない異界へもこうした音は届くと考えられていました。神降ろしや悪霊祓いの儀式に様々な楽器が使用されるのもそのためです。音を悪しき神霊を攻撃する呪力を持った一種の武器と捉える伝承も残されています。
音は彼岸と此岸との境界を越える事ができると考えられていたのです。
***
神隠しに遭ったと判断されたという事は、失踪の原因は現実世界にはなく、人ならざるモノにあると判断したわけです。それによって様々な現実の問題は生死も含めて隠されてしまうことになります。つまり、「神隠し」にあった者は、事故や事件に巻き込まれたり、家出したりしたのではなく、意図せずに何かに「隠された」のであり、どこか異世界で生きていると考えたのです。ですから、神隠しに遭ったと判断されるということは、行方不明者が生きている可能性があるということであり、それによって悲しみを和らげるばかりか、いつか戻ってくるかもしれないという期待を持ち続けることができたのです。
現実には、こうして姿を消してしまう人々は、不慮の事故でなければ、何らかの束縛から逃れるための覚悟の家出、あるいは自殺をしたものと考えられます。かつてはこうした出来事に対して、「神隠し」という柔らかく曖昧な表現を取ったと考えられるのです。そのため、万一年月を経て再び現れた人があっても、これを受け入れることが可能となったのだと考えられるのです。そうした点では「神隠し」とは優しい言葉・民俗知であったと言うことができましょう。その一方で、こうした抑圧から逃れた人をも、謂わば生贄にして、イエやムラなどの共同体の帰属意識を高める装置としてしまうといった点があることも忘れてはならないでしょう。
したがって、神隠しと判断することは、生存の可能性を残すという面があるとはいえ、通常は二度とは戻らないという諦めを強いるものでもあったのでしょう。こうしたことを思い合わせれば、鉦太鼓による儀式的な探し方は葬送を思わせ、まさに「諦めのための儀式」だったのでしょう。
***
一方、神隠しには前述した長期間にわたる、時には永久に戻ってこない例の他に、比較的短い間に帰ってくる場合があります。時間的にはわずかの間ですが、その失踪した状況や帰ってきた状況、あるいは見つかった場所が異常であったために、神隠しと判断されるものです。こうした短期間の行方不明者は、しばしば特異な神隠し体験を語ります。我々の持つ異界のイメージや神隠しの正体は、主にこれらの証言に拠っているわけです。
天狗に攫われて空を飛んだという体験談や、見知らぬ人に誘われて日本中を旅したといった物語がそれに当たります。
実際には、これらの事例は神隠しの実在を証明するものではなく、この証言者・体験者も神隠しに関する観念、つまり異界観を周囲の人々と共通して持っていると言うことを示しているのです。つまりこれは謂わば共同幻想であり、周囲の人も納得する形で不思議が語られたという訳なのです。
ところで、かつて民俗社会では、隠れん坊(隠れ遊び)を夕方にはしてはならない、という禁忌が広く信じられていたと言います。大正時代の終わり頃には、東京でもこの民俗が生きていたようです。なぜかというと、神隠しに遭いやすいからという訳です。夕刻、彼は誰時には妖しいモノ達が跋扈すると信じられていました。そして隠れ遊びという行為が、現実世界の神隠しの模倣であると考えられるということが重要です。つまり、隠れ遊び、すなわち“遊び”の神隠しが、“現実”の神隠しを呼び寄せてしまうと考えられていたのです。
***
6−2.幻の楽園
また、神隠しには陰惨なイメージと甘美なイメージという、相反した二つのイメージが存在します。誘われる異界は恐ろしい世界の可能性もあり、一方ではもしかすると新たな世界、桃源郷や神仙の世界かもしれないのですから。
ですから、神隠し体験すなわち、異界体験は、良き神霊によってもたらされる場合、悪意を持った神霊によってもたらされる場合、の両方が考えられます。ただし、悪意の強い、大きくマイナス価を持った神隠しの場合は(喰われたり殺されたりして)隠された人間が戻ってくることはないだろうし、しばしの間連れ回す天狗のように、正負どちらとも言えない場合も多いのですが。
良き神霊によって誘われる異界としては、竜宮が最も有名でしょう。浦島太郎の話などを、浦島が住んでいた村の側から見ると、一種の神隠しとなることが解ると思います。しかし、こうした“良い”異界のイメージは、小松和彦の指摘するように、四方四季の庭・酒と御馳走など極めて類型化されたものであったと思われます。それ程当時の庶民にとっては、桃源郷は遠い存在であったと言う事なのでしょう。
しかし、打ち出の小槌を授かったりする場合を除くと、こうした“素晴らしい世界”を垣間見た者達の後日談はむしろ悲惨なものが多い様な気がします。「元の状態に戻った」などと言う場合もありますが、一度桃源郷を見てしまった者にとっては色あせた元の世界へ戻ってきても、元のように生きていくのは困難でしょう。私にはこうした“良き”神霊の誘いすら、巧妙な罠だったような気がしてなりません。
さて、ここで平田篤胤が記録した有名な神童寅吉の話をすべきなのかもしれません。が、私はこの話(だけではなくこの種の平田篤胤の幽冥界の話)が嫌いなので、申し訳ないのですが略します。有名な話なので、神仙界やら神隠しについての本なら大抵載っているので、そちらを参照して下さい。
***
それでは、神隠しを行う主体として想起された「神」あるいは「隠し神」とは如何なる存在だったのでしょうか。今回は神隠しの犯人について考えてゆきたいと思います。
これまで述べてきたように、神隠しにおいては、失踪者は現世とは異なる異界へと連れ去られたと考えられていた訳です。民俗社会では、本来日常では、こちら側の世界(現世)とあちら側の世界(異界・他界)とは強固な境界によって隔てられていると考えられていました。逆に言えば、こうした境界を設定する事で、人は安心して毎日を送る事ができたのです。しかし、時にこの境界が破れ、異界が露わになる事があります。そこに怪異や神隠しが生じてくるのです。

従って、異界へと人を誘う神隠しの主体としては、しばしば妖怪が想起されたのです。漠然と「神」あるいは「隠し神」と称する場合もありますが、こうした時の「神」は神社に祀られるような神霊ではなく、むしろ魔・妖怪に近いものと思われます。
ただし、この妖怪的な存在にしても千差万別で、複雑な様相を示している事は否めません。つまり、竜宮や鼠浄土、マヨイヒガなどの桃源郷の類、即ち人に対して好意的な異界からの使者も、一種の神隠しをもたらすと考えられるからです。彼らは神隠しの主体であるとはいえ、妖怪というより、やや神に近い存在かもしれません。
いずれにせよ、異界・他界から来たるモノ、境界を越えるモノが神隠しの犯人と考えられた訳です。例えば、山・川・海は他界と考えられていた代表的な場所ですが、神隠しの犯人の多くはそれらとの境界領域(山麓・野、川辺・橋、海岸等々)から訪れたのです。さらに、町の辻や天空もこうした異界へと通じる場所と言えるかもしれません。
***
ところで、神隠しを行う主体、隠し神の正体として、良く語られるのは鬼、狐、天狗です。まあ、天狗の場合は天狗攫いとか天狗隠しと言いますが。また狐については化かされた、鬼の場合には喰われたと表現するのが普通でしょう。なお、松谷みよ子は神隠し譚を記述するに当たって、その主体及び原因により、「天狗」、「山の神」、「何のものとも知れぬもの」、「狐・むじな」、「深山の婚姻」という風に章分けしています。
ただし、様々な神隠し体験の事例では、多くの場合天狗が犯人と考えられたようです。はっきり天狗と呼ばれない場合も、その風体や行動から天狗の類と判断できるのです。文化人類学者/民俗学者の小松和彦は、多くの場合神隠し信仰は、天狗信仰と深く結びついていたと述べています。従って神隠し体験も、天狗の持つ性質に合ったものとなるのです。空を飛んだり山中を歩き回ったり酒盛りをしたりするというのがそれです。
このようなこととは別に、神隠しにあった者の属性によって、その“隠し神”の主体が選ばれたと思われる面もあります。つまり、男の子が攫われた場合には(稚児用として)天狗が攫った、若い女性の場合には(妻とするために)山男が攫った、といった考え方です。
それでは、まずは天狗について考えてみましょう。民俗社会(近世以降)では、特に理由無く人を異界へと誘い、また戻すということ(神隠し)が行われた時に、その犯人として多くの場合天狗が想起されたと思われます。これは、仏教に敵対して僧侶を攫ったという平安期の天狗や、陰謀を巡らす姿を見せるために人間を異界へと誘った中世の天狗の系譜を引いていると考えられます。もっとも、後世になる程人間を隠す意図は曖昧になってしまっていますが。
なお、天狗全般についてはこちらにまとめてあります。
続いて伝承の多い狐についても見てみましょう。狐の行為は隠すと言うより騙すというべきもので、しばしば天狗などより悪質でした。狐は幻の異界(風呂と見えて肥壺、など)を作りだし、そこに人を誘い込むのです。天狗の場合と異なり、誘われた人間自体はそこを異質の場所とは思っていないのです。それでも狐に隠された者は人間界へと戻ってくる(正気に戻る)場合が多く、逆に失踪者が戻ってくる場合の神隠しの主体として、天狗に並んで狐が挙げられることになったと思われます。
もうひとつ、人を隠すモノに「鬼」があります。鬼の場合、隠された者は普通戻ってこれません。なぜなら、鬼が人を隠すのは“喰うため”か“妻とするため”と考えられていたからに他なりません。人を攫って喰う鬼としては酒呑童子の話などが有名でしょう。人を隠す良き神霊、悪しき神霊のうち、鬼は悪しき神霊の代表なのです。ただし、鬼が神隠しの主体とされることが少ないのは、人を喰ってしまうと考えられた故と思われます。つまり、戻らぬ失踪者が出た場合、普通は喰われたか否かは確かめようがないし、その正体が語られるはずもないというわけです。
この他に、山姥(隠し婆)や鬼女、河童なども神隠しを行うとされます。また、妖怪「隠れ座頭」もこうした一種ですが、これは元々は隠里(かくれざと)の転訛と思われます。異界の名称がいつの間にか異界へと誘うモノの名前へと変化したのです。
一方で、妖怪ならぬ人間(異人)によって人が攫われる話も伝えられています。それが「人さらい」の登場する「脂取り」や「纐纈城」といった説話です。人を攫って生血や脂を絞り取る、怖ろしい異人が失踪の原因として想起されたこともあったと思われます。
考えてみれば、神隠しの主体とされるモノの多く(天狗・鬼・狐)は幻想郷に棲む者達ですが、鬼も狐も八雲紫と関係が深いところが面白いですね。
***
さて、ここでもう一度神隠しの“真実”について言及しておこうと思います。神隠しの正体(現実)について、家出など自発的な動機のある場合については前記しました。
一方で本当に強制的に攫われた場合もあったと考えられます。例えば、中世では人売り・人買いが存在し、強制労働や売春などのために人身売買がなされていたと言います。このように売買するために誘拐されることは少なくなかったようです。誘拐の道具は大きな袋であり、人を攫う妖怪に「袋担ぎ」があることはこのような事実と結びついているのでしょう。さらに、「児肝取り」の伝承があります。中世の記録には、不治の難病を治療するために子供の生き肝を使用し、その調達のために誘拐が行われていたとあります。実際に事実かどうかは不明ですが、少なくともそうした「児肝取り」の噂があったことは確かです。また、このように外部に犯人を求めずとも、口減らしなどのために、家人に殺されてしまったという場合もあったでしょう。
神隠し譚の背後には、こうした現実の誘拐・殺人事件があったのかもしれません。
そして、微妙な問題を含む為にあまり言及されませんが、神隠しには、おそらく精神的な病によるものもあったのではないかと思われます。
「神隠し」とは、小松和彦の言葉を借りれば、現実世界の因果関係を無視し、失踪事件を「神隠し」という神秘的ヴェールに包み込むことなのです。“隠し神”のせいにすることで、自殺・事故による死・誘拐・逃亡・家出・駆け落ち・夜逃げ・口減らしのための殺人といったあらゆる事実を隠微してしまうものだったのです。
神隠しに遭った者は社会的に死んだと認識され、あらゆる現実的な「真相」は不問に付される事となるのです。ところが、時に神隠しに遭った者が帰ってくるときがあります。この際にも神隠しは、失踪していた間の失踪者の体験を覆い隠すヴェールとして働いたのです。人々は「神隠しに遭ったのだから」として共同体への復帰を認め、その失踪期間については不問に付したのです。
言い換えると、神隠しとは一つの社会的な装置だと言えるのです。つまり、失踪者を死者でも生者でもない中間的な状態に置く事で、社会から隠しておく装置だった訳です。そして隠された理由も、戻ってきた理由も、その間の出来事も総て人間を超えた“神”によるものとされ、不問に付されたのです。
吹きちらす紅葉や風の神かくし(毛吹草)
***
次に取り上げるのは、属性の一つ「スキマ妖怪」です。スキマ妖怪とは何か、またその周辺について探って行きたいと思います。
私はスキマ妖怪の一般的な定義というものをあまり良く知らないのですが、大体、人がいるはずのない方向から視線を感じ、振り返ると本来人が入れるはずがないような狭い隙間から何者かが覗いていたというハナシであると考えて良いと思います。
現代伝説に関するアンソロジーなどから、幾つか例話を引いて見ましょう。
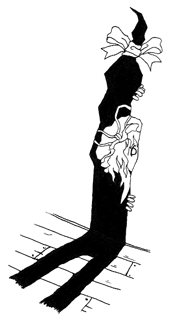
これらのハナシは、90年代には盛んに語られるようになっていたものと考えられます。渡辺節子は『走るお婆さん』でこれら隙間人間のハナシとそれに対する話者の対応について、三十センチのミニクジラの噂(千葉の沖合で潮を吹いていたらしい)や、高速道路を疾走する三十センチのお婆さんとの類似性を指摘しています。また、これらのハナシの出所としてメディアの可能性も指摘しています。テレビの宣伝(「ピクシーの巾だけあれば生きられます」)や「スキママン」(スズキコージ『大千世界の仲間たち』福音館書店1985)などを具体的に挙げています。テレビでこの話を聞いたという報告もあるそうです。
ただし、同書で渡辺も紹介しているとおり、江戸時代にも類似の噂が伝えられており、対象がわからない視線を感じたり、僅かな隙間に何かが居ることへの恐怖は、昔からのものと考えられます。すなわち、隙間人間(スキマ妖怪)の話はそうした昔からの流れを受け継いだものではないでしょうか。
江戸時代のスキマ妖怪とは、戸袋の中に潜む女です。ある家では主人が開けると問題なく開く戸なのに、召使いの男が開けようとすると、誰かが押さえているかのように酷く開け難い戸がありました。ある日召使いの男が、その開け難い戸を無理に開けたところ、戸袋の中から女が現れ、組み付こうとしたので、慌てて突き退けたところ消えてしまったという話です。これは江戸時代の随筆集、根岸鎮衛『耳袋』に「房斎新宅怪談の事」として記されたものです。
なお、この種の隙間女に類似したハナシに、箪笥の引出の中に紫色の着物を着た小さなお婆さんが居た、という怪談もあります(木原浩勝・中山市朗『新耳袋』第四十七話)。しばしば学校のトイレに出没した紫色の怪異がここにも顔を出して、隙間の怪と融合しています。
***