| 上白沢慧音さんの歴史講座「伝承文化と民間信仰」 | 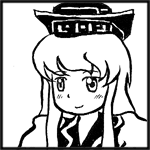 |
| ・天狗覚書 (※キャラクターはいらない、という人や変な会話調じゃなくて もっと普通の解説が読みたいという人はこちらへ) |
●蛇足の解説(天狗)の巻
| 上白沢慧音さんの歴史講座「伝承文化と民間信仰」 | 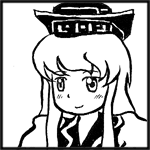 |
| ・天狗覚書 (※キャラクターはいらない、という人や変な会話調じゃなくて もっと普通の解説が読みたいという人はこちらへ) |
 |
目次 緒言 第一 原天狗 第二 夜叉としての天狗 第三 山神としての天狗 第四 怨霊としての天狗 第五 他界の天狗 結び 参考 |
緒言 さて、日本の妖怪史において大きな存在である天狗について述べよう。知識と歴史の半獣たる私、上白沢慧音が案内役を務めよう。やや退屈な所もあるかも知れぬが、暫くの間辛抱して呉れ給え。 天狗は極めて多様な側面を持った存在だ。中々短くまとめて語ることは困難だ。そもそもこうした存在はその注目の方法、語り方によって印象を大きく変えてしまうこともあり得る。だから、どのような姿勢で対象に向かうのかという点もおろそかには出来ぬ。そこで例えば、時間的変遷を追うという歴史学的手法に則った語り口もあろう。また、図像学的、形態的な面に注目して語ることも出来よう。所謂高い鼻を持った「鼻高天狗」と「鳥類天狗」に大別することができる、といった風にだ。 だが、今回は天狗の全体像を見渡す視点を提供するということを目的に、様々な様相を持って立ち現れる天狗それぞれが持つ性質から論じてみたいと思う。即ち、天狗を大陸の「原天狗」、反仏教的存在の「夜叉としての天狗」、山岳信仰に関わる「山神としての天狗」、人間が化した「怨霊としての天狗」、独自の天狗界を形作る「他界の天狗」、の五つに分けて語ろうと思う。 ところで、テングに対応する文字だが、天狗が代表的だが、天宮や天公、天狐という漢字を当てることもある。 *** 第一 原天狗 先ず最初に述べなくてはならないのは謂わば「原天狗」とも言うべき存在であろう。これは大陸での「天狗」と、それを直輸入した我が国初期の天狗像である。これは端的に言えば、虚空を飛ぶ尋常ならざるものを指す言葉で、むしろ天文現象であり、後の民俗伝承的な天狗とは異なるものだと言えよう。 そもそも大陸における天狗とは、尾を引く流星又は彗星の事を指す。実際に司馬遷の『史記』や『五雑俎』などの文献では音を発して飛ぶ星を天狗星と称している。さらに『史記』には、奔星(流星)の墜ちた所には狗の様な生き物が見られると記している。この一種の雷獣の如き伝承から流星を「天の狗」と呼んだのだと思われる。以下にその例を引用しておこう。 『史記』「天官書 第五」 「天狗、状如大奔星、有声。其下止地類狗(犬)、所堕及炎火。望之、如火光炎炎衝天。 其下円数項田處、上兌者則有黄色」 (天狗は、状(かたち)大奔星の如くにして声有り。地に止まるときは、狗に類(に)たり。 堕つる所、炎火に及ぶ。之を望むに火光の如く、炎炎として天を衝く。 其の下の円(まろ)きこと、数項(すうけい)の田処の如く、上兌(えい)なる者は則ち黄色有り) ※項(けい)とは面積の単位:1項=100畝 ※兌(えい)とは尖っている様子を表す 『漢書』「天文志」 「天鼓有音、如雷非雷、天狗、状如大流星」 (天鼓音有り、雷の如きも雷に非ず、天狗、状大流星の如し) 本邦では『日本書紀』舒明天皇九年(西暦637年)二月十一日の条(※二十三日と註されている場合もあった)に始めて天狗の文字が見られる。僧旻がこれは流星ではなく天狗だと言ったという話だ。原文と読み下しを挙げておこう。 「九年春二月丙辰朔戊寅、大星従東流西。便有音似雷。時人曰、流星之音。亦曰、地雷。 於是、僧旻僧曰、非流星。是天狗也。其吠声似雷耳」 (九年の春二月(きさらぎ)の丙辰(ひのえたつ)の朔戊寅(つちのえのとらのひ)に大きなる星、 東(ひむがし)より西に流る。便(すなわ)ち音有りて雷に似たり。時の人の曰はく、「流星の音なり」といふ。 亦は曰く、「地雷(つちのいかづち)なり」といふ。是に僧旻僧(みんほうし)が曰はく、 「流星に非ず。是天狗なり。其の吠ゆる声雷音に似たるのみ」と) なお、この記事の前の舒明天皇七年には彗星の記事が、同八年には日蝕や飢饉の記事があり、さらにこの記事の後、同九年の三月には日蝕の記事と蝦夷の反乱の記事が記されている。これは天狗が日蝕や彗星の出現と同様に、不吉な出来事の予兆と見られていた、あるいは天文の異常が地上の災厄をもたらすと考えられていたことをうかがわせる。 ところで、ここに現れる「天狗」を「アマツキツネ」と読ませている。これは『日本書紀』北野本の訓によるものと思われるが、この訓は、当該部分について『聖徳太子伝暦』に「僧旻法師曰、是謂天狐也」とあることから採用されたかと思われる。このアマツキツネ或いはアマツトトネという読みが後世天狗が狐と習合して行く伏線となるのだが、このことは又後で触れることもあろう。 ただし、大陸でも天狗は一筋縄ではいかないようだ。例えば天狗を魔性の女の霊とする考え方や、『山海経』(前漢末頃までに成立か)「西山経次三経」のように動物の一種と見るものもある。『山海経』では天狗を首の白い山猫のような生き物だとしている。また明時代の李時珍『本草綱目』(西暦1596年刊)によれば、天狗は穴熊(かん)の蜀地方での呼び名であると云う。魔性の女と見る伝承については、子供を攫う異形のもので、名を天狗あるいは偸生(とうせい)と称するという。これは未婚のまま死んだ娘の悪霊と言われ、新生児を彼岸に連れ去ることで代わりに自分が現世へ生まれ出ようとするのだそうだ。この辺りは自分の子とする為に攫う姑獲鳥などとは似て非なるものだな。この魔物から子供を護るために、狗毛符と呼ぶ毛玉を産着に縫いつけたり、狗圏という銀色の環や帯を付けたりしたそうだ。我が国の玩具で、赤ん坊の悪霊祓いの効果があるとされている犬張子もこうした大陸の伝承の影響を受けているのかも知れないな。 他にも天狗と関わりのあるかもしれない大陸の生き物がある。それは羽民と呼ばれる異人達だ。明時代の博物誌、王圻『三才図絵』(西暦1607年)には、羽民は海の東南の崖にある羽民国に住み、人に似ているが卵から生まれると記されている。その姿は頬長く嘴を持ち、赤目白首、羽毛が生えていて飛ぶことが出来るという。 なお、近世の知識人達は、これらの大陸の天狗ならぬ天狗達についての知識も持っていたようだな。例えば江戸期の滝沢馬琴による『烹雑の記』の「天狗図」には、山伏姿の天狗の他に、『山海経』の首の白い獣や人面鳥身の山の神、獅子の如き猛獣天狗、仙人の一種白鶴童、翼を持つ巨大な山鬼など大陸の文献に見られる天狗に似た異形の者どもが描かれているのだ。江戸時代の「怪奇鳥獣図巻」と題された絵巻にも「天狗(てんくう)」の項目があるが、これは明らかに『山海経』に拠るものだな。形態も首の白い獣のような生き物だ。詞書きには魔除けとなる、ともあるな。また、中世になっても、星の一種としての天狗は、「天狗星」や「天狗流星」として知られていたようだ。例えば15世紀の『応仁記』「一、乱前御晴之事」には次のような一節がある。 「夜亥の刻に坤方より艮方え光物飛び渡りける(中略)天狗流星と云物にて有りけるとかや」 流星にせよ獣にせよ、「原天狗」は後の天狗像とは随分と異なる物に見える。これらの異質な存在が、後世の天狗とどう繋がるのかについて少し考えてみよう。これはおそらく、本邦の天狗は、「原天狗」の持っていた天空を飛ぶモノ、天と地を繋ぐ大きな音を発する怪物、異変をもたらすモノ、という性質に山の神霊という要素が加えられるという形で作られたものなのだろう。今後述べて行くことになろうが、本邦の天狗はこれらの性質に仏教と御霊信仰の影響を加えることで語ることができると考えられるのである。 ここで大陸の天狗と、本邦の天狗との結びつきに関する説を一つ紹介しておこう。19世紀前半の小山田与清(ともきよ)『松屋筆記』によれば、我が国で元々天神の意味の天の君(アメノキミ)と呼ばれた霊獣が、天公と記されることで「てんぐ」と呼ばれるようになり、大陸の天狗と混同されたという。この説の真偽は解らないがな。 さらにもう一つ、今度は鳥のような姿の鳥類天狗の原型とも考えられるものを紹介しよう。それは「治鳥(じちょう)」という正体不明、おそらくは想像上の鳥である。これは大陸の博物誌に記されたものだが、本邦でこれを天狗に充てることがあるのだ。『本草綱目』によると、この鳥は越地方(広東省、広西省)の深山に棲む。大きさは鳩位で青い。その鳥の巣の有る木を伐ると、虎を使ってその人の家を焼き、復讐するという。………自分で言っておいて何だが、よく解らん奴だな。時に三尺(約90㎝)くらいの人に変じて蟹を取り、人家で炙って食べるという。こうなるとむしろ山人、山童の伝承に近いな。本邦の博物誌、寺島良安『和漢三才図絵』でも天狗は「治鳥」の項に載せられている。鳶のような姿の木の葉天狗や、菊岡沾涼『諸国俚人談』に見える川の魚を漁る鳥のような天狗の話の源流はこの辺りにあるのかも知れぬな。ただ、実際の所、江戸時代の学者が、大陸に天狗に相当する類似の怪物を見い出せなかったので、この化鳥に無理矢理こじつけたと言えないこともないがな。 |
◎おまけの絵は「天狗」
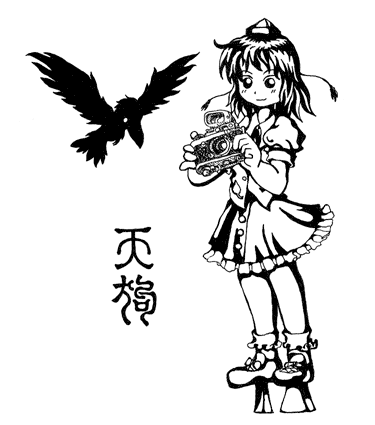
「さあ、今日も幻想郷の真実を撮りに出発よ!」